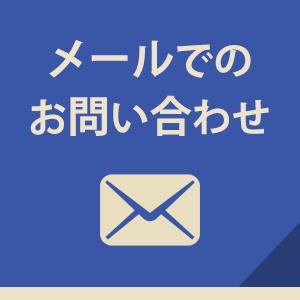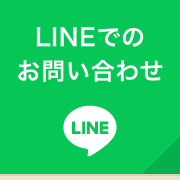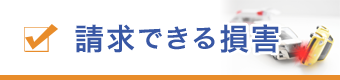横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》 - Part 3
むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害
まず,交通事故でむち打ち症になってしまった場合に,むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害について確認をしたいと思います。
むち打ち症は,頚部痛,頭痛,吐き気,耳鳴り,腕のしびれなど様々な症状が出現することが多いのですが,自賠責や労災では「神経系統の機能又は精神の障害」のうち「局部の神経系統の障害」の後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害等級と障害の程度は以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害12級 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 後遺障害14級 | 局部に神経症状を残すもの |
12級と14級の違いは,「がん固な神経症状」かどうかにあります。「がん固な神経症状」といわれても抽象的過ぎてよく分かりませんが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合に「がん固な神経症状」が存在すると判断されて12級の後遺障害が認定されます。
そうすると,今度は,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合というのはどのような場合かという疑問が出てきますが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合とは,基本的には,レントゲン,CT,MRIなどの画像によって症状の原因を確認できることを意味します。画像以外にも,症状の原因を確認できる検査等はありますが,少なくともむち打ち症においては画像で症状の原因を確認できることが重要です。
最初の自賠責用の診断書を確認する
むち打ち症で異議申し立てを検討するケースというのは,後遺障害が非該当であった場合が多いと思います。後遺障害が非該当であった場合,まず確認をしなければならないのが,最初の自賠責用の診断書です。自賠責用の診断書とは,受診した病院が保険会社に治療費の請求をする際に発行する診断書です。
診断書ですので「傷病名」を記載する欄があるのですが,傷病名を記載する欄に,「頚椎捻挫」,「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていないと,むち打ち症で後遺障害が認定されることはありません。
例えば,症状固定時に頚部痛の症状があり,後遺障害診断書の自覚症状の欄に「頚部痛」という記載があったとします。それにもかかわらず,最初の自賠責用の診断書に「右肘打撲」の傷病名しかなければ,交通事故で頚部痛の原因となる怪我を負っていなかったという判断をされてしまい,後遺障害は非該当になってしまいます。
異議申し立てをする際に,最初の自賠責用の診断書を確認してむち打ち症の原因となる傷病名が記載されていない場合には,何度異議申立てをしても非該当にしかなりません。
通院期間と通院頻度を確認する
最初の診断書に「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていたら,次に,通院期間と通院頻度を確認します。
むち打ち症の場合,自賠責は通院期間が6ヶ月を下回っている場合,交通事故と症状との間に因果関係がないと判断して非該当としてしまいます。
そうすると,通院期間を確認して6ヶ月を下回っていた場合は異議申立てをしても非該当のままということになってしまいます。ただし,6ヶ月を多少下回っているくらいなら,通院期間の条件をクリアする可能性があるので,厳密に6ヶ月を下回っていたら異議申立てをしても意味がないという訳ではないので注意が必要です。
また,通院期間が6ヶ月以上であったとしても,通院の頻度が極端に少なく,前回の通院から1ヶ月以上の間隔があるような場合にも非該当となってしまいますので,1ヶ月以上の間隔をあけずに通院していたか確認をする必要があります。
画像上の異常所見がないと異議申立てをしても意味がないか
後遺障害が認定されず非該当だったということで相談に来られる方から「レントゲンに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」,もしくは「MRIに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」と質問されることがあります。
結論から言うと,レントゲンやMRIなどの画像に何も異常が写っていなかったとしても14級の後遺障害に該当する可能性はあります。
レントゲンは,主に骨折の有無を確認するために撮影するものですので,むち打ち症の場合には,ほとんどのケースで異常所見は認められません。
また,MRIも,単純なむち打ち症の場合には異常所見はないケースが多いです。ただし,14級から12級に異議申立てをする際には,MRIで異常所見があることは必須といっていいです。
最初に説明したように,12級と14級の違いは「がん固な神経症状」があるかどうかで,「がん固な神経症状」とは,症状の原因が他覚的所見,主に画像所見で証明できる場合です。そうすると,頚部痛やしびれなどの症状の原因となる神経根の圧迫所見がMRIで確認できなければ,むち打ち症で12級が認定されることはほぼないと言っていいと思います。
むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする場合には弁護士にご相談を
むち打ち症のような神経症状の場合,怪我が軽度で症状の原因がはっきりしないということも多くあります。頚椎捻挫と診断されて通院期間が6ヶ月以上であっても非該当となってしまうこともあります。
そのため,むち打ち症の場合,異議申立てをして結果が出るかどうかの判断は非常に難しいので,むち打ち症で後遺障害の異議申立てを検討の方は弁護士へのご相談をお勧めします。
関連記事
休業損害,逸失利益,慰謝料に税金はかかりますか?
交通事故に遭うと保険会社から休業損害,逸失利益,慰謝料として相当額の賠償金が支払われます。
通常,金銭の支払いがあるとその支払いに対して所得税,住民税などの税金がかかってきます。
では,休業損害,逸失利益,慰謝料などの賠償金が支払われた場合,税金はかかるのでしょうか。特に,休業損害は給与の代わりとして支払われるもので,しかも,源泉徴収がされる前の金額を基準に支払われるので,所得税などの税金がかかってくるようにも思えます。
税金は法律によって課せられるものですので,法律が賠償金の課税についてどのように規定しているのか見てみたいと思います。
所得税法9条には非課税所得が列挙されており,同条1項17号には以下のように規定されています。
所得税法は,保険契約に基づいて支払いを受ける損害賠償金で,心身に加えられた損害については非課税所得になるとしています。
また,所得税法施行令30条に非課税所得の内容が具体的に規定されています。
所得税法施行令30条1号は,「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」,「勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるもの」を非課税所得としていますので,休業損害や逸失利益は賠償金として支払われても所得税はかからないということになります。
また,「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料」も非課税所得とされていますので,慰謝料にも所得税はかからないということになります。
なお,住民税は,所得税法の総所得金額の計算と同じ計算をすることになるので,賠償金には住民税もかからないということになります。
死亡事故の賠償金に税金はかかりますか?
死亡事故は,相続人が被害者(被相続人)の損害賠償請求権を相続するという構成をとるため,被害者(被相続人)の逸失利益や慰謝料の賠償金には相続税がかかってきそうにも思えます。
ところが,税務上は,相続人は被害者(被相続人)の損害賠償請求権を相続するものの,賠償金を相続したという扱いにはしておらず,相続人に支払われた賠償金は相続人自身の所得として扱っています。
そして,先ほど説明したように,賠償金は所得税法では非課税所得としていますので,死亡事故の賠償金に税金はかからないということになります。
また,当然ですが,相続人の固有の損害に対する賠償金は,非課税所得となりますので税金はかかりません。
なお,交通事故の被害者が一度賠償金を受け取って,その後,死亡したことにより,相続人が賠償金として支払われた金銭を相続した場合には,相続税がかかりますので注意してください。
人身傷害補償保険金には税金がかかることもある
人身傷害補償保険とは,交通事故の被害者が契約している保険会社から人身傷害事故によって被った損害について保険金が支払われるという保険で,加害者の責任の有無や被害者の過失割合に関係なく,保険約款の損害額の算定基準によって算定された金額が支払われるものです。
このように,人身傷害補償保険は,被害者に交通事故発生の過失があったとしても,それに関係なく約款で決まった保険金が支払われるので,被害者は,賠償金+保険金(自己過失分)を取得することになり,実質的には過失相殺がされずに賠償金をもらえた状態と同じになります。
人身傷害補償保険金は,基本的には,人身損害に対して支払われる保険金ですので,先ほど説明したように課税されることはありません。
しかし,被害者が死亡して相続人が人身傷害補償保険金を受け取った場合には,死亡保険金と同じ扱いを受けて所得税,もしくは相続税が課される場合があります。
賠償金の性質を有する場合
人身傷害補償保険は,加害者に責任がある場合にも保険金が支払われます。加害者に事故の責任がある場合,通常は,加害者から被害者に対して,加害者の責任割合(過失割合)に従って賠償金が支払われます。
そうすと,加害者の責任割合に相当する部分について人身傷害補償保険によって保険金が支払われた場合,その保険金は実質的には賠償金として支払われたのと同じですので,賠償金の性質を有しているということになります。
先ほどから説明をしているように,賠償金については課税されることはありませんので,人身傷害補償保険金が支払われても,賠償金の性質を有する場合には税金はかかりません。
被害者の過失割合に相当する金額
人身傷害補償保険は,死亡した被害者に過失がある場合,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分についても保険金が支払われます。
賠償金は,被害者に過失がある場合には,その割合に従って過失相殺され減額されますので,当然,損害額のうち被害者の過失に相当する部分については支払われません。
そうすると,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に支払われた人身傷害補償保険金は賠償金の性質は有していないということになります。
損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に人身傷害補償保険金が支払われた場合,税務上,死亡保険金が支払われた場合と同じ取り扱いをします。
死亡保険金は,被害者が保険料を負担していた場合には相続税がかかり,相続人が保険料を負担していた場合には所得税がかかります。
そうすると,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に人身傷害補償保険金が支払われた場合,損害保険料を被害者が負担していた時には,保険金に相続税がかかり,相続人が負担していた時には,保険金に所得税がかかるということになります。
保険会社が休業損害を支払ってくれない!
交通事故に遭って仕事を休んだ場合,通常は,休業損害証明書という書類を会社に作成してもらってそれに基づいて保険会社が被害者に休業損害を支払うことになります。
休業損害証明書は,休業の日数と事故前3ヶ月分の給与を記載する書類になります。会社員の方は,毎月固定給が支払われているので金額が一定しており,また,交通事故によって仕事を休んだことも会社が証明してくれるので,休業損害について争いになることはあまりありません。せいぜい,休業損害をいつまで支払うのかということで争いになるくらいです。
これに対して,自営業者の方は固定給があるわけではないので,休業損害の支払い基準となる日額の算定が難しいという場合がよくあります。また,仕事を休んだ日もしっかりと証明できないということもあります。
そのため,保険会社も自営業者の場合,すんなりと休業損害の支払いをすることはなく,ひどいケースでは,自賠責の休業損害の最低日額である5700円で計算した金額しか支払ってこないということがあります。もっとひどいケースでは,休業損害を計算できないと言って全く休業損害を支払ってこないということもあります。
裁判外で休業損害の支払いを保険会社に強制することはできない
保険会社が自営業者だからということで十分な休業損害の支払いをしてこない場合,まずは,一定額の休業損害を支払ってもらうよう交渉することになります。
その際,保険会社には事故前年の確定申告書を送ることになるのですが,それだけでなく,固定費が分かる資料を送って,被害者側で休業損害の支払い基準となる日額の算定をする必要があります。なぜなら,被害者側で計算をしないと先ほど説明したように最低の日額でしか支払ってこないということが多くあるからです。
それでも,被害者側で計算した金額を満額で支払ってくるというケースは少なく,被害者側で計算した金額を減額してしか支払ってこないことが多いです。
保険会社が休業損害を支払わなかったり,減額してしか支払ってこなかったとしても,裁判外では保険会社に休業損害の支払いを強制することはできません。
もちろん,粘り強く交渉を重ねてもいいのですが,仕事ができず収入が途絶えている場合には,生活ができなくなってしまうので,時間をかけて交渉を重ねることはできないということになります。
休業損害の支払いをしてくれないときは仮払仮処分
保険会社が休業損害の支払いをしてくれないときには,仮払仮処分という手続きの申立てを検討すべきです。仮払仮処分が裁判所で容認されれば保険会社に対して休業損害の支払いを強制することができます。
仮払仮処分の手続は,民事保全法23条2項の「仮の地位を定める仮処分」の1つですので,申立てを裁判所に認容してもらうためには,以下の要件を疎明する必要あります。
①被保全権利
②保全の必要性
③争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要であること
仮払仮処分が認容されるためにはこれらの要件を被害者側で疎明しなければならないのですが,通常,「疎明」というのは「証明」ほど証明力の高い証拠を提出しなくてもいいとされています。
しかし,仮払仮処分の場合,その後の正式な裁判(本案訴訟)で実際の損害額が仮払仮処分で認容した損害額を下回り,その払い過ぎの分を保険会社側で回収できないおそれがあるため,本案訴訟と同じ程度の証拠を提出する必要があります。
そのため,被害者本人が行おうと思っても簡単にできるものではないので,仮払い仮処分の手続は弁護士に依頼する必要があります。
仮払仮処分が認容された場合には,症状固定日まで仮払仮処分で認容された休業損害が支払われることになりますので,かなり実効性のある手段です。
ですので,保険会社と休業損害で争いがある場合には,できるだけ早めに弁護士に依頼して,場合によっては仮払仮処分の手続をとって保険会社に休業損害の支払いを強制できるようにした方が賢明です。
関連記事
任意保険会社の一括対応とは?
交通事故に遭った場合,治療費など被害者の損害については,一次的には加害者の自賠責保険が負担し,自賠責保険を超える損害について加害者の任意保険が負担することになります。そうすると,この建前を貫くと,被害者は,治療費などをまず自賠責保険に請求して,自賠責保険の限度額を超えたら任意保険に請求するという煩雑な手続きを取ることになってしまいます。
被害者がこのような煩雑な手続きを取らなくていいように,任意保険会社が自賠責保険の分も一括して対応して治療費等の支払いをすることを任意保険の一括対応といいます。
任意保険会社が一括対応をしてくれれば,被害者は治療費などを自己負担することなく,任意保険会社と病院との間で直接治療費に関するやり取りをしてもらえるので,被害者としては,間違いなく任意保険会社に一括対応をしてもらった方が得策です。
後遺障害分まで任意保険会社に一括対応してもらうと,後遺障害の認定が事前認定によってなされてしまうので,任意保険会社が被害者に不利になるような資料を提出してしまうなどのおそれがあるため,あまりよくありませんが,少なくとも治療費などの傷害分については,一括対応によるデメリットはあまりないので,症状固定までは任意保険会社に一括対応してもらった方がいいと思います。
ちなみに,任意保険会社が治療費の支払いを打ち切るというのは,任意保険会社が一括対応を拒否したというだけなので,その後も症状固定まで自己負担で通院して治療を受けても全く問題はありません。
一括対応を拒否した場合の治療費の負担
被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,治療費は被害者が自己負担することになります。多くの病院は,交通事故の治療は自由診療で対応していますので,一括対応を拒否した場合,病院から10割の治療費を請求されてしまうおそれがあります。
しかし,交通事故の場合,必ず自由診療でなければならないということはなく,健康保険を利用することができるので,一括対応を拒否した場合には,必ず健康保険を使って治療費を支払うようにしましょう。
また,一括対応を拒否した場合,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が作成されません。そのため,被害者が自分で病院に自賠責用の診療報酬明細書と診療報酬明細書を作成してもらうよう依頼する必要があります。なぜかというと,後遺障害の被害者請求のときに必要になるからです。
自賠責用の診断書は依頼すればほとんどの病院が作成してくれますが,自賠責用の診療報酬明細書については,健康保険を利用した場合には,病院は健康保険用の診療報酬明細書を作成しているので,自賠責用の診療報酬明細書は作成できないと言ってくるケースがあります。病院がこのように言ってきた場合にはやむを得ないので,被害者請求の際には,健康保険用の診療報酬明細書を付けるか,最悪,病院が発行する治療費の明細書を付ければ大丈夫です。
一括対応を拒否した場合の後遺障害の請求
被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,後遺障害の請求は,当然ですが,被害者請求で行うことになります。後遺障害の請求については,傷害分を一括対応してもらっていた場合でも事前認定より被害者請求の方がいいので,一括対応を拒否したことによる問題は特にないと思います。
ただ,先ほど言ったように,自賠責用の診断書や神慮報酬明細書など病院で作成してもらう資料もすべて被害者が依頼する必要があるので,その点だけ注意が必要です。
一括対応を拒否した場合には示談での解決が難しくなる
被害者がはじめから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,任意保険会社は,怪我の内容,治療状況,治療費の総額等の情報を全く知ることができません。そのため,後遺障害が認定されて,その後,被害者から任意保険会社に対して損害賠償の請求があった時点で,初めて任意保険会社は怪我の内容,治療状況,治療費の総額等の情報を知ることになります。
任意保険会社が一括対応をした場合には,任意保険会社が総額でどれくらい支払いをしなければならないかをあらかじめ想定することができるのですが,被害者が初めから一括対応を拒否した場合には,総額でどれくらい支払いをすることになるのかを想定できないため,被害者の請求は任意保険会社にとって不意打ち的な請求となってしまいます。
任意保険会社は,被害者から送られてきた資料をもとに賠償額の検討をするしかありませんが,その資料だけでは不十分だということになれば,任意保険会社が賠償額を検討するのに必要な資料を独自に集めるということになります。
もし,裁判外で十分な資料を集めることができないとなれば,任意保険会社は示談で解決せずに,裁判を起こして裁判所の手続によって資料を集めて争うということもあります。
実際に,私が担当した事件で,被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否して,軽度な怪我なのに2年近く通院を続けたという件では,示談で解決することはできず,裁判をすることになってしまいました。
任意保険会社の一括対応は,少なくとも症状固定までは被害者にとってデメリットは少なく,メリットの方が大きいので,多少,任意保険会社の担当者が気に食わなかったとしても,症状固定までは一括対応してもらうようにしましょう。
自賠責保険・共済紛争処理機構とは?
自賠責保険・共済紛争処理機構とは,自賠責保険(自賠責共済含む)からの支払いに関する紛争を公正かつ適確に解決することにより被害者の保護を図ることを目的とした自動車損害賠償保障法に基づいて設立された機関です。
自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページによると事業の内容は以下のとおりです。
1.自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停事業
2.自賠責保険・共済からの支払いに関する被害者等からの相談等を目的とする事業
3.その他本機構の目的を達成するために必要な事業
このように書いてあると分かりにくいですが,基本的には,自賠責で判断された後遺障害,有無責,重過失減額に関して不服を申し立てる機関と考えて間違いはないと思います。
特徴としては,弁護士,医師,学識経験者(元裁判官,法律学者,交通工学の専門家等)などの交通事故賠償の専門的知識を有する専門家が紛争処理委員となって,紛争処理の審査を行っているという点です。
そのため,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,自賠責の異議申立ての判断よりも非常に詳細な内容となっており,こちらに不利な判断だったとしても,判断の理由を読むと納得せざるを得ないという点があります。
また,軽度の高次脳機能障害のように画像上の異常が確認しにくいような事案で自賠責では異常所見が見落とされていたような事案でも,しっかりと画像上の異常所見を発見してくれて,高次脳機能障害の後遺障害を認定してくれたということもありました。
個人的には,自賠責保険・共済紛争処理機構でダメだったら諦めがつくと思えるくらい,しっかりとした判断をしてくれると感じています。
異議申立てをしてもダメなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ
後遺障害,有無責,重過失減額に関する不服を申し立てる方法としては,自賠責の異議申立てもありますが,自賠責の異議申立てと自賠責保険・共済紛争処理機構はどのような関係にあるのでしょうか。
建前としては,自賠責の異議申立てをしてから自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の調停の申請をするという関係にあるわけではありません。しかし,あとで説明するように自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,裁判外では最終的な判断でそれ以上争うことができませんので,いきなり自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をすると,事務局の方からできれば自賠責の異議申立てをしてからにして欲しいという要望がきます。
確かに,自賠責の異議申立ては,調査事務所というところが判断するのですが,こちらは,追加の検査や追加の資料を求めてくることがあり,申立人が提出した資料以上の資料を集めてから判断することがあるのですが,自賠責保険・共済紛争処理機構は,申請人が提出した限りの資料でしか判断しないことが多いので,先に,自賠責の異議申立てをして,十分な資料が整ってから,自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をした方がいいと思います。
紛争処理申請に必要な資料
自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理の申請は,書面でしかできない,いわゆる書面主義をとっています。紛争処理の申請に必要な資料は以下のとおりです。
①紛争処理申請書
②紛争に関する申請者の意見を記載した書面
③同意書
④委任状及び委任者の印鑑証明書(代理申請の場合)
⑤交通事故証明書
⑥自賠責保険会社又は共済組合からの通知書(回答書)
⑦申請者の意見を裏付ける資料(診療報酬明細書,事故発生状況報告書,実況見分調書,画像資料,医師の意見書など)
規定上は,自賠責保険・共済紛争処理機構は独自の調査をすることができるので,新たな検査や資料の提出等の依頼を申請者に対してすることができるのですが,これまで,自賠責保険・共済紛争処理機構から新たな検査や資料の提出を求められたことがないので,申請者の意見を裏付ける証拠を十分にそろえてから申請することをお勧めします。
自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は裁判外では最終判断
先ほども説明をしましたが,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,裁判外では最終的な判断となるので,裁判以外では争うことはできません。
もちろん,「裁判外」での最終的な判断なので,裁判を起こして争うことはできますが,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,提出した資料を十分に検討して詳細な内容となっていますので,正直,自賠責保険・共済紛争処理機構で不利な判断があったときに,これを裁判で争うの相当難しいのではないかと思います。
そのため,自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の申請は,申請者の意見を裏付ける証拠が十分にそろってから行う必要があります。
事実婚の配偶者が交通事故で亡くなったらどうなる?
通常,法律上の婚姻関係のある夫婦の一方が交通事故で亡くなった場合,配偶者は,亡くなった配偶者の逸失利益などの損害賠償請求権を相続するという法律構成によって,加害者に対して損害賠償の請求をすることになります。
しかし,事実婚の場合,配偶者が交通事故によって亡くなっても,もう一方の配偶者は,法律上,亡くなった配偶者の損害賠償請求権を相続することはできません。
多くの裁判例は,この不都合を回避するために,事実婚の配偶者の扶養請求権の喪失を根拠として加害者に対する逸失利益などの損害賠償請求を認めるという法律構成をとっています。
扶養請求権の喪失を根拠に損害賠償請求を認めている多くの事例は,事実婚の夫が交通事故の被害者で,事実婚の妻が専業主婦だったり,パート収入しかなく事実婚の夫に扶養されているという事例です。
このように,事実婚の奥さんが専業主婦だったり,もしくはパート収入くらいしかない状況で事実婚の夫に扶養されているという場合であれば,扶養される権利の喪失を根拠として,加害者に対して損害賠償の請求をすることは比較的簡単に認められます(夫に前妻との間の子供がいるというような場合はまた問題が生じると思いますが)。
同性同士の事実婚の配偶者が交通事故で亡くなったらどうなる?
現在では,男女間の事実婚だけでなく,渋谷区などが戸籍上の性別が同じ同士の方たちにパートナーシップ証明書を交付するなど,同性同士で事実婚のような関係にある方もいらっしゃいます。そうすると,今後は男女間の事実婚だけでなく,同性間の事実婚の場合も含めて,配偶者が交通事故で亡くなったときに,どのような法律構成によりもう一方の配偶者が加害者に対して損害賠償の請求ができるかを考える必要があるのではないでしょうか。
もちろん,同性間の事実婚の場合で,一方の配偶者がもう一方の配偶者に扶養されているという状況であれば,男女間の事実婚の場合と同じように,扶養請求権の喪失を根拠とすることが可能だと思います。
しかし,同性間の事実婚の場合,一方がもう一方に扶養されているという状況は少ないのではないでしょうか。おそらく,二人ともが仕事を持ち一人でも生活できるだけの収入を得て生活をしていることの方が多いように思います。そうすると,同性同士で事実婚にある二人が一人で生活できるだけの収入を得ていたとすると,扶養請求権の喪失を根拠として加害者に対する損害賠償請求を認めるという法律構成はとることができないのではないかという疑問が生じます。
もちろん,この疑問は,男女間の事実婚の場合でも,扶養されていた妻が交通事故で亡くなった場合には生じてきます。
これまでの裁判例を見ていると,扶養されていた妻が亡くなった場合には,固有の慰謝料の請求しか認めず,扶養されていた妻の家事労働の逸失利益の損害賠償請求は認めていないものが多いように思います。これは,事実婚の場合には,あくまでも相続ができないため,扶養請求権の喪失を根拠とするという立場が貫かれているためだと考えられます。
そうすると,やはり同性同士の事実婚の場合,亡くなった配偶者の逸失利益の損害賠償請求は認められないというケースが多くなってしまうように思います。
法律上の婚姻関係にある場合には,扶養されていない場合でも,配偶者がなくなった場合にはその逸失利益の損害賠償が認められることと比較すると,均衡がとれていないように感じます。
固有の慰謝料は当然に請求できる
事実婚の配偶者が交通事故で亡くなった場合でも,もう一方の配偶者に固有の慰謝料請求は認められます。亡くなった配偶者の逸失利益の請求が認められないような場合には,固有の慰謝料を増額するなどして多少調整を図ることになると思います。
もちろん,固有の慰謝料の請求が認められるためには,事実婚の関係にあることを請求する側で証明することが必要です。
同性同士の事実婚の場合には,先ほど挙げたパートナーシップ証明書などは有力な証拠になるはずです。そのほかには,同居して夫婦同然の生活をしていたことを示すことができればいいので,住民票と当事者の陳述書などでも大丈夫だと思います。
解決実績
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
関連記事
交通事故に強い弁護士が死亡交通事故の民事の解決方法について解説!
自賠責保険の仮渡金とは?
交通事故に遭って被害者の方が亡くなったり,負傷した場合に,ご遺族や被害者本人に葬儀費や治療費など当座の費用がないという場合に,自賠責保険に対して一定額を請求できるという制度があります。これを自賠責保険の仮渡金といい,自動車損害賠償保障法17条で被害者やそのご遺族に認められた権利になります。
仮渡金の制度は,請求手続きを簡便にして迅速に一定金額を支払うことにより被害者やご遺族の保護を図るという点にあります。
このような制度趣旨であるため,仮渡金は被害者や遺族だけが請求でき加害者が請求することはできません。また,自動車損害賠償保障法16条の被害者請求と比べて,請求書に添付する書類が少なく迅速に支払いがなされるという特徴があります。
どのような場合に仮渡金を請求できる?
仮渡金が請求できる場合,請求できる金額は以下の表のとおりです(自動車損害賠償保障法施行令5条)。
| 仮渡金が請求できる場合 | 金額 |
|---|---|
| 死亡した場合 | 290万円 |
| ①脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合 ②上腕または前腕の骨折で合併症を有する場合 ③大腿または下腿の骨折した場合 ④内臓の破裂で腹膜炎を併発した場合 ⑤14日以上病院に入院することを要する傷害で,医師の治療を要する期間が30日以上の場合 | 40万円 |
| ⑥脊柱の骨折 ⑦上腕または前腕の骨折 ⑧内臓の破裂 ⑨病院に入院することを要する傷害で,医師の治療を要する期間が30日以上の場合 ⑩14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
| ⑪11日以上医師の治療を要する傷害を受けた場合 | 5万円 |
仮渡金の請求に必要な資料
仮渡金の請求に必要な資料は以下の表のとおりです。
| 傷害の仮渡金請求 | 死亡の仮渡金請求 |
|---|---|
| ①支払請求書 ②請求者の印鑑証明書 ③交通事故証明書 ④事故発生状況報告書 ⑤診断書 | ①支払請求書 ②請求者の印鑑証明書 ③交通事故証明書 ④事故発生状況報告書 ⑤死亡診断書または死体検案書 ⑥省略のない戸籍(除籍)謄本 |
自賠法16条の被害者請求の場合,傷害分の請求であっても診断書のほかに診療報酬明細書が必要になりますが,仮渡金の請求には診療報酬明細書は必要ありません。
仮渡金は自賠責保険会社から返還を求められることがある
仮渡金は,上記のとおり迅速な支払いをすることにより被害者やその遺族を保護することを目的としていますので,支払いの時点で,加害者に事故発生の責任があるかどうか(有無責)の調査をしっかりとせずに支払いがされます。
そのため,後から実は加害者に事故発生の責任がなく被害者だけに事故発生の責任があるという場合や被害者の損害が支払った仮渡金を下回る場合には,仮渡金を支払った自賠責保険会社は,仮渡金を受け取った被害者またはその遺族に対して返還請求することができます(自賠法17条3項)。
2016年の「ながらスマホ」等の交通事故1999件、死亡事故27件
2016年に「ながらスマホ」や携帯電話を利用中に発生した交通事故は1999件だったそうです。そのうち死亡事故は27件もあったそうです。
記事によると,携帯電話使用による交通事故の発生は,2011年と比較すると約1.6倍になっており,特にスマホなどの画面を見たり操作したりして起きた事故は約2.3倍と急増しているそうです。昨年8月には,運転中にスマホゲームのポケモンGOをしていて交通事故を起こし被害者が死亡したという事件があり話題になりました。
取締り強化や広報の活動をするそうですが,運転中の「ながらスマホ」による交通事故は今後も増えていきそうです。そうすると,「ながらスマホ」が原因の交通事故の刑事裁判も増えていきそうです。
先ほどの運転中にポケモンGOをしていて死亡事故を起こした運転手は,懲役1年2月の実刑判決になっています。
死亡事故なので実刑判決は珍しいことではなく,ポケモンGOをしていた「ながらスマホ」だからといって,ほかの同じような運転手の著しい過失によって発生した死亡事故と比べて特別に重い刑が下されているという感じはしません。
実刑判決になるかどうかというのは刑事事件の話になりますが,次に「ながらスマホ」によって交通事故を起こしてしまった場合,民事事件でどのような影響があるか考えてみたいと思います。
運転手の過失割合が大きくなる
過失割合は,事故態様を基本に,事故ごとの個別の事情を考慮して決定することになります。個別の事情とは,法定速度を超過していた,酒気帯び運転をしていたというような事情です。
携帯電話が普及して時間が経っていますので,運転中に携帯電話を利用していたという事情は,以前から過失割合を決定する個別の事情として考慮されることは多くあり,運転手の過失割合が+10になるという事情でした。そうすると「ながらスマホ」も,当然,運転手の過失割合を大きくする事情になります。
ただ,「ながらスマホ」は単に運転中に携帯電話を利用していたという場合に比べて,完全に前方からスマホの画面に目を移し,前方を見ていない時間も長くなるので危険性が高い行為といえます。そうすると,運転手の過失割合を+15から+20にするような事情と考えてもいいように思います。
慰謝料増額事由になりうる
運転中に危険な行為をして交通事故を起こした場合には,危険な行為を行ったという事情は慰謝料を増額する事由になります。例えば,社会的に大きな問題となった飲酒運転は,きわめて危険性の高い行為になるので慰謝料増額事由になります。
「ながらスマホ」はスマホ画面を注視してしまうため,前方を見ていない時間が長くなることから極めて危険性の高い行為です。
そうすると「ながらスマホ」も慰謝料を増額する事由になりうると考えられます。
軽度な事故だと運転手の「ながらスマホ」が分からないことがある
先ほどの運転中にポケモンGOをしながら死亡事故を起こしてしまったような事件は重大事件ですので,警察もきちんと捜査をして運転中にスマホを利用していた事実を通信会社の利用履歴などをとって裏どりをしているはずです。
ところが,軽度な事故だと,警察は当事者から事故の状況を聞いて実況見分調書に事故の状況を記録しておくくらいの捜査しかしてくれませんので,事故の当事者からスマホを使っていたという申告がない限り,運転手が「ながらスマホ」をしていたという事実が分からないということもあり得ます。
見通しのいい道路での事故など,こんなところで事故が起きるなんておかしいと思った場合には,運転手が「ながらスマホ」をしていた可能性もあるので,警察に捜査をするよう促してみて下さい。
自賠責保険の重過失減額とは?
自賠責保険の重過失減額とは,交通事故の被害者に7割以上の過失がある場合に,被害者の過失割合に従って定められた減額割合に基づいて自賠責保険金を減額するという制度です。
被害者の過失割合が10割のときには免責となり自賠責保険金はおりませんので,被害者の過失割合が7割以上10割未満のときに重過失減額が適用されるということになります。
被害者の重過失による減額割合は以下のとおりです。
| 減額適用上の被害者の過失割合 | 減額割合 | |
| 後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |
重過失減額の可能性がある場合は被害者請求で意見を述べた方がいい
このように自賠責保険金の重過失減額が認められてしまうと,傷害の損害(治療費,休業損害等)では2割,後遺障害,死亡の損害は2割から5割も減額されてしまいます。
例えば,死亡事故で被害者に7割の過失がある場合には,死亡の自賠責保険金3000万円から減額分600万円が控除されて2400万円になってしまいます。
自賠責は「事故発生状況報告書」という書類で交通事故の状況を把握するのですが,もし,交差点の信号の色などに争いがあり,被害者不利な判断がされた場合には重過失減額が適用されるおそれがあるときは,被害者請求の際に事故状況について被害者に有利な過失割合となる事故状況であったという意見を述べる必要があります。
以前,私が担当した事件で,二輪車が反対車線に転回(Uターン)したところ反対車線を直進してきた自動車に衝突されて,二輪車の運転手が重度の障害を負ったという交通事故がありました。転回した二輪車と直進の自動車では,過失割合は7割対3割となります。
ところが,実況見分調書を取り付けたところ自動車に時速20km以上の速度超過があったことが分かりました。
自動車に時速20km以上の速度超過があれば,当然,過失割合は7割対3割から被害者に有利に変更になるので,被害者の過失割合は7割を下回ることになります。
そこで,被害者請求の際に,実況見分調書を証拠に被害者の過失割合が7割以下になるという意見を述べたところ,重過失減額されずに後遺障害等級どおりの自賠責保険金が支払われました。
自賠責の調査事務所は,重過失減額の調査については,加害者側の保険会社に加害者側の意見を照会するなどの調査はしていないようなので,被害者が証拠を付けて意見を述べれば,被害者に有利に判断される可能性が高いように思われます。
重過失減額されるおそれがあるときは積極的に意見を述べるようにしましょう。
自賠責で重過失減額されていると裁判でも不利になるおそれがある
裁判所は,自賠責が判断した後遺障害の認定に拘束されないので,自賠責と違った後遺障害の判断をすることができます。
これは,過失割合についても同じで,自賠責で重過失減額がされたとしても,裁判で過失割合を争うことは可能です。
しかし,やはり自賠責で重過失減額がされていると,裁判所も自賠責の判断と大きく異なった判断をすることはためらいがあると思います。
そうすると,自賠責で重過失減額がされていると,裁判所も被害者に不利な過失割合で判断する可能性が高くなってしまうおそれがあります。
重過失減額を争う方法
自賠責で重過失減額をされても争う方法があります。
まずは,自賠責に対して重過失減額に関する異議申立てをして争うという方法です。
最も有力な証拠は警察が作成した実況見分調書ですので,実況見分調書に過失割合を被害者に有利に変更できるような事情があれば,その事情を主張して異議申立てをすることになります。
次に,自賠責に対する異議申立てでも重過失減額に変更がなかった場合には,自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理の調停で争う方法があります。
自賠責保険・共済紛争処理機構とは,自動車損害賠償保障法に定められた公的な機関で,自賠責保険や自賠責共済の支払いに関して争いがあるときに,中立・公正な立場で紛争の解決を図ることを目的としています。
調停の申請には費用が掛かりませんので,後遺障害に関して異議申立てをしても変更がなかった場合によく利用する機関です。
当然,重過失減額についても争うことができますので,異議申立てをしても変更にならなかったときには,自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の調停の申請をすることを考える必要があります。
ただし,自賠責保険・共済紛争処理機構で下された判断は,裁判外でこれ以上争うことはできませんので,十分な証拠をそろえて調停の申請をする必要があります。
減収がないからといって後遺障害逸失利益が認められないわけではない
後遺障害逸失利益とは,後遺障害によって将来的に得られなくなってしまった収入を損害とするものです。
後遺障害逸失利益を損害として考えるときに,実際に減収が発生していない場合に逸失利益が認められるかという問題があります。この問題については,差額説と労働能力喪失説という考え方があります。
基本的には,差額説に基づいて逸失利益を考えることになるのですが,差額説の考え方は,「交通事故がなければ被害者が得られたであろう収入と,事故後に現実に得られる収入との差額」を損害とするので,この考え方を厳格に貫くと,減収が発生していない場合には逸失利益は認められないということになってしまいます。
そうすると,表題の公務員の場合,事故後に減収が発生していないということが多いので,公務員に逸失利益は認められないのではないかという問題が出てきてしまいます。
かつての最高裁判例には,後遺障害等級が5級とわりと重い後遺障害であったにもかかわらず,減収がないというだけで逸失利益を否定したものもあります(最判昭和42年11月10日)
しかし,減収がなければ逸失利益がないとしてしまうと,公務員が被害者になった場合,多くのケースで逸失利益がないとされてしまいます。
上記の最高裁判例の後に出された最高裁判例では,原則として減収がなければ逸失利益が認められないとしながらも,後遺障害によって被害者に経済的不利益が認められるような特段の事情がある場合には,減収がなくても逸失利益が認められるという判断をしています(最判昭和56年12月22日)。
減収がない場合にどのような事情があれば後遺障害逸失利益が認められるのか?
では,後遺障害によって被害者に経済的不利益が認められる特段の事情とは,どのような事情をいうのでしょうか?先ほどの最高裁判例は,以下のような判断を示しています。
「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには,たとえば,事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって,かかる要因がなければ収入の減少を来しているものと認められる場合とか,労働能力喪失の程度が軽微であっても,本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇給,転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など」
この最高裁判例では,減収がなくても逸失利益が認められる事情として,本人の努力によって減収が生じていない場合,職業の性質から特に昇給,転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合を上げています。
これ以外にも,裁判例を見てみると,勤務先の配慮によって減収が生じていないという事情がある場合にも特別の事情があると判断しているものもあります。
公務員の給与制度から後遺障害逸失利益を考える
公務員は,減収がないという理由で逸失利益が争われることが最も多い職業だと思います。多くのケースでは,減収がないどころか収入が増えているということもあります。
しかし,事故後に減収がなかったり収入が増えたりすることが多いのは,公務員の給与制度によるところが多いと思います。
特に,地方公務員は,「級」と「号給」の組み合わせによって給与額がきまるという給与制度になっており,よほどの事情がない限り「級」や「号給」が下がることがないので,給与が下がることもありません。
地方公務員の給与制度は,条例によって具体的に定められているのですが,「級」や「号給」の上がり方も規定されています。規定の詳細については説明を省きますが,基本的な条件を満たしていれば,毎年決まった数の「号給」が上がり,一定の「号給」に達すると「級」が上がるというような規定になっています。
そうすると,基本的に,公務員は一定の条件を満たしていれば,毎年給与が上がっていくということになります。
毎年決まった数の「号給」が上がる条件の1つに出勤日数があり,この出勤日数を下回ると「号給」は決まった数上がりません。
交通事故に遭って重傷を負うと,仕事を長期間休むようになるため,決まった数「号給」が上がる条件の出勤日数に達しないということがあります。このような場合でも,「号給」が下がらないので,事故後の給与額は事故前の給与額を下回りません。
しかし,「号給」が決まった数上がらないと,「級」が上がるのが遅くなるという事態が生じます。
先ほど説明したように,地方公務員は「級」と「号給」の組み合わせによって給与額が決まる給与制度ですので,「級」が上がるのが遅くなると,事故に遭う前に比べて給与額が上がるペースが遅くなるという不利益が生じます。
しかも,「号給」が決まった数以上に上がる条件は極めて厳しいため,普通に仕事をしている限りでは,毎年,決まった数の「号給」しか上がらず,事故の時に上がらなかった「号給」を後から取り戻すということはほぼ不可能です。
そうすると,一度,給与額が上がるペースが遅くなると定年まで毎年,昇給幅が抑えられるという不利益が生じます。
このように,公務員の場合は,減収がなくても毎年のように昇給幅が事故前に比べて抑えられるという不利益が生じることがあります。このような観点から,逸失利益が生じているという主張をすることができると思います。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。