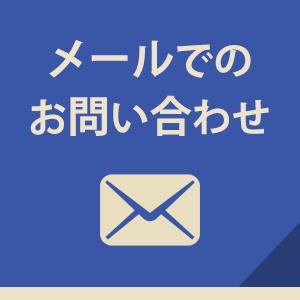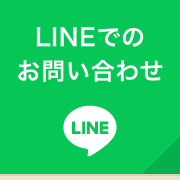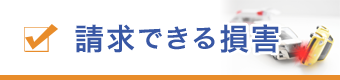横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》 - Part 4
基本的な入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法
入通院慰謝料とは,交通事故によって傷害を負い治療のために入通院をしたことに対する慰謝料をいいます。
入通院慰謝料という言い方ではなく,傷害慰謝料という言い方をすることもあります。基本的には,いずれも同じ意味で使っています。
地域によって多少異なるのですが,全国的の多くの地域では,入通院慰謝料(傷害慰謝料)は,入通院期間を基礎に赤い本の別表Ⅰを基準に計算をします。
通院期間とは事故日から症状固定日までの期間を言い,実通院日数(実治療日数)とは違います。
また,赤い本とは,日弁連交通事故相談センター東京支部が出している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という本のことを言います。
おそらく,表紙が赤いので赤い本と呼ばれているのだと思います。
ちなみに,赤い本は一般の書店では販売しておらず,一般の方は,東京の霞が関にある弁護士会館3階の日弁連交通相談センター東京支部の窓口で購入する,または,同センターのホームページにある申込書をファックスするかで申し込みをして購入するしかありません。
別表Ⅰは,縦軸が通院期間,横軸が入院期間となっており,それぞれの期間で重なり合う欄にある金額を基準に入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算するという使い方をします。
分かりにくいので具体例で説明をしたいと思います。
例えば,交通事故によって右足を骨折して事故日から症状固定日までに1ヶ月の入院と1年間の通院をしたというケースで説明すると,入院1ヶ月と通院1年(12ヶ月)が重なり合う欄には,183万円という金額が記載されていますので,このケースの入通院慰謝料(傷害慰謝料)は183万円ということになります。
むちうちは別表Ⅱを使用して入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算する
先ほどの赤い本の別表Ⅰというのは,レントゲンで骨折が確認できるような他覚的所見が認められる場合に使用します。
他覚的所見がない場合には,赤い本の別表Ⅱを使用して,入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算をすることになります。
何が違うかというと,単純に別表Ⅰの方が金額が高く,別表Ⅱの方が金額が低いという違いになります。別表Ⅰの方が25%くらい金額が高くなっています。
むちうちは他覚的所見がない場合に下される診断ですので,別表Ⅱを使用して入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算することになります。
むちうちの場合入院することはあまりないのですが,別表Ⅰと別表Ⅱの比較をわかりやすくするため,先ほどの例を使って別表Ⅱの入通院慰謝料(傷害慰謝料)を見てみると,入院1ヶ月と通院1年(12ヶ月)が重なり合う欄は,136万円という金額が記載されています。
そうすると,むちうちで1ヶ月入院して退院後1年通院した場合の入通院慰謝料(傷害慰謝料)は,136万円ということになります。
別表Ⅰとくらべると,47万円も低くなってしまいます。
「『入通院期間を基礎として』別表Ⅱを使用する」に変更になった
実は,平成28年版の赤い本から,むちうちの入通院慰謝料の計算基準が多少変更になりました。以前は以下のような基準になっていました。
むちうちの入通院慰謝料の計算基準(変更前)「むちうち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用する。この場合,慰謝料算定のための通院期間は,その期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする」
このような説明になっていたため,むちうちの場合,単純に通院期間を見るのではなく,実治療日数×3を通院期間としていました。
例えば,先ほどの例で12ヶ月通院したけど,自通院日数は40日であった場合,以下の計算式ように4ヶ月を通院期間としていたということになります。
40日×3=120日 120日÷30日=4ヶ月
このように,むちうちの場合は,別表Ⅰよりも入通院慰謝料(傷害慰謝料)が低くなる別表Ⅱを使用し,さらに通院期間も実際よりも短くなってしまうので,2段階で入通院慰謝料(傷害慰謝料)が低く計算されるという基準になっていました。
しかし,平成28年の赤い本からは以下のように基準が改訂されました。
むちうちの入通院慰謝料の計算基準(変更後)「むちうち症で他覚的所見がない場合等は入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用する。通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度を踏まえて実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする」
このように,むちうちの場合であっても,いきなり実通院日数(実治療日数)の3倍を通院期間とするのではなく,ほかの傷害と同じように,原則的には事故日から症状固定日までの通院期間を基準に別表Ⅱを使用して入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算をし,例外的に通院が長期間にわたる場合に,実通院日数×3を通院期間として入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算すると変更になりました。
先ほどの例でいうと,12ヶ月の通院が長期の通院ではないとした場合,通院期間は4ヶ月ではなく12ヶ月として入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算するということになります。
このように基準が変更されたのは,むちうちの裁判例を検討すると,実通院日数×3を通院期間として別表Ⅱで入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算した金額よりも,多くの裁判例で高額な入通院慰謝料(傷害慰謝料)を認定していたということが要因のようです。
おそらく,裁判所はむちうちでも事故日から症状固定日までの期間を通院期間として入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算をすることが多いのではないかと考えられます。
むちうちでも入通院慰謝料(傷害慰謝料)を安易に譲歩しないこと
このように,むちうちの入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算の基準は変更されましたので,保険会社が以前のように実通院日数×3を通院期間として入通院慰謝料(傷害慰謝料)を計算してきても安易に譲歩して示談してはいけません。
できる限り,事故日から症状固定日までの期間を通院期間として入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算するように交渉する必要があります。
関連記事
歯牙障害とは
歯牙障害とは、一定数以上の歯に「歯科補てつを加えた」場合に認められる後遺障害です。
「歯科補てつを加えた」とは、現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損(歯冠部の体積の4分の3以上を欠損)に対する補てつをいいます。
分かりやすく言うと、歯が折れてブリッジにしたり、歯がなくなったところにインプラント治療を施したような場合を言います。
歯牙障害の後遺障害等級と障害の程度は以下の表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害10級 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 後遺障害11級 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 後遺障害12級 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 後遺障害13級 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 後遺障害14級 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
後遺障害逸失利益が認められないことが多い
歯牙障害の後遺障害で、最も特徴的な点は後遺障害逸失利益を認められないことが多いということです。
先ほど、「歯科補てつを加えた」の例としてブリッジやインプラントにした場合を上げましたが、これは虫歯などの歯周組織の疾患でも行うことがあります。
歯周組織の疾患でブリッジやインプラントにしたからといって仕事ができないという人はいません。
そうすると、当然、交通事故で歯を欠損したり喪失してブリッジやインプラントにしても仕事ができないということにはなりません。
歯牙障害のすべてのケースで逸失利益が認められないということなく、歯を食いしばって力を入れるような仕事の場合には労働能力に影響があると判断されることもあります。
しかし、歯牙障害で逸失利益が認められるケースでも後遺障害等級どおりの労働能力喪失率は認められない可能性が高いです。
歯牙障害の後遺障害の場合、逸失利益が認められる後遺障害と違って、原則、逸失利益は認められず、例外的に逸失利益が認められると考えて間違いないと思います。
そうすると、歯牙障害で逸失利益の請求をするのであれば、被害者側で積極的に歯牙障害によって労働能力を喪失しているという証拠を出す必要があるということになります。
既存障害があることが多い
歯牙障害は既存障害があること多いという特徴があります。
既存障害とは、事故に遭う前からすでに後遺障害があることを言います。例えば、歯牙障害でいえば、事故に遭う前から歯周組織の疾患によって一定数の歯にブリッジやインプラントにしていたような場合を言います。
既存障害がある場合、事故によって同一部位(同一系列)に障害が生じても加重障害にならなければ、その事故によって新たな後遺障害が残ったという判断がされません。
加重障害とは、事故前から障害が残存していたところに交通事故によって新たな障害が加わった結果、事故によって生じた新たな障害が既存障害の程度よりも重くなった状態のことを言います。
例えば、交通事故に遭う前から5歯に歯科補てつを加えていた場合、13級の既存障害があるということになります。
そうすると、交通事故によって5歯に歯科補てつを加えても、13級を超える障害が残っていないので加重障害とならず、7歯以上に歯科補綴を加えて初めて加重障害となり後遺障害が認定されることになります。
この場合、後遺障害は、現存障害で12級、既存障害で13級と認定されることになります。
このように既存障害があって加重障害になった場合は、12級の自賠責保険金224万円から13級の自賠責保険金139万円を差し引いた85万円が自賠責保険金として支払われる金額になります。
既存障害があって加重障害になった場合には、賠償上でも、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率が差し引かれることになります。
先ほどの例で、仮に逸失利益が認められるとした場合、12級の喪失率14%から13級の喪失率9%を差し引くことになるので、現存障害12級、既存障害13級の労働能力喪失率は5%ということになります。
また、後遺障害慰謝料も同じように差し引かれることになるので、先ほどの例でいえば、12級の290万円から13級の180万円を差し引いて、後遺障害慰謝料は90万円となってしまいます。
歯牙障害の場合、もともと虫歯治療等で多数の歯に歯科補てつを加えていることが多いので、既存障害があることが非常に多いです。
私が今まで経験した歯牙障害の事例では、ほぼ既存障害がありました。
そうすると、先ほど説明したように、歯牙障害の場合、後遺障害逸失利益が認められないことが多いので、ただでさえ賠償金がほかの後遺障害よりも小さくなってしまうのに、後遺障害慰謝料も等級どおりの慰謝料とならないので、さらに賠償金が小さくなってしまうということになります。
インプラントは問題の宝庫!
上部構造に高額な素材を使ってしまった場合
交通事故によって歯を欠損すると、歯科医がインプラント治療をするということが多くのケースで見られます。
インプラント治療で最も困るのは、交通事故で保険会社がすべての治療費を支払ってくれると勘違いして、オールセラミックなど非常に高額な上部構造を使用してしまうことがあるということです。
インプラント治療はもともと1本15万円から30万円程度もかかるため、治療費が高額になりやすいのですが、上部構造に高額な素材を使用されるとさらに1本あたり10万円から20万円程度金額が上がってしまうので、治療費が非常に高額なります。
そうすると、保険会社から、上部構造に高額な素材を使用することは、交通事故と相当因果関係がないとしてインプラントの治療費を争われることになってしまいます。
そして、裁判でも上部構造の高額な素材は審美目的と判断されてしまい、相当額まで治療費を減額されてしまうということがあります。
インプラントの交換費用は認められにくい
また、以前は、インプラントは数年したら交換しなければならないと言われていたような時代もあったので、インプラントの交換費用が数年おきに必要になるとして、インプラントの交換費用を認めた裁判例もあったのですが、個人的な感覚としては、今はインプラントの交換費用をそのまま認めるということはなくなってきているように思います。
まだ、保険会社側から主張されたことはないんですが、インプラントの永久保証をうたっているような歯科医院もあるので、メンテナンスをしていれば定期的に交換する必要はあまりないのかもしれません。
そのかわり、どの歯科医院もインプラントのメンテナンスは必須で、定期的にしないといけないと説明していますし、保証の条件に定期的なメンテナンスをしているということがあげられていますので、メンテナンス費用については、将来分も含めて認められる可能性が高いと思います。
実際に、歯牙障害の後遺障害だけの事案で裁判をした時もメンテナンス費用は将来分も含めて認められました。
後遺障害慰謝料もそれほど増額しない
後遺障害逸失利益が認められない後遺障害の場合には、後遺障害慰謝料を増額するというのが定番です。
しかし、同じく逸失利益が認められにくい男性の外貌醜状と比べると歯牙障害の場合、後遺障害慰謝料の増額幅が小さいように思います。
しかも、先ほど説明したように、歯牙障害の場合、既存障害より後遺障害慰謝料がすでに減額されていることが多いので、増額されても後遺障害等級に見合った金額まで増額しないということも多くあります。
歯牙障害の後遺障害が認定されたら弁護士に相談しよう
ただし、歯牙障害の後遺障害が認定される場合は、顔の骨を骨折していたり、顔に大きな傷が残ってしまい、神経症状や外貌醜状の後遺障害が認定されていることも多くあります。
ほかの後遺障害が認定されている場合には、逸失利益が認められる可能性が高いため、賠償金も高額になる可能性があります。
それでも保険会社は、低額な逸失利益しか認めない可能性が高いので、歯牙障害の後遺障害だけしか認定されていな場合も、ほかの後遺障害が認定されている場合も弁護士に相談しましょう。
歯牙障害の解決実績
歯牙障害の場合、後遺障害逸失利益が認められにくいという話をしましたが、当事務所では、歯牙障害の後遺障害事案でも、後遺障害逸失利益を認めさせた上で、高額の賠償金を獲得した事案がありますので、歯牙障害の後遺障害が認定されたという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
労災保険金は交通事故の賠償金から控除される
通勤中に交通事故に遭った場合には労災保険が利用できるため、治療費や休業補償を労災保険から支払ってもらっているということがあります。その場合、労災保険から支払われた治療費や休業補償は、加害者側から支払われる交通事故の賠償金から控除されることになります。
労災保険金が交通事故の賠償金から控除される理由は、労災保険金が損害の填補という性質を有していること、また、労災保険金の根拠規定である労働者災害補償保険法に労災保険金が被害者に支払われたときには、被害者の損害賠償請求権が給付者に移転する(代位する)と規定されていることにあります。
このように書くと難しく感じますが、例えば、治療費を労災保険で支払ってもらったのに、賠償金からも支払ってもらうことになると、治療費を二重で支払ってもらうことになってしまい、被害者が得をするという事態が生じます。このように、被害者が交通事故に遭って得をするような状況はよろしくないので、労災保険金によって損害が填補された場合には、その分を賠償金から差し引きますよ、ということです。
ただし、労災保険から支払われるもののうち特別支給金は、損害の填補という性質も有していませんし、代位の規定もないため、交通事故の賠償金から控除されませんので気を付けましょう。
交通事故の賠償金から控除されるのは、以下の労災保険給付になります。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
遺族(補償)年金は誰の賠償金からいつまでの分控除される?
遺族(補償)年金は、「労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の受給資格者に対して給付されるものです。
遺族(補償)年金は、受給資格者のうち第一順位の者に給付されます。一方、賠償金は、死亡した被害者の賠償金を相続することになるので、相続人であれば請求することができます。そうすると、遺族(補償)年金を受給する相続人と受給しない相続人がいて、それぞれが交通事故の賠償金を請求できるということになります。
このような場合に、遺族(補償)年金の控除は、遺族(補償)年金を受給する相続人の賠償金だけから控除され、遺族(補償)年金を受給していない相続人の賠償金からは控除されません。遺族(補償)年金を受給している相続人の賠償金だけから控除することは、最高裁判所でも認められています(最判平成16年12月20日)。
また、年金ですので毎年一定金額が給付されますが、賠償金から控除する年金は将来支払われる分も含めて控除するのかという問題があります。
この問題については、最高裁は、「現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に控除の対象になる」と判断しました(最判平成5年3月24日)。つまり、すでに支給されている分と支給されていることが確定した分だけ控除され、将来分については控除されないということになります。
過失相殺がある場合の過失相殺による減額と労災保険金の控除の順番
これまで説明してきたように、労災保険金は交通事故の賠償金から控除されることになるのですが、被害者に過失があり過失相殺しなければならないときには、過失相殺による減額と労災保険金の控除はいずれが先になるかという問題があります。
例えば、治療費として労災保険から100万円の休業(補償)給付を受けていたとします。裁判では、休業損害が200万円であると認められましたが、被害者の過失が20%で加害者の過失が80%とされたとします。
この場合に、過失相殺による減額が先であれば、以下のような計算になります。
200万円(休業損害)×80%(加害者の過失)-100万円(休業給付)=60万円
過失相殺による減額が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は60万円ということになります。
次に、労災保険金の控除が先の場合であれば、以下のような計算になります。
(200万円(休業損害)-100万円(休業給付))×80%(加害者の過失)=80万円
労災保険金の控除が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は80万円ということになります。
このように、過失相殺による減額を先に行うよりも、労災保険金の控除を先に行った方が最終的に獲得できる賠償金は大きくなります。
しかし、最高裁は、過失相殺による減額を先に行い、その後に労災保険金の控除をするという判断をしています(最判平成元年4月11日)。
労災保険金の控除には損害項目による制限がある
労災保険金は、労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除することはできないという制限があります。以下の表は、労災保険給付と控除できる賠償金の損害項目を表にしたものです。
| 労災保険給付 | 賠償金の損害項目 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 治療費関係 |
| 休業(補償)給付 障害(補償)給付 傷病(補償)年金 | 休業損害と後遺障害逸失利益の合計額 |
| 遺族(補償)給付 | 死亡による逸失利益 |
| 葬祭料 | 葬儀費用 |
| 介護(補償)給付 | 介護費、将来介護費 |
慰謝料から労災保険金が控除されることはない!
労災保険は、業務災害や通勤災害によって労働者に負傷、疾病、障害、死亡の結果が生じたときに、労働者の保護や社会復帰を目的とした制度ですので、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料という考え方はありません。
それに対して、交通事故の賠償は基本的には民法に基づくので、民法710条に定められている精神的損害に対する賠償請求が認められます。
先ほど説明したように、労災保険金は労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除されないので、労災保険給付と同質性のない慰謝料については、労災保険金が控除されないということになります。
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、正式には「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的として、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を行うADR機関です。
法律相談、和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。和解あっせんの進め方は、担当弁護士によっても異なるのですが、ほとんどの担当弁護士は、被害者と加害者側の保険会社もしくは共済組合の担当者からそれぞれの話を聞いて、基本的には弁護士基準で計算した賠償金で和解を勧めることが多いです。
交通事故紛争処理センターは本部のほかに7つの支部と3つの相談室がある
交通事故紛争処理センターは、東京本部のほかに、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡に支部があり、さいたま市、金沢、静岡に3つの相談室があります。
どこでも利用を申し込めるというものではなく、申立人の住所地又は事故地に対応した本部、支部、相談室で利用を申し込むことになります。
一度、本部、支部、相談室のいずれかに利用を申し込んだ場合、そこが気に入らないからといって申し込みを取り下げてほかの本部、支部、相談室に利用を申し込むということはできません。例えば、本人がさいたま相談室で利用を申し込んで、途中から東京の弁護士に依頼した場合でも東京本部に利用の申し込みをすることはできませんので注意が必要です。
交通事故紛争処理センターを利用できない場合
加害者側の保険会社又は共済組合が保険協会又は共済連合会に属していない場合
交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との示談をめぐる紛争を解決することを目的としていますので、加害者側に保険会社又は共済組合がついていない場合には利用することができません。
保険会社及び共済組合は以下の組織に加盟している保険会社又は共済になります。
・日本損害保険協会
・外国損害保険協会
・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
・全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
・全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
紛争の種類によって利用できない場合
また、紛争の種類によっても交通事故紛争処理センターを利用できない場合があります。以下の場合には交通事故紛争処理センターを利用することができません。
①自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
②搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、被害者(側)が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
③自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争
交通事故紛争処理センターで解決するメリット
無料で利用できる!
交通事故紛争処理センターは、最初に説明したように担当弁護士が和解のあっせん等を行いますが、利用するにあたって費用はいりません。無料で利用することができます。そのため、賠償金があまり望めないような交通事故の場合に交通事故紛争処理センターを利用しても費用倒れになることはありません。
迅速に解決することができる!
交通事故紛争処理センターのホームページのQ&Aをみると以下のような説明があります。
「人身損害の場合は、通常3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。物損の多くの場合は、2回程度で取り扱いが終了しています。」
交通事故の裁判の場合ですと、裁判を3回行っただけでは判決はもちろん和解にもならないので、3回で解決できれば迅速な解決といえます。
審査会の判断に保険会社及び共済組合は拘束される
和解のあっせんによって解決ができない場合、審査会の判断で解決することになります。審査会はあっせん担当の弁護士とは違う3人の弁護士で構成され、あっせん担当の弁護士から事案や争点の報告受け、両当事者の主張を確認した上で賠償金の判断を行います。
審査会が下した賠償金の判断は、被害者側は納得がいかなければ、その判断で解決することなく裁判を起こすことができます。
それに対して、保険会社及び共済組合は、どんなに納得がいかない内容の賠償金であっても審査会の判断に拘束され、裁判を起こすことはできません。
実際に交通事故紛争処理センターを利用してみての感想
これまで何件もの交通事故を交通事故紛争処理センターに申立てをして解決をしましたが、事案とあっ旋の担当者によって交通事故紛争処理センターのメリットを享受できるかどうか変わってくると思っています。
後遺障害、過失相殺が争点となっていると早期に解決ができない可能性が高い
後遺障害や過失相殺が争点になっていると保険会社や共済組合はかなり力を入れて争ってきます。後遺障害が争点となる事案では、裁判だと通院した病院のカルテなどを取り付けて意見書を作成したりするのですが、交通事故紛争処理センターでもカルテなどを取り付けて意見書を作成して後遺障害を争う保険会社や共済組合があります。そうすると、3回で終わることはなく、1年以上時間をかけても解決しないということがあります。現に、今も交通事故紛争処理センターでそのような事案を担当しています。
交通事故紛争処理センターの担当弁護士がきちんとあっ旋をしない場合には早期に解決できないことが多い
交通事故紛争処理センターでの解決は、初めに説明した通りセンターの担当弁護士があっせんをしますので、早期に解決できるかどうかは、センターの担当弁護士によるところが非常に大きいです。
中には、保険会社がむち打ちの事案で医療記録を取得して後遺障害14級を争うと言ってきたときに、むち打ち事案で後遺障害14級が認定されている場合には、14級の後遺障害があることを前提に賠償案を出すので、医療記録の取り付けをしても無駄だとはっきり言ってくれて、保険会社側の医療記録の取り付けを認めずに解決をしてくれたような素晴らしい担当弁護士もいます。
しかし、一方で、早期解決に向けてきちんとあっ旋をしない担当弁護士もいるので、そのような場合には解決まで長引くことを覚悟しなければなりません。きちんとあっ旋をしない弁護士は、裁判のように一方が主張をしたらもう一方に反論をさせて、さらにその反論に再反論をさせてということを漫然と繰り返すという特徴があります。やはり、交通事故紛争処理センターは裁判とは異なりますので、そのことを意識して何度も主張と反論を繰り返させるような進め方はやめて欲しいなと思います。
賠償金の金額だけに争いがある事案が向いている
交通事故紛争処理センターでの解決が向いているのは、賠償金の金額だけに争いがあるという事案だと思います。具体的に言うと、例えば、後遺障害は10級が認定されて争いがなく、もちろん過失にも争いがない、争いがあるのは、後遺障害慰謝料が弁護士基準の550万円を下回っているという点だけというような事案です。
極端な話、このような事案であれば、1回で解決することもあります。
それと、先輩弁護士にいちゃもんをつけることになってしまうのであまり大きな声では言えませんが、担当弁護士の方、損害額計算書だけでなく当事者の申立書や証拠ももう少し見て欲しいなって思います。
交通事故紛争処理センターの所在地一覧
東京本部
〒163-0925 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
TEL.03-3346-1756 FAX.03-3346-8714
札幌支部
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241 FAX.011-261-4361
仙台支部
〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング11階
TEL.022-263-7231 FAX.022-268-1504
名古屋支部
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491 FAX.052-581-9493
大阪支部
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277 FAX.06-6227-9882
広島支部
〒730-0032 広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421 FAX.082-245-7981
高松支部
〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階
TEL.087-822-5005 FAX.087-823-1972
福岡支部
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881 FAX.092-716-1889
さいたま相談室
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271 FAX.048-650-5272
金沢相談室
〒920-0853 金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階
TEL.076-234-6650 FAX.076-234-6651
静岡相談室
〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル4階
TEL.054-255-5528 FAX.054-255-5529
個人事業主の休業損害は簡単じゃない
交通事故に遭って仕事を休んだ場合,休業損害を請求することができます。
通常,会社員の方であれば,「休業損害証明書」を会社に作成してもらって,それを保険会社に提出すれば,休業損害を支払ってもらえます。
しかし,個人事業主は会社に休業損害証明書を作ってもらうことはできません。
つまり,個人事業主の場合,休業損害証明書によって収入の日額や休業日数を確認することができないので,休業損害証明書から休業による損害額を把握することができないということになります。
保険会社は,休業損害証明書によって休業による損害額を把握して支払いをするため,これを確認することができない個人事業主の方の場合,休業損害を最低額でしか支払ってこないということが多くあります。
そのため,個人事業主の被害者の方が求める休業損害を保険会社に支払わせることは簡単じゃなく,揉めることが非常に多くあります。
売上を請求することはできないけど固定費を休業損害として請求できる
個人事業主の方から休業損害の相談を受けると,多くの方から売上を休業損害として請求できないのかという質問を受けます。
確かに,個人事業主の方が仕事を休めば,それだけ売上が下がりますので,売上金額そのものを休業損害として請求したいと思う気持ちはよくわかります。
しかし,売上を上げるためには経費が必要となりますが,休業したことによって支払いを免れる経費がありますので,売上そのものを休業損害として認めてしまうと,支払いを免れた経費の分まで休業損害に含めてしまうことなってしまいます。
そのため,売上そのものが休業損害として認められることはありません。
原則として,売上ではなく所得金額が個人事業主の休業損害となります。
もっとも,家賃など毎月固定でかかる経費(固定費)については,休業しても支払わなければならない経費ですので,休業損害として請求することができます。
また,青色申告で確定申告をしている場合には,青色申告特別控除という特典を受けています。
青色申告特別控除とは,所得金額から最高65万円を控除して課税所得を下げることができるというものです。
これは,実際に支出したものではないので経費には当たりませんので,休業損害に含めることが可能です。
そうすると,所得金額に固定費と青色申告特別控除額を足した金額が個人事業主の休業損害ということになります。
確定申告をしていない場合や事業に直接関係ない費用を経費として計上していた場合は?
個人事業主の所得金額や固定費は,基本的には事故前年の確定申告書と添付書類から把握することになります。
では,確定申告をしていなかった場合にはどうなるのでしょうか?
この場合でも何かしら収入がなければ生活ができないので休業損害は認められます。
ただし,確定申告書以外の資料で収入や経費を証明しなければならないので,正確な休業損害の証明はかなり難しいといっていいでしょう。
正確な休業損害の証明ができない場合は,賃金センサスを基準に,平均賃金の50%から60%くらいの金額を収入とみて,日額の計算をすることになってしまいます。
そうすると,日額は1万円を下回るような金額になってしまいます。
また,個人事業主の方だと,事業と直接関係ない費用を経費として計上しているということがあります。
例えば,家族の携帯電話の料金を経費として計上いるような場合です。
このような場合にも,やはり,経費として計上している費用が事業と直接関係ないものであることを被害者側で証明しなければなりません。
先ほど例にあげた携帯電話の料金であれば明細があるので明細と確定申告書の決算書から事業と直接関係のない費用であることを立証できるかもしれませんが,一般的には,事業と直接関係のない費用であることを立証することはかなり難しいです。
整形外科よりも接骨院?
交通事故でむち打ち症くらいの怪我しか負っていないと,整形外科に通院をしても医師があまり話も聞いてくれないし,治療もしてくれないという話を依頼者の方からよく聞きます(もちろん,むち打ち症でも,しっかりと話を聞いてくれて,治療もしてくれる整形外科の先生がいらっしゃるという話も聞きます!)。
そのような場合,整形外科ではなく,接骨院(整骨院を含みます)に通院をしているという方が多くいらっしゃいます。
そして,接骨院に多く通院されている方は,大抵,整形外科よりも接骨院の方が治療効果を感じるということをおっしゃいます。
確かに,むち打ち症の場合,整形外科では,簡単な診察をして薬を処方するぐらいで,しっかりとリハビリをしてくれないというところもあるようです。
それに対して,接骨院の場合は,30分から1時間かけてマッサージをしてくれるので,むち打ち症による痛みやだるさが一時的に軽減するので,接骨院の方が治療効果を感じるという方が多いのだと思います。
私も仕事の疲れをとるためによくマッサージに行きますので,被害者の方がそのように感じるのは共感できますし,おそらく私も交通事故でむち打ち症になったら接骨院に行ってマッサージを受けると思います。
接骨院の通院は整形外科医の指示が絶対に必要?
交通事故のポータルサイトを見ていると,接骨院の通院には整形外科の医師の指示が必要とか,接骨院に通院する必要があることを診断書に書いてもらわないと,接骨院の施術費を払ってもらえない可能性があります,というような記載があります。
もちろん,整形外科の医師が接骨院に通院するよう指示をしたり,通院する必要があると診断書に記載してくれれば,保険会社が接骨院の施術費の支払いを争ってきても,医師の指示や診断書を根拠に支払いを求めることができると思います。
しかし,実際に,整形外科の医師が,積極的に接骨院への通院を指導することはほとんどないですし,接骨院に通院する必要があるという内容の診断書を書いてくれることもほとんどないと思います。
普通に考えたらわかることですが,整形外科の医師の立場からすれば,自分が診察や治療をしているのに,どうして接骨院への通院が必要なのかと疑問に感じるはずです。
むち打ち症の事件を数多く扱ってきましたが,実際に,整形外科医が積極的に接骨院への通院を指示していたというケースは1件もありませんでした。
せいぜい,接骨院で施術を受けることを了承するというような内容の診断書が作成されているのを見たことがあるくらいです。
接骨院への通院は,過度な通院でなければ,保険会社は医師の指示がなくても施術料を支払っているので,整形外科医の指示は絶対に必要という訳ではないと思います。
ただし,後から接骨院の施術費を争われた時の対策をしておく必要はあります。
私の場合は,依頼者の方が接骨院にも通っているという場合には,整形外科の医師に接骨院に通っていることを伝えるようにして下さい,とアドバイスをしています。
そうすると,整形外科の医師は,カルテに接骨院に通院していると記載をしてくれます。
カルテに接骨院に通院していたという記載があり,医師が明確に接骨院に通院することを中止するように言っていなければ,事実上,整形外科医が接骨院に通院することを了承していたと主張することが可能だからです。
また,実務上も,医師の指示がなければ接骨院の施術費を認めないという判断はしておらず,施術の必要性・有効性,施術期間,施術内容,施術費の相当性に関して具体的な主張立証があれば接骨院の施術費の賠償を認める傾向にあります。
接骨院への過度な通院は治療費打ち切りの原因になるので控えましょう
整形外科医の指示がなくても接骨院の施術費が認められるとしても,接骨院への過度な通院は控えた方が賢明です。接骨院への過度な通院は,治療費の打ち切りの原因となってしまいます。
接骨院は,1つの部位の施術で何千円という施術料の請求をするので,どうしても施術料が高額になってきます。
そのため,接骨院に過度な通院をしていると施術費が非常に高額になってしまうために,保険会社としても早期に治療費の打ち切りに動くようになってしまいます。
接骨院への通院は多くても1週間に1回程度にした方が治療費の打ち切りにあう可能性を低くできると思います。
関連記事
脊柱変形の後遺障害
脊柱とは,頚椎,胸椎,腰椎,仙骨,尾椎から構成されるもので,躯幹を支持し,同時に上肢や下肢からの力学的並びに神経学的情報を脳に伝えるための重要な組織のことを言います。
脊柱の機能は,躯幹の支持性,脊椎の可動性,脊髄などの神経組織の保護の3つに集約されます。
ただし,後遺障害の認定においては,脊柱の後遺障害は,頚部及び体幹の支持機能,保持機能,運動機能に着目したものであるため,仙骨と尾椎は脊柱に含まれません。
脊柱変形とは,脊椎骨折,圧迫骨折,脱臼により脊椎に変形を残す後遺障害です。
圧迫骨折は、レントゲンで骨折していることが確認されれば後遺障害が認定されますので、脊柱変形の後遺障害の原因で1番多い骨折になります。
脊椎の変形の程度によって以下の表のとおり6級,8級,11級に区分されています。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 | 具体的な基準 |
|---|---|---|
| 後遺障害6級 | 脊柱に著しい変形を残すもの | エックス線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で以下のいずれかに該当する場合 ①脊椎圧迫等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの。 ②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じるとともに,コブ法による側弯度が50度以上となっているもの。 |
| 後遺障害8級 | 脊柱に中等度の変形を残すもの | エックス線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で以下のいずれかに該当する場合 ①脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの ②コブ法による側弯度が50度以上であるもの ③環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの。 ⅰ60度以上の回旋位になっているもの ⅱ50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの ⅲ側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの |
| 後遺障害11級 | 脊柱に変形を残すもの | ①脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの ②脊椎固定術が行われたもの ③3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの |
脊柱変形の労働能力の喪失が問題になった経緯
以前,脊柱変形は6級と11級しかなく,後遺障害を認定する具体的基準も現在とは異なるものでした。
例えば,6級は,「レントゲン写真上明らかな脊柱圧迫骨折または脱臼等に基づく強度の亀背・側弯等が認められ,衣服を着用していても,その変形が外部から明らかに分かるもの」という内容でした。
現在の具体的基準は客観的な基準になっていますが,以前は,「衣服を着用していても,その変形が外部から明らかに分かるもの」というやや主観的な条件も含まれていました。
このような基準であったため,著名な整形外科の医師が「着衣の上から分かる程度の変形であれば6級(喪失率67%)とすることは,それがもたらす労働能力の低下となると過大評価である」と指摘したということがありました。
また,11級については,「脊椎圧迫後の変形では,労働能力の実質的喪失は,ほとんど無いに等しい」という指摘もありました。
このように,著名な整形外科医が脊柱変形の労働能力の喪失に疑問を呈したことから,脊柱変形によって労働能力は喪失しないという主張が保険会社側からされるようになったのです。
基本的に脊柱変形でも労働能力の喪失は認められるべき!
脊柱変形は,これにより頚部及び体幹の支持機能,保持機能,運動機能が低下するという点を評価して後遺障害とされているものです。
頚部や体幹の支持機能,保持機能,運動機能が低下すれば,当然,労働能力に影響をありますので,基本的には,脊柱変形による労働能力の喪失は認められるべきだと思います。
裁判官が中心となって編集された「交通関係訴訟の実務」にも以下のような説明があります。
「脊柱変形は,脊椎骨折に由来する器質的障害であるが,脊柱の支持性及び運動性を減少させるとともに,骨折した脊椎の局所に疼痛や易疲労性を生じさせ得るものといわれている。そして,障害等級認定基準の見直しの経緯及び内容を踏まえると,高度の脊柱変形については,基本的には現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられる。」(森冨義明,村主隆行編著「交通関係訴訟の実務」207頁)
このように,裁判所も少なくとも高度の脊柱変形である6級については,等級通りの67%の喪失率があると考えています。
では,11級の脊柱変形についての労働能力喪失についてはどのように考えられているのでしょうか。
同じく「交通関係訴訟の実務」では以下のように説明されています。
「脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には,このような取り扱いが相当ではないこともあり得る。このような場合には,被害者の職業,神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断することになろう」(森冨義明,村主隆行編著「交通関係訴訟の実務」207頁)
このように,実務では,軽微な脊柱変形であったとしても,直ちに労働能力の喪失が否定されるわけではなく,被害者の職業,神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断するという取り扱になっています。
私が担当した交通事故で11級の脊柱変形が認定された事案では,脊椎の運動機能は低下しているので,周辺の筋肉がこわばることで痛みの症状が現れるということが多く,また,疲れやすくなったり疲れが取れにくくなったりで仕事に影響のあるケースばかりでした。
そのため,11級の脊柱変形の事案でも,労働能力の喪失を否定されたという件は1件もなく,すべてのケースで11級の喪失率20%がそのまま認められました。
11級の脊柱変形ですと,労働能力の喪失が争われやすいですが,脊柱変形により出現している症状とその症状による仕事の支障の程度をしっかりと主張することが労働能力の喪失を認めさせる上で大事なのではないかと思います。
脊柱変形の後遺障害慰謝料は最低でも420万円、賠償金は1000万円を超えることもあります。
脊柱変形の後遺障害が認定された場合、等級は最低でも11級になります。
後遺障害11級の後遺障害慰謝料は弁護士基準で420万円になります。
逸失利益の労働能力喪失率は11級で20%、もし労働能力喪失率が下げられても12級の14%は維持されることが多いです。
そのため、脊柱変形の後遺障害が認定された場合、被害者に大きな過失がない限り賠償金は1000万円以上になることが多いです。
保険会社は脊柱変形の後遺障害の場合、必ず労働能力喪失率を下げてきますし、後遺障害慰謝料も弁護基準では提示しませんの420万円を下回ります。
保険会社から100万円を超えるような賠償金の提示があっても、圧迫骨折をしている場合や圧迫骨折で脊柱変形の後遺障害が認定された場合には、示談する前に弁護士に相談しましょう。
解決実績
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得(一人暮らしの無職の高齢女性で逸失利益を獲得!)
70代女性 圧迫骨折(脊柱変形)11級 約1100万円獲得 500万円増額
関連記事
保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがある
保険会社から賠償金の提示がある前に依頼を受けると,保険会社が過失割合をどのように考えているかは分からないことが多いです。
保険会社が支払いを拒否しているなどの事情があれば,保険会社が被害者の過失割合を相当大きく考えているということが分かるのですが,ほとんどの場合,被害者に多少の過失があっても,保険会社は治療費等の支払いをして,示談の時に過失相殺をするのが一般的ですので,示談交渉の前に具体的な過失割合の話をすることはあまりありません。
時々,休業損害の支払いなどで,被害者の過失分を控除して支払ってくるような保険会社もありますが,どちらかといえば,このようなケースは少ないように思います。
一方,被害者の代理人としては,被害者がどの程度過失があるのかは重要なことになりますので,事前に刑事記録を入手して,被害者にどの程度の過失が見込まれるかを確認するようにしています。
もちろん,事前に刑事記録を確認するのは,保険会社との交渉のために事前にどの程度の過失割合になるのか知っておくためですが,事前にどの程度の過失割合になるかを確認することで,被害者の方にどの程度の賠償金になるのかという見込みを説明することができるというメリットもあります。
こちらは事前に刑事記録を確認して被害者と加害者の過失割合の想定をしていますが,もちろん,賠償金を請求するときにこちらから過失割合を示して過失相殺をして請求するということはありません。
なぜならば,保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがあるからです。
過失割合の判断には刑事記録が重要
過失割合の判断には刑事記録が重要です。
刑事記録とは,主に交通事故の状況を記録した実況見分調書のことを指します。
事故の状況を記録した実況見分調書以外にも加害車両の状態を記録した実況見分調書や照射実験の結果を記録した実況見分調書などがありますが,事故の状況を記録した実況見分調書が最も重要な刑事記録になります。
刑事記録の中には,このような客観的な事実を記録したもの以外に,事故の当事者や目撃者の供述を調書にした供述調書という記録もあります。
ところが,この供述調書は刑事事件で正式裁判にならず不起訴処分になると開示されないことが多いです。
事故の状況を記録した実況見分調書と当事者の供述調書を照らし合わせて,正確な事故の状況が分かるということもあるので,供述調書も開示して欲しいのですが,刑事記録を保管・管理している検察庁が不起訴の場合はプライバシー侵害のおそれがあるとして供述調書を開示しない方針をとっているのでやむを得ません。
ただし,裁判になれば,供述調書を開示する方法もあるのですが,これはまた別の機会に書きたいと思います。
とにかく,過失割合の判断には刑事記録が重要ということは認識しておきましょう。
保険会社は刑事記録を取得していないこともある
過失割合の判断には刑事記録が重要なので,当然,保険会社も刑事記録を取得していると思うかもしれませんが,実際のところ,保険会社は全ての交通事故で刑事記録を取得しているわけではないようです。
刑事記録は,先ほど検察庁が供述調書を開示しない理由でも書きましたが,プライバシーにかかわる記録です。
そのため,保険会社とはいえ,交通事故の当事者でない者が刑事記録を簡単に入手することはできません。
そうすると,保険会社が刑事記録を入手するためには弁護士に依頼をする必要があります。もちろん,弁護士も無料では依頼を受けませんし,刑事記録の開示を求めるにもそれなりの実費が必要になります。
つまり,1件の交通事故の刑事記録を取得するだけでも保険会社にとってはそれなりのコストが発生するということになります。
保険会社が扱っている交通事故は膨大な件数ですので,そのすべてで刑事記録を取得していたらそのコストだけでかなりの金額になってしまいます。
そのため,保険会社は事故の状況を確認しなければならない事故の時だけ刑事記録を取得しており,すべての事故で刑事記録を取得しているわけではありません。
特に,軽度な事案ではほとんどのケースで刑事記録を取得していないように思います。
刑事記録を取得していないと,当然,こちらは知っているが保険会社は知らないという事実が出てきます。
以前あったのは,自転車が交差点を横断中にトラックに衝突されたという事故で、衝突時の信号は自転車が青でトラックが赤だったのですが,自転車が横断を開始した時の信号の色は赤で横断途中で青に変わり,その後にトラックと衝突したという事故がありました。
トラックの運転手はナビを見て運転をしていたため,当然,自転車が青信号になる前に横断を開始したという事実は知りません。
刑事記録は,自転車の運転手の供述に基づいて記録されていたのです。
保険会社は,トラックの運転手の話しか聞いていませんでしたので,当然,100%トラックの運転手の責任で,自転車の運転手には過失はないと考え,過失相殺をせずに賠償金の提示をしてきたということがありました。
自転車が横断を開始した時の信号が赤で,トラックが交差点に進入した時の信号が青で,その後,信号が変わり衝突したという場合には,多少過失割合が違ってきてもおかしくないという事案です。
しかし,保険会社は,刑事記録を取得していなかったため,被害者の過失を0で解決することができました。
一方で,被害者の過失を下げるような事実が刑事記録を見て初めて分かるというケースもあります。
その場合は,こちらから刑事記録を保険会社に送って,被害者の有利に過失割合を変更することが可能です。
刑事記録は,事故の当事者であれば検察庁で取得することが可能ですが,結構手間がかかりますので弁護士に依頼して取得した方がいいと思います。
解決実績
30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
関連記事
死亡事故の逸失利益
逸失利益とは,将来生きていれば得られたはずの収入を填補するという損害項目です。
死亡事故の逸失利益は,賠償金の大部分を占めますのでどのように計算をするかをしっかりと理解しておく必要があります。死亡事故の逸失利益は以下の計算式で計算をします。
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
死亡事故一般については,「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。
学生の逸失利益
基礎収入
基本的に学生は仕事をしていないので収入がありません。しかし,将来仕事をすることは間違いありませんので,学生の場合も逸失利益は認められます。
死亡事故の逸失利益の計算(主婦の場合)でも書きましたが,交通事故に遭った当時に収入がない被害者の方の場合には賃金センサスの平均賃金を使います。
学生といっても,小学生,中学生,高校生,専門学校生,大学生とあります。学生の場合は,賃金センサスのうち学歴計全年齢の平均賃金,もしくは大卒の平均賃金のいずれを用いるかが問題になります。もちろん,平均賃金は大卒の方が高額になります。
学生のうち,専門学校生は学歴計全年齢の平均賃金,大学生は大卒の平均賃金を基礎収入にするということであまり問題はありません。
小学生,中学生,高校生の場合には,一般的には学歴計全年齢の平均賃金を基礎収入にすることが多いと思いますが,被害者が大学に進学することが明らかだった場合には,大卒の平均賃金を基礎収入にすることとも可能です。ただし,後で説明する労働能力喪失期間の就労開始年齢が,学歴計全年齢の平均賃金を基礎収入とする場合は18歳となりますが,大卒の平均賃金を基礎収入とする場合は22歳となるので,その点は注意が必要です。
生活費控除率
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |
| 年金部分 | 30%~50% |
被害者が学生の場合,基本的には独身の方が多いと思いますので,上の表でいうと,男性であれば50%,女性であれば30%になります。ただし,上の表の女性の生活費控除率は,基礎収入を賃金センサスの女性学歴計全年齢の平均賃金とすることを前提としていると考えられます。民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)には,以下のような説明があります。
「なお,女子年少者の逸失利益につき,全労働者(男女計)の全年齢平均賃金を基礎収入とする場合には,その生活費控除率を40%~45%とするものが多い」(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)
そうすると,女子の年少者(小学生くらい)の場合,基礎収入を全労働者(男女計)学歴計全年齢の平均賃金を使うのであれば,生活費控除率は40%から45%になる可能性が高そうです。
労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)
学生の場合,まだ就労を開始していませんので,労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数が少し複雑になります。
学生の場合のライプニッツ係数は,①まず,事故当時の年齢から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数を出します。②次に,事故当時の年齢から実際に働き始めるまでの年齢の期間に対応するライプニッツ係数を出します。③①から②を差し引いた出された数値を労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とします。
このように書くと全く分からないので,具体例で説明したいと思います。
事故当時10歳の子供が18歳から働き始めることを前提とした場合
①67歳-10歳=57年 57年に対応するライプニッツ係数 27.1509
②18歳-10歳=8年 8年に対応するライプニッツ係数 7.0197
③27.1509-7.0197=20.1312
この場合,20.1312を労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とすることになります。
なお,ライプニッツ係数は,民法改正前は,民法の法定利率と同じく年5%で中間利息を控除する数値になっていましたが,現時点では年3%で中間利息を控除する数値になっていますので,それに合わせてライプニッツ係数の修正を行いました。ライプニッツ係数の数値は、今後も変更になるので注意が必要です。
事故当時12歳の男子小学生で18歳から働き始めることを前提とした場合の逸失利益は約6000万円
基礎収入は,18歳から働き始めることが前提ですので,令和元年の賃金センサスの男性学歴計全年齢の平均賃金560万9700円となります(賃金センサスは年度によって金額が変わりますのでご注意ください)。
生活費控除率は男子ですので50%になります。
さあ,一番複雑な労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数です。以下のとおりとなります。
①67歳-12歳=55年 55年に対応するライプニッツ係数 26.7744
②18歳-12歳=6年 6年に対応するライプニッツ係数 5.4172
③26.7744-5.4172=21.3572
そうすると,この場合の逸失利益の計算は以下の計算式のとおりとなります。
560万9700円×(1-50%)×21.3572=5990万3742円
事故当時20歳の女子大学生で大学卒業後から働き始めることを前提とした場合の逸失利益は7000万円以上
基礎収入は,女子大学生ですので,令和元年の賃金センサスの女性大卒全年齢の平均賃金472万400円となります。
生活費控除率は,先ほど説明したように独身女性の生活費控除率はは30%になります。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は以下のとおりになります。
①67歳-20歳=47年 47年に対応するライプニッツ係数 25.0247
②22歳-20歳=2年 2年に対応するライプニッツ係数 1.9135
③25.0247-1.9135=23.1112
大学生の場合,卒業時の年齢(通常22歳)から就労開始となりますのでこのような計算になります。
そうすると,この場合の逸失利益の計算は以下の計算式のとおりとなります。
472万400円×(1-30%)×23.1112=7366万5875円
実際にどれくらいに賠償金になるのかは弁護士に相談しよう!
実際にどれくらいの賠償金になるのかは、それぞれの事情によって違ってきますので、弁護士に相談しましょう!
交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのか無料でお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。
K-1の小宮山工介選手,交通事故現場で窓ガラス割り救出
乗用車とトラックが正面衝突した交通事故の現場で,K-1の小宮山工介選手がトラックの窓ガラスを肘打ちで粉砕してトラック運転手を救出したというニュースが話題になっています。
小宮山選手が運転手を救出をした後,トラックは炎上したそうですから,大変勇気のある素晴らしい行動ですね。
今回この話を取り上げたのは,小宮山選手の行動が素晴らしかったということを取り上げたかっただけでなく,法的に考えると少し問題となることもあり得るなと思い取り上げました。
小宮山選手の治療費やファイトマネーの補償は誰が払うの?
小宮山選手は,トラックの窓ガラスを肘打ちで粉砕して右肘に10針も縫う怪我を負ったそうです。これによって,9月18日に出場する予定であった試合への出場が未定になってしまったそうです。
右肘に10針も縫うけがをしたということは,今後もしばらくの間は通院が必要となります。
その際に,発生する治療費は法的には誰が負担することになるのでしょうか?また,試合を欠場してしまった場合,試合に出場すればもらえるはずであったファイトマネーの補償はされるのでしょうか?
トラック運転手に対して請求できるか?
この問題を考える際には,まず小宮山選手とトラック運転手との間でどのような法律関係が成立しているかを考える必要があります。
小宮山選手が行った救出行為は,法的に考えると民法697条が定める「事務管理」に該当すると考えられます。
事務管理とは,契約や法律の規定による義務を負っていないにもかかわらず,他人の事務を管理する意思をもってその事務を管理することを言います。
民法の本でよく上げられる事務管理の例としては,道で倒れている人を病院に連れていくことや家事になった隣家の消火活動などがあります。まさに,今回の小宮山選手の救出行為は事務管理に該当します。
事務管理の当事者は,他人の事務を管理する事務管理者と事務管理をされる本人がいます。
今回の件で言えば,事務管理者が小宮山選手で事務管理をされる本人がトラック運転手となります。
事務管理者と本人の間には,事務管理者が本人に対して事務管理の報告をする義務があったり,事務管理者が本人の利益になる費用を支払ったときは,事務管理者は本人に対して支払った費用を返還するよう請求したりすることができます。
では,今回の件で小宮山選手が怪我をしたことによって負担することになった治療費やファイトマネーの補償をトラック運転手に対して請求することはできるのでしょうか?
これは,事務管理者(小宮山選手)が,事務管理によって生じた損害を本人(トラック運転手)に対して,請求することができるかという問題になります。
事務管理は,委任という契約の条文を準用しているのですが,委任契約で認められている受任者の委任者に対する損害賠償の規定を事務管理の条文は準用していません。
そうすると,事務管理者は,事務管理をして自分が損害を負ったとしても,事務管理をされた本人に対して損害賠償の請求はできないということになります。
今回の件で言えば,小宮山選手は,治療費やファイトマネーの補償をトラック運転手に対して請求することはできないということになります。
乗用車の運転手に対して請求できるか?
次に,小宮山選手の治療費やファイトマネーの補償をもう一方の事故の当事者である乗用車の運転手に請求できるか考えてみたいと思います。
交通事故の状況が正面衝突ということしかわからないので,乗用車の運転手にどの程度の過失があったのか分かりませんが,正面衝突ということだと,どちらかのセンターラインオーバーによって今回の交通事故が発生した可能性が高いと考えられます。
もし,トラック運転手のセンターラインオーバーが原因であれば,トラック運転手と乗用車の運転手の過失割合は,100対0になります。
そうすると,乗用車の運転手に今回の交通事故の責任はないということになりますので,当然,小宮山選手の治療費やファイトマネーの補償を支払う責任を負うこともありません。
反対に,今回の交通事故の原因が乗用車の運転手のセンターラインオーバーであれば,過失割合は乗用車の運転手の100%ということになります。
では,事故の原因が100%乗用車の運転手にある場合,小宮山選手と乗用車の運転手はどのような法律関係になるのでしょうか?
小宮山選手は交通事故の当事者ではないので,乗用車の運転手が小宮山選手に対して自賠法による責任を負うということはありません。
また,民法の不法行為も,乗用車の運転手が小宮山選手に対して選手に対して加害行為を行ったわけではないので,成立しないと思います。
そうすると,残りは不当利得が成立するかです。
不当利得とは,法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,それにより他人に損失を及ぼした場合に,利益を受けた者がその他人に利益を返還しなければならないという法律関係をいいます。
不当利得は,なかなか具体例を挙げて説明しづらいのですが,売主の詐欺によって車を買わされた買主が売買契約を取り消すと,買主と売主の間に契約関係がなくなります。
ところが,売主は売買代金を得たままになっていますので,法律上の原因なく売主が利得をしている状態にあり,買主は代金を返してもらえず損失が生じています。
このような場合に,買主が売主に対して売買代金の返還を求めることを不当利得返還請求といいます。
今回の交通事故の件でいうと,小宮山選手に治療費やファイトマネーといった損失が生じていることは明らかですが,乗用車の運転手は何か利得をしているでしょうか。
仮に,小宮山選手が救助しなければトラックの運転手が大怪我をし,本来,その治療費を乗用車の運転手が支払うはずであったとして,乗用車の運転手が治療費の支払いを免れたといえるのであれば,乗用車の運転手に利得が生じたと考えることはできるかもしれません。
もし,これを利得と考えることができれば,あとは,小宮山選手の治療費等の損失と乗用車の運転手の利得との間に因果関係が認められれば,小宮山選手は,治療費やファイトマネーの補償を乗用車の運転手に請求することが可能ということになります(因果関係は認められるでしょうか?なかなか難しい判断のように思えます)。
小宮山選手が粉砕したトラックの窓ガラスの修理代は誰が払うの?
では,最後に,小宮山選手が粉砕したトラックの窓ガラスの修理代をだれが払うことになるのか考えてみたいと思います。
小宮山選手が負担しなければならない?
形式的には,小宮山選手の行為によってトラックの窓ガラスが損壊するという損害がトラック運転手に生じていることになります。
そうすると,小宮山選手がトラックの窓ガラスの修理代を負担しないといけないようにも思えます。
しかし,人命救助をしたのに窓ガラスの修理代を小宮山選手が負担しなければならないなんて,あまりにも世知辛い世の中になってしまいます。
いくら法律でも,そこまで世知辛くはありません。
先ほど,小宮山選手とトラック運転手の関係は事務管理という法律関係が成立すると説明をしました。
事務管理の中でも,本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるための事務管理を緊急事務管理といいます。
緊急事務管理の場合,事務管理者に悪意又は重大な過失がなく本人に発生した損害については,事務管理者が責任を負わないことが法律に明記されています。
今回の件が緊急事務管理に該当することは間違いありませんので,小宮山選手がトラックの窓ガラスの修理代を負担することはありません。
乗用車の運転手が負担する?
では,乗用車の運転手がトラックの窓ガラスの修理代を負担することはあるのでしょうか?
乗用車の運転手に事故の過失がなければ責任を負わないことは先ほど説明した通りです。
乗用車の運転手に過失があった場合は,乗用車の運転手が負担する可能性はあるのですが,それには交通事故と窓ガラスの損壊との間に相当因果関係が認められなければなりません。
救助の際に,窓ガラスを壊して運転手を救助するということは通常あり得ることなので,おそらく,交通事故と窓ガラスの損壊との間に相当因果関係は認められる可能性は高いのではないでしょうか。
相当因果関係が認められるのであれば,乗用車の運転手は窓ガラスの修理代を支払うことになります。
※今回の記事は,あくまでも法的に考えるとどのような問題が生じるかについて書いただけで,当事者がどのような行動をとったのかを書いたものではないのでご注意下さい。特に,危険を省みずに人命救助をした素晴らしい人間性を持つ小宮山選手が治療費やファイトマネーの補償を事故の当事者に請求するなんてことは考えらませんので,くれぐれも誤解なきようお願い致します。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。