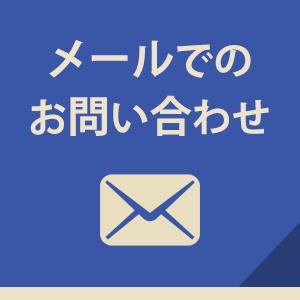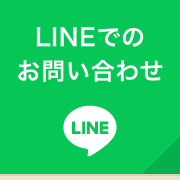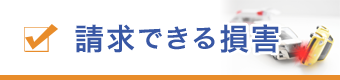横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》 - Part 5
自賠責の後遺障害と労災の障害の認定基準は同じ
自賠責の後遺障害は1級から14級までありますが,これは労災の障害補償の障害等級表に準じた内容になっていますので,自賠責の後遺障害の認定基準と労災の障害認定基準は同じということになります。
例えば,交通事故でよくあるむち打ち症による神経症状14級の場合,正式には,自賠法施行令別表第2に規定されている第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という基準に該当した時に認定されます。
労災の障害認定基準を規定した労働者災害補償保険法施行規則別表第1の第14級9号も「局部に神経症状を残すもの」という基準になっています。
自賠責と労災で認定された後遺障害が一致しないことがある
このように,自賠責は労災の障害認定基準を準用しているので,通勤災害のように自賠責も労災も使えるような場合,認定される後遺障害は必ず同じ等級になるように思えます。
ところが,自賠責で認定された後遺障害と労災で認定された障害等級が一致しない,もしくは一方で後遺障害認定されたのにもう一方では非該当だったということが時々あります。
認定された後遺障害の等級が一致しなかったり,一方で後遺障害認定されたのにもう一方で非該当だったということが生じる大きな原因として以下の2つが考えられます。
①後遺障害診断書等の資料に症状固定時に残っている症状がしっかりと書かれていない
②後遺障害の有無や程度を判断するために必要な検査結果が労災と自賠責で異なっている
症状がしっかりと書かれていない
症状はあくまでも自覚症状であったり,家族など被害者の周囲の人の申告に基づいて後遺障害診断書等の資料に記載される主観的なものですので,症状の捉え方が医師によって違うということが生じてきてしまいます。
特に,高次脳機能障害のように認知機能障害や人格障害の程度よって後遺障害等級が変わってくる障害になると,後遺障害診断書以外に障害の程度を確認するための資料があるのですが,同じ被害者のことでも障害の程度が違って記載されているということが時々あります。
このような場合に,自賠責の認定と労災の認定が異なってくるということがあります。
検査結果が自賠責と労災で異なっている
後遺障害診断書等の資料には,通常は,残っている症状が後遺障害に該当するかを確認するのに必要な検査結果が記載されています。
例えば,機能障害であれば,関節可動域の検査結果が記載されています。
この検査結果が自賠責と労災で異なっているということがあります。
後遺障害認定の際に提出する資料は,自賠責と労災で異なっているのですが,その資料を自賠責と労災でそれぞれ違う医師が作成するということがあります。
また,資料の作成時期も異なっているということがあります。
このように,資料を作成する医師や作成時期が違うと,検査結果も違ってくるということがあります。
先ほどの機能障害は,測定する時期によって関節の可動域の制限の程度が異なるということがよくあります。
そうすると,例えば,労災では2分の1以下の制限が認められ10級が認定されたのに,自賠責では4分の3以下の制限しか認められず12級しか認定されないという事態が生じます。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合にはどうすればいいか
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合にはどうすればいいのでしょうか?
認定された後遺障害の結果に不服があるときのために,自賠責では異議申立て,労災では審査請求という制度が用意されています。
後遺障害の認定に納得がいかない場合には,この制度を利用することになります。
いずれの制度も,なぜ後遺障害が認定されなかったのか,なぜ上位の後遺障害等級が認定されなかったのかを分析した上で,認定されなかった理由を覆すだけの資料を準備する必要があります。
では,異議申立てないし審査請求の資料に,一方の有利な認定結果を用いることはできるでしょうか?
先ほどの機能障害の例で説明すると,労災で10級が認定されて,自賠責で12級しか認定されなかったときに,労災の10級の認定結果自体を自賠責の異議申立ての資料として用いるのことができるのかという問題です。
自賠責又は労災は,後遺障害の認定をする際にそれぞれ必要な調査をしていますが,これは異議申立てや審査請求でも同じです。
そうすると,異議申立てや審査請求でも後遺障害の認定基準に該当するかを症状や検査結果を記載した新たに提出した資料に基づいて判断をします。
一方の有利な認定結果は症状や検査結果を記載した資料ではありませんので,提出しても参考程度にしか用いられません。
つまり,一方の有利な認定結果は,異議申立てないし審査請求で最初の認定を覆すだけの決定的な証拠にはならないということです。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合には、後遺障害に強い弁護士に相談しよう!
最初に説明したように、自賠責と労災の後遺障害の認定基準は同じです。
そうすると、本来であれば、自賠責と労災の後遺障害の認定は同じ結果になるはずです。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違うということは、必ず原因があるはずです。
後遺障害の認定結果が違う理由は、後遺障害診断書等に認定基準を満たす内容が記載されていないということが多いと思います。
後遺障害診断書等に認定基準を満たす内容が記載されてない場合には、認定基準を満たすような内容を記載してもらうようにしなければなりません。
そのためには、後遺障害の認定基準をしっかりと理解している必要があります。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合には、後遺障害の認定基準をしっかりと理解している後遺障害に強い弁護士に相談しましょう!
クロノス総合法律事務所は、後遺障害の異議申立て、審査請求をして後遺障害の認定結果を変更した実績が多くあります。
後遺障害の認定結果を変えたいという被害者の方は、クロノス総合法律事務所にご相談下さい。
クロノス総合法律事務所は、電話・メール・LINE・オンライン面談のいずれの方法でも無料相談をしております。
解決実績
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)
関連記事
示談書(承諾書,免責証書)は定型文になっている
交通事故の賠償を示談で解決する場合,保険会社と示談書(承諾書,免責証書と言ったりもします)を交わすことになります。
示談書は大抵保険会社が作成した定型書式を利用しますので,示談の内容は定型文になっています。
どこの保険会社も
①示談書に明記された賠償金を受領したらその他の損害賠償請求権を放棄する
②今後,裁判上,裁判外において一切の異議を申し立てない
ということが記載されています。
このような内容にすることで,後から被害者が本当だったらもっと賠償金がもらえたことに気が付いて,あらためて保険会社に請求をしたり裁判を起こしたりしても,被害者の請求が認められないようになっています。
そのため,任意保険会社の基準で計算した慰謝料や賠償金で示談してしまった場合,後から弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金の方がはるかに高額だということが分かったとしても,再度,弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金で保険会社に請求することはできません。
このような事態を避けるためには,保険会社から賠償金の提示をもらったときに,交通事故を専門とする弁護士に相談することが必要です。
「敵(損保会社)は味方のふりをする」でも書きましたが,どんなにいい担当者でも,弁護士が介入していない段階で弁護士基準で計算した賠償金を提示してくる担当者は絶対にいません。
示談書にサインする前に気を付けた方がいいこと
弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がいくらなのか確認すること
しつこいかもしれませんが,示談書にサインをする前に弁護士に相談をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がどれくらいになるのかを確認するように気を付けましょう。
これは絶対に気を付けなければならないことと言っても過言ではありません。
例えば、交通事故で多いむち打ち症で6ヶ月通院した場合には、被害者に過失がなければ、通院に対する慰謝料は弁護士基準で計算する約90万円になります。
しかし、任意保険が計算する通院に対する慰謝料は高くても50万円から60万円程度です。
酷いときには、自賠責基準で計算して20万円から30万円程度しか提示してこないということもあります。
必ず弁護士基準で計算したい慰謝料どれくらいの金額になるのかは確認しましょう!以下のリンク先で交通事故の慰謝料の計算・相場について解説していますので参考にして下さい。
示談書に症状が悪化して後遺障害等級が上がったことを想定した文言を追加すること
また,なんとか自分で交渉をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金になったとしても示談書にサインをする前に気を付けておいた方がいいことがあります。
それは,すべての事案で気を付けた方がいいというわけではないのですが,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合です。
例えば,股関節付近の骨折後に股関節に健側の2分の1以下の可動域制限が残って後遺障害等級10級が認定され,さらに将来的に股関節に人工関節を入れる可能性があるような場合です。
将来,実際に股関節に人工関節を入れて可動域が健側の2分の1以下になった場合には,後遺障害等級が10級から8級に上がります。
このような場合には,被害者としては,人工関節にした際に必要となった手術代(治療費),通院交通費,入院雑費,入通院慰謝料(傷害慰謝料),等級に応じた後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求したいと思うはずです。
このような場合,示談書に何も追加で書かなかったとしても,裁判にすれば後遺障害等級8級になったことによって発生した賠償金を請求することはできます。
しかし,示談では,最初の示談書を盾にとって,保険会社が一切の交渉に応じないという可能性もあります。
そこで,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合には,以下のような文言を示談書に追加して欲しいと保険会社に言った方がいいと思います。
「ただし,症状が悪化して現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,別途協議する。」
このような文言を示談書に入れておけば,現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,保険会社は示談交渉に応じざるを得ない状況になります。
保険会社も,後遺障害等級が上がった時には裁判にされるよりは示談で終わらした方が得策ですので,このような内容の文言を追記することを拒否することはありません。
実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいい?
では,実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいいのでしょうか?
この場合,通常の後遺障害の被害者請求と同じことをすることになります。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい自賠責に対して後遺障害の被害者請求をします。
症状の悪化が交通事故から時間が経っていても,時効の起算日は新たに作成した症状固定日になりますので,時効の心配はありません。
注意が必要なのは自賠責用の診断書(後遺障害診断書ではなく毎月病院が治療費を保険会社に対して請求する際に作成している診断書です)の作成を病院に依頼することです。
一度示談している以上,保険会社が病院に直接治療費を支払うことがないので,手術等の治療費については,一度,被害者の方が健康保険を利用して自己負担することになります。
そうすると,被害者の方から病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しないと,病院は自賠責用の診断書を作成してくれません。
自賠責に後遺障害の被害者請求をするときには自賠責用の診断書が必要になりますので,被害者の方が病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しておく必要があります。
それと,領収書もしっかりと保管しておきましょう。多くの方が示談している以上保険会社にこれ以上賠償金の請求することはできないと考えてしまい,領収書を捨ててしまっていることが多くあります。
示談書にサインをする前に弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談しよう!
示談書にサインするということは、損保会社の提示する慰謝料や賠償金にそれなりに納得したからだと思います。
しかし、その金額は、もしかしたら弁護士基準で計算をすれば、慰謝料も賠償金ももっと高い金額になるかもしれません。
実際に慰謝料や賠償金がいくらになるのかは、後遺障害の有無、被害者の過失の有無、被害者の年収などによって変わってきますので、自分で判断しようと思ってなかなか簡単ではありません。
やはり、示談書にサインする前に交通事故を専門としている弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談した方が納得いく解決ができると思います。
交通事故を専門としている弁護士や交通事故に強い弁護士の探し方は以下の記事を参考にして下さい。
関連記事
交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)
交通事故に強い弁護士が弁護士に依頼するための弁護士費用特約の使い方を解説!
機能障害とは?
機能障害とは,上肢,下肢,指の関節の動きが制限された場合に認められる後遺障害です。交通事故では比較的によく見られる後遺障害になります。
上肢及び下肢であれば3大関節の動きが制限された場合に後遺障害が認定されます。上肢とは腕のことで下肢とは脚のことをです。3大関節とは,腕であれば肩関節,肘関節,手関節(手首の関節)をいい,脚であれば股関節,膝関節,足関節(足首の関節)をいいます。
上肢及び下肢の機能障害は,「関節の用を廃した」場合,「関節の機能に著しい障害を残す」場合,「関節の機能に障害を残す」場合で認定される等級が異なってきます。
上肢の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害1級 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害5級 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害6級 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害1級 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害5級 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害6級 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害12級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
指の場合は,手指と足指で後遺障害が認定される条件が異なります。
手指の場合は,「手指の用を廃した」場合と「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」場合に後遺障害が認定されます。
足指の場合は,「足指の用を廃した」場合だけ後遺障害が認定されます。
手指の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害7級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害9級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害12級 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
| 後遺障害13級 | 1手の小指の用を廃したもの |
| 後遺障害14級 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
足指の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害9級 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害11級 | 1足の第1の足指を含み2の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害12級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害13級 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害14級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
同一上肢の機能障害と手指の機能障害,または,同一下肢の機能障害と手指の機能障害は,本来的にはそれぞれ同一系列ではないのですが,みなし系列として同一系列の扱いを受けてしまいます。
具体的に説明すると,例えば,右肘関節で10級の機能障害が認定され,右指関節で10級の機能障害が認定された場合,併合されて1等級繰上り9級になるように思えますが,同一系列の扱いになりますので,後遺障害等級は10級となってしまいます。
機能障害はよく争われる後遺障害
機能障害は関節付近の骨を骨折したような場合に残りやすい障害なので,よく発生する後遺障害です。ただ,これまでの経験からすると,機能障害は,裁判でよく争われる後遺障害という印象が強いです。
機能障害は,最初に説明したように関節の動きが制限される後遺障害ですので,症状固定時に関節がどの程度動くかを測定して,その数値を後遺障害診断書に記載し,その数値からどの程度関節の動きが制限されているかを判断して,後遺障害の認定をします。
当然ですが,症状固定とはこれ以上治療しても改善しない状態ですので,事故直後が最も関節が動かず,徐々に改善して症状固定時が最も改善した状態ということになります。
ところが,ケースによっては症状固定時の関節の動きの数値よりも,それ以前に測定した関節の数値の方が改善した数値になっているということがあります。そうすると,本当は,関節の動きはもっといいはずであるのに,後遺障害診断書には本当の動きよりも悪い数値が記載されたとして,保険会社側の弁護士から,機能障害が本当に残っているのか,または,もっと軽い程度の機能障害しか残っていないのではないか,と争われてしまうのです。
後遺障害診断書に記載された関節の動きの数値よりも,それ以前のカルテに記載された関節の動きの数値の方が改善した数値になっていたということは,実際によくあることですので,関節機能障害は,障害の存在や程度がよく争われる後遺障害といえます。
機能障害には注意が必要
このように,関節機能障害はよく争われる後遺障害ですので注意が必要です。
関節の動きの測定方法が医師によってばらつきがあるということを知っておく必要があります。
本来であれば,日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が制定する測定法によって関節の動きを測定する必要があります。
ところが,医師によってはその測定法に従わずに測定をしたり,測定器を使わずに目測で測定することが多々あります。
そのために,先ほど説明したような症状固定時の関節の動きの数値よりも,その前に測定した関節の動きの数値の方がよい数値であったというような事態が生じてしまうのだと思われます。
そのため,もし,機能障害の後遺障害で裁判をする場合には,裁判をする前にカルテを取得して後遺障害診断書に記載された関節の動きの数値よりも良い数値がカルテに記載されていないか確認した方が良いでしょう。
疼痛以外の感覚障害とは?
今回はかなりマイナーな後遺障害の話になります。私が以前担当した交通事故で「疼痛以外の感覚障害」という後遺障害が認定されたという事案がありました。
疼痛以外の感覚障害とは,疼痛はないけど蟻走感や感覚脱失等の感覚異常が残ってしまった障害をいいます。ちなみに,私が担当した被害者の方は,多少違和感があるくらいで,常時気になるようなことはないと言っていました。
疼痛以外の感覚障害は,単に感覚異常が残っただけでは認められずその範囲が広い場合に後遺障害として認定されます。ただし,労災や自賠責の基準では,どの程度の範囲に感覚異常が残れば,「範囲が広い」に該当するのかは明確にされていません。
疼痛以外の感覚障害の後遺障害等級は14級しかなく,そのほかの神経症状の後遺障害のように他覚的所見があったとしても12級は認定されません。というか,おそらく,疼痛以外の感覚障害の後遺障害は,他覚的所見がある場合にしか認められないと思います。
私が担当した事件でも,こめかみ辺りから3つに分かれている三叉神経のうち第三枝の損傷が画像によって確認することができるという事案でした。
疼痛以外の感覚障害による労働能力の喪失はあるか?
疼痛以外の感覚障害は,先ほど説明したように後遺障害等級は14級しかなく,認定の基準も労働能力とは無関係な感覚異常の範囲が広いかどうかというものだったので,この事案を担当することになった時には,感覚障害による労働能力の喪失が認められるのかという疑問を持ちました。
このような疑問がありましたが,むちうちによる14級の後遺障害でも労働能力の喪失が認められるのだから,疼痛以外の感覚障害にも労働能力の喪失は認められるだろうとそれほど大きな問題とは考えていませんでした。それどころか,三叉神経損傷が画像によって確認でき他覚的所見があるのだから,14級でも労働能力喪失期間は10年にはなると考えていたくらいです。
また,示談交渉の段階では労働能力喪失期間に争いはありましたが,保険会社は逸失利益が認められないという争い方はしなかったので,それほど労働能力の喪失の有無については気にしていませんでした。
裁判になったら労働能力喪失の有無を争ってきた!
この事案は,結局,示談では解決できず,交通事故紛争処理センターへの申立てをしました。過失がある事案だったのですが,当方は,最低でも自賠責保険金75万円を除いて350万円以上の賠償金を主張し,相手方は,200万円程度の賠償金までしか応じられないという回答でした。そのため,交通事故紛争処理センターでも示談することができず,裁判に移行することになりました。
交通事故紛争処理センターの時点で,加害者側には弁護士がついていたのですが,交通事故紛争処理センターでは労働能力の喪失の有無を争わなかったにもかかわらず,裁判になったら労働能力の喪失の有無を争ってきました。
しかも,相手方弁護士が労働能力の喪失が認められないと主張する理由の1つに,感覚障害が残った部位が唇からアゴにかけてであったため,歯牙障害と同じようなものだという理由があったのです。
歯牙障害とは,事故によって歯が喪失や欠損して歯科補綴をした場合に認められる後遺障害なのですが,一般的に労働能力の喪失は認められません。
労働能力の喪失が認められた!
相手方弁護士は,三叉神経損傷による感覚異常はこの歯牙障害と同じだという主張を裁判になって初めてしてきたのです。この主張は盲点だったので多少ドキッとしました。確かに,残っている症状は多少違和感があるくらいで,普通に仕事をしていたので,歯牙障害と同じようなものと裁判所に思われてしまうのではないかと思ったからです。
しかし,歯牙障害と同じ口の障害には,「言語機能の障害」というものがあります。「言語機能の障害」とは,発音不能の語音がある場合に認定される後遺障害なのですが,これは,コミュニケーションに支障が生じるために問題なく労働能力の喪失が認められる後遺障害です。
そこで,歯牙障害ではなく言語機能の障害に近いと裁判所に思わせれば,裁判所は労働能力の喪失を認めるのではないかと考え,そのような主張をしました。つまり,唇からアゴにかけての感覚障害によって事故前に比べて会話がしづらくなっておりコミュニケーションに支障が生じているという主張をしたのです。
この作戦がうまくいったのかは分かりませんが,裁判所が出した和解案では,感覚異常の後遺障害による労働能力の喪失が認められました。しかも,労働能力喪失期間は5年ではなく10年となりました(ちなみにトータルの賠償金は自賠責を除いて450万円となりました)。
どの部位に疼痛以外の感覚障害が残っても労働能力の喪失が認められるか?
今回は,唇からアゴにかけての感覚障害だったので,コミュニケーションに支障があるという主張ができましたが,ほかの部位に感覚障害が残った場合にも労働能力の喪失は認められるでしょうか?
おそらく上腕部や前腕部,大腿部や下腿部,胸部や臀部など体の動きとあまり関係のない部位に感覚障害が残ったとしても,労働に支障が生じるケースは少ないと思うので,労働能力の喪失は認められないような気がします。
残りの賠償金は慰謝料だけではないですよ!
ヤフーの検索エンジンに「交通事故」と入力すると,最上位の第2検索ワードが「慰謝料」となっています。実際に,交通事故に関係するキーワードで「交通事故 慰謝料」の検索ボリュームはかなり大きいようです。
ここでふと思ったことが,「交通事故」の最上位の第2検索ワードが,なぜ「賠償金」じゃないのだろうかってことです。弁護士の感覚ですと,交通事故の最上位の第2検索ワードは「慰謝料」よりも「賠償金」の方がしっくりきます。
「慰謝料」は,交通事故の賠償実務では,入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料がありますが,あくまでも賠償金を構成する損害項目の1つに過ぎません。交通事故の被害に遭ったら,慰謝料がいくらになるのか,ということ以上に,賠償金が総額でいくらになるのかということの方が気になります。
ここで再びふと思ったのですが,もしかしたら交通事故の被害に遭った人の多くが,治療費や休業損害などは保険会社からすでに支払ってもらったので,残りの賠償金は慰謝料だ!と考えて,「交通事故 慰謝料」と検索しているのかもしれないということです。
確かに,交通事故の相談を受けていると「私の場合,慰謝料はいくらになりますか」と聞かれることが度々あります。この相談者の方が,慰謝料以外に損害項目があることを理解して質問しているとは思えなかったので,「慰謝料以外にも賠償金はもらえますよ」と答えると,大抵,「えっ」という反応をされます。
このような反応をされる方は,治療費や休業損害などはすでに保険会社から支払われているので,残りの賠償金は慰謝料しかないと考えている方ばかりでした。
念のために言っておきますが,治療費や休業損害などが支払われていても,残りの賠償金は慰謝料だけではありません。
慰謝料も重要ですが逸失利益も重要ですよ!
治療費や休業損害などが支払われていた場合,残りの賠償金は,慰謝料と逸失利益です。もちろん,慰謝料も重要ですが,逸失利益はもっと重要です。
慰謝料は入通院期間や後遺障害等級によって決まってきますので,同じ入通院期間や後遺障害等級であれば,慰謝料の金額は同じになります。
一方,逸失利益は,同じ後遺障害等級であっても,収入と年齢によって金額が大きく変わってきます。収入が高く,年齢が若ければ,逸失利益は慰謝料よりも高額になることが多くあります。
例えば,年収1000万円で40歳の男性と年収500万円で50歳の男性で,いずれも後遺障害等級が9級の場合に,逸失利益がどれくらいの金額になるか確認してみましょう。
ちなみに,後遺障害9級の後遺障害慰謝料は弁護士基準で690万円で,40歳の方も50歳の方も違いはありません。
まず,年収1000万円で40歳の方の逸失利益は以下のとおりの金額となります。
1000万円×35%×14.6430=5125万500円
次に,年収500万円で50歳の方の逸失利益は以下のとおりの金額になります。
500万円×35%×11.2741=1972万9675円
いずれのケースでも後遺障害9級の後遺障害慰謝料690万円を大きく上回っています。
また,年収1000万円の40歳男性の逸失利益は,年収500万円の50歳男性に比べると,3000万円以上も高額です。後遺障害等級が同じでも,収入が高く,年齢が若いほど逸失利益が高額になるということをお分かりいただけたと思います。
保険会社は慰謝料もそうだけど逸失利益をもっと低く提示してくる
保険会社は,慰謝料も逸失利益も弁護士基準を大きく下回る金額で提示してきますが,保険会社としては,逸失利益を低い金額で抑えられた方が会社の利益になります。
そうすると,逸失利益は低い金額のまま据え置きで,慰謝料を増額して被害者の方を納得させて示談させるということが多くあります。
被害者の方としては,慰謝料ばかりに目を向けず逸失利益が弁護士基準で計算された金額になっているかということも確認する必要があります。
逸失利益は、基本的には事故前年の年収を基準にして計算しますが、事故当時20代の被害者の場合には、賃金センサスを基準に計算することもあります。被害者の属性によって計算方法に違いがあるので弁護士に相談することをお勧めします。
関連記事
交通事故に強い弁護士が会社員の死亡事故の逸失利益のについて解説!
交通事故に強い弁護士が主婦が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算について解説!
公務員は減収がないから逸失利益がない?~交通事故に強い弁護士が公務員の逸失利益を解説!~
行政書士が被害者請求するのって弁護士法違反にならないの?
後遺障害の認定の手続きは被害者請求で行った方がいいという話をしました(「事前認定と被害者請求ってどっちがいいの?」をご覧ください。)。ただ,被害者請求は後遺障害の認定に必要な資料を自分で集めなければならないので少し面倒です。しかし,事前認定にすると,保険会社の担当者が被害者にとって不利な資料を提出してしまうかもしれません。そうすると,誰かに代わりに被害者請求の手続きを手伝ってもらいところです。
では,被害者請求は誰に手伝ってもらったらいいのでしょうか?
被害者請求は自賠法16条に基づく請求ですので,本来,被害者請求を代理することができるのは弁護士だけです。ところが,現在では,多くの行政書士が被害者請求の代理業務を行っています。弁護士法72条は,弁護士以外の法律事務の取り扱いを禁止していますが,行政書士が自賠法16条に基づく被害者請求を行うことは,弁護士法72条違反とならないのでしょうか?
大阪高裁平成26年6月12日は,行政書士が交通事故の被害者と締結した自賠責保険の申請手続き・書類作成等の準委任契約は,弁護士法72条に反するものであり,公序良俗に反するため無効であるという判断をしました。
通常は,被害者請求の手続きにおいては,被害者の方の症状を確認して,どのような後遺障害等級が認定されるかを予測し,その予測のもと,被害者の方にアドバイスをすることが必要となります。また,予測した後遺障害等級が認定されない場合には,自賠責保険に対して異議申立てをする必要があります。
そうすると,自賠法16条に基づく被害者請求は,将来法的紛争が発生することが十分に予測される手続ですので,弁護士法72条の法律事件に関する法律事務に該当します。
そうだとすれば,行政書士が自賠法16条に基づく被害者請求の代理をすることは,弁護士以外が法律事務を取り扱うことを禁止している弁護士法72条に違反すると考えるのが妥当です。おそらく,代理だけでなく,被害者請求に関するアドバイスをすることも弁護士法72条違反になるでしょう。
被害者請求の報酬は弁護士と行政書士どっちが高い?
このように,行政書士が被害者請求を代理したり,アドバイスしたりすることは弁護士法72条に違反すると考えられますが,現状,多くの行政書士がホームページ等で被害者請求に関して集客をしている以上,行政書士に被害者請求の手続きを依頼することを考えている方もいらっしゃると思います。
そこで,弁護士と行政書士の被害者請求の報酬を比較してみたいとおもいます。
弁護士が被害者請求の手続きを代理して行う場合,日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)の基準に基づいて契約することが多いと思います。
LACでは,被害者請求を含む事案簡明な自賠責保険の請求は,着手金・報酬方式ではなく,手数料方式で行うように規定されています。手数料は,自賠責保険金が150万円以下の場合は3万円,150万円を超える場合は2%と規定されています。
一方,行政書士の報酬をみると,着手金が3万円から5万円,報酬が自賠責保険金の15%から20%とするところが多いようです。
以下の表は,被害者請求の手続きの弁護士の手数料と行政書士の報酬を比較した表です(※自賠責保険金が150万円以下の場合3万円)。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険金 | 弁護士手数料(2%)※ | 行政書士報酬(20%) |
|---|---|---|---|
| 1級(別表Ⅰ) | ¥40,000,000 | ¥800,000 | ¥8,000,000 |
| 2級(別表Ⅰ) | ¥30,000,000 | ¥600,000 | ¥6,000,000 |
| 1級(別表Ⅱ) | ¥30,000,000 | ¥600,000 | ¥6,000,000 |
| 2級(別表Ⅱ) | ¥25,900,000 | ¥518,000 | ¥5,180,000 |
| 3級 | ¥22,190,000 | ¥443,800 | ¥4,438,000 |
| 4級 | ¥18,890,000 | ¥377,800 | ¥3,778,000 |
| 5級 | ¥15,740,000 | ¥314,800 | ¥3,148,000 |
| 6級 | ¥12,960,000 | ¥259,200 | ¥2,592,000 |
| 7級 | ¥10,510,000 | ¥210,200 | ¥2,102,000 |
| 8級 | ¥8,190,000 | ¥163,800 | ¥1,638,000 |
| 9級 | ¥6,160,000 | ¥123,200 | ¥1,232,000 |
| 10級 | ¥4,610,000 | ¥92,200 | ¥922,000 |
| 11級 | ¥3,310,000 | ¥66,200 | ¥662,000 |
| 12級 | ¥2,240,000 | ¥44,800 | ¥448,000 |
| 13級 | ¥1,390,000 | ¥30,000 | ¥278,000 |
| 14級 | ¥750,000 | ¥30,000 | ¥150,000 |
このように弁護士の手数料に比べて,行政書士の報酬の方が非常に高額であることが分かります。
弁護士費用特約があるの使えなかった!
このように,被害者請求の手続きに関する行政書士の報酬が非常に高額であるため,保険会社は,弁護士費用特約が付いていても行政書士の報酬を支払わないという方針をとるようになりました。
そうすると,弁護士費用特約があるにもかかわらず,行政書士の報酬の支払いに弁護士費用特約が使えず被害者の方が自己負担しなければならないというケースが非常に増えています。
さらに,東京海上日動火災は,平成27年10月1日以降の約款から,弁護士費用特約で報酬を支払う対象から行政書士を除外しています。この約款の規定は,行政書士の被害者請求の報酬について支払いを拒否することを明確にしたものと思われます。
被害者請求から弁護士に依頼しましょう
行政書士は,後遺障害認定があった後に,保険会社と示談交渉をすることができませんので,結局は,示談交渉を弁護士に依頼することになります。
行政書士の報酬がこれだけ高額で弁護士特約も使えないのであれば,被害者請求の手続きから弁護士に依頼した方が賢明ということになります。
ヤマト,全集配車にドライブレコーダー搭載するってよ
クロネコヤマトで有名なヤマト運輸がすべての集配車にドライブレコーダーを搭載するそうです。
交通事故の記録を残すこと,社員に運転の映像を視聴させて安全教育に役立てることが目的ということです。投資総額は10億円にもなるそうです。
10億円もかけてすべての集配車にドライブレコーダーを搭載するなんて儲かってる会社はやることが違うなと思ってしまいます。
しかし,どれだけ儲かっている会社でもドライブレコーダーの搭載が全く会社の利益につながらないのであれば10億円もの投資はしないと思います。
ドライブレコーダーの搭載によってヤマト運輸にどのような利益があるのか考えてみたいと思います。
交通事故による荷物の遅配がもたらす損害を減らすことができる
集配車が交通事故を起こせば,その集配車で荷物を運ぶことができなくなりますので,荷物の遅配が生じます。
荷物の遅配が生じれば,その集配車で運ぶ予定であった荷物をほかの集配車で運ばなければならなくなったり,配送ドライバーが時間外労働をしなければならなくなってしまいます。
そうすると,余計に人件費や燃料費などがかかってしまいます。
ヤマト運輸の集配車が年間でどのくらい交通事故を起こしたり,起こされたりするのかは分かりませんが,おそらくヤマト運輸が保有している集配車は何万台(もしかしたら何十万台?)もあると思いますので,そのうちの1%が交通事故を起こすだけでも会社に相当な額の損害が発生すると思います。
仮に集配車の1%程度の交通事故が発生し2000万円の損害が発生していたとして,集配車の交通事故が0になれば交通事故によって発生していた2000万円の損害を0にすることができます。
逆に言えば,交通事故が0になれば単純計算で2000万円の利益が発生するということになります。
もちろん,どんなに気を付けていても交通事故を0にすることは難しいと思いますが,交通事故の発生件数が集配車の0.5%程度になるだけでも,会社の利益が増えることに間違いはありません。
つまり,交通事故の発生を少なくできれば,交通事故による荷物の遅配がもたらしていた損害をそのまま会社の利益に転換することができるということです。
ドライブレコーダーを搭載する目的に「社員に運転の映像を視聴させて安全教育に役立てる」というのがありましたが,ドライバーの安全意識が高まれば,その分,ドライバーが起こす交通事故も少なくなると思います。
そうすれば,交通事故による荷物の遅配がもたらす損害は大きく減るのではないでしょうか。
自動車保険料などの損害保険料を下げることができる
運送会社にとって,自動車保険や荷物の損壊を補償する損害保険の保険料は収益を圧迫する大きな要因だと思います。
特に,自動車保険については,フリート契約で交通事故によって支払われた損害額の大きさによって翌年の自動車保険料の割引率が決まってきますので,損害額が大きければ,翌年の自動車保険料は割高になります。
これは,運送会社の話ではないのですが,多くの営業車を抱えている会社は,毎年のように営業車が交通事故を起こして自動車保険を使って支払う損害額が多額になるため,あまり保険料の割引が受けられず,毎年,高額な自動車保険料を支払っているという話を聞いたことがあります。
そうすると,ヤマト運輸も毎年高額な自動車保険料を支払っている可能性が考えられます。
ドライバーの安全意識が高まり集配車の交通事故が少なくなって,自動車保険を使って支払う損害額が少なくなれば,ヤマト運輸が毎年支払っている自動車保険料を下げることができます。
また,損保会社によっては,ドライブレコーダー搭載車の自動車保険料の割引をしていますので,すべての集配車にドライブレコーダーを搭載することで自動車保険料の割引を受けられるのかもしれません。
ドライブレコーダーで信号の赤青問題がなくなる
ヤマト運輸がすべての集配車にドライブレコーダーを搭載する目的に「交通事故の記録をする」というものがありますが,交通事故でよく登場するのが,信号の赤青問題です。
典型的には,信号機のある交差点での出会いがしらの事故ですが,この場合,必ずどちらかの運転手は信号を見ていなかったり,不注意で信号を見落としています。
ところが,なぜか,両方の運転手が自分が交差点に進入した時には信号の色は青だったと主張することが度々あります。
いずれかが赤信号で交差点に進入していなければ,衝突事故は発生しないのですから,必ずどちらかが嘘をついているか,記憶違いをしています。
交通事故で信号の色が問題となった場合,警察が作る交通事故の記録の中に信号サイクル表のような交差点のすべての信号の点灯時間と切り替わるタイミングを表した表が添付されます。
この信号サイクル表をもとに,運転手が信号機を確認した地点,その時の走行速度等の事実を総合して,交差点進入時の信号の色を判断するのですが,正直,それだけでは信号の色はわからないということの方が多いと思います。
その点,ドライブレコーダーがあれば,信号の色はドライブレコーダーの映像で一目瞭然ですので,信号の赤青問題は完全になくなります。
ヤマト運輸の集配車だけでなく,すべての自動車にドライブレコーダーの搭載が義務化されれば,交通事故の捜査が容易になるでしょう。
また,交通事故の民事事件においては,信号の色を問題とする責任論や過失相殺が争点ではなくなりますので,早期の解決が期待できるようになるでしょう。
いつか,すべての自動車にドライブレコーダーの搭載が義務化される日が来るのでしょうか?
※ブログタイトルは,「桐島,部活やめるってよ」をモチーフにしましたが,特に意味はありません。ごめんなさい。
保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?
交通事故の被害者の方から相談を受けていると,「保険会社から同意書が送られてきたんですがサインしていいんですか?」という相談を受けることがあります。
同意書にサインって言われると,何かまずいことになってしまうのではないかと感じるのでサインするのにためらうのもよくわかります。
おそらく,私も何もわからない状況で同意書にサインしろと言われたら抵抗感を強く覚えると思います。
では,加害者側の保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?
保険会社が治療費を支払うため
1つ目は,保険会社が治療費を支払うために必要な診断書と診療報酬明細書を医療機関から取得するためという意味があります。
この診断書と診療報酬明細書は自賠責用の診断書と診療報酬明細書です。
医療機関は,自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成して保険会社に治療費を請求します。
治療費を支払うためとはいえ,診断書や診療報酬明細書には傷病名や治療内容といった被害者の個人情報が記載されていますので,保険会社が診断書や診療報酬明細書を取得するためには被害者の同意書が必要となるのです。
なお,保険会社は,医療機関に治療費を支払ったら自賠責に支払った分を請求しますが,その際に,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が必要になります。
交通事故の治療費は自由診療で保険診療の2倍の金額になりますので(2.5倍で請求する医療機関もあったりします。),被害者としても,治療費は加害者側の保険会社に支払ってもらう必要があります。
治療費を自己負担しないためには,加害者側の保険会社から送られてくる同意書にはサインをする必要があります。
特に,事故直後に保険会社から同意書が送られてきた場合には,治療費を支払うためにという意味で送ってきているのでサインをしても問題ありません。
以前,私が担当した被害者の方で保険会社を信用できないからと言って,同意書に一切サインをせずに治療費を健康保険を使って自己負担し続けたという方がいらっしゃいました。
これも一つの戦略ではあるのですが,基本的にはこのような戦略をとらない方が賢明だと思います。
この被害者の方のようにすべての治療費を自己負担した場合,保険会社との示談交渉の際に自己負担した治療費を請求することになります。
自己負担した治療費がすべて交通事故と因果関係があると保険会社が認めてくれればいいですが,因果関係を争ってきて,裁判等でも因果関係が否定されれば,最終的に治療費を自己負担しなければならなくなってしまったということになりかねません。
一度,保険会社が支払った治療費は,保険会社もあまり争ってきませんし,争ってきたとしても一度支払っている以上,裁判等でも事故との因果関係が否定されることはあまりありません。
医療照会をするため(治療費の支払いを止めるため?)
2つ目は,保険会社が医療機関に対して医療紹介をするためという意味があります。
事故が軽度であるにもかかわらず,保険会社が想定しているよりも通院が続いているような場合に,保険会社が医療機関に対して治療の状況や就労制限の有無などを確認するために医療照会をすることがあります。
保険会社が医療機関に対して医療照会をするためには同意書が必要となります。
この場合,多くのケースでは,保険会社がもう治療費の支払いを止めたいと考えていることが多いと思います。
それじゃあ,同意書にはサインしなければいい!となりそうですが,そうもいきません。保険会社は,同意書にサインしないなら治療費をこれ以上支払えないと言ってくるからです。
それでは,いずれにしろ治療費の支払いは止められてしまうのだから同意書にサインをしてもしなくてもいいじゃないかということになりそうです。
まあ,それでもいいように思いますが,医療照会の結果が出るまでには時間がありますので結果が出るまでの治療費は保険会社に支払ってもらった方がいいですし,むしろ,それを利用して治療費の支払いを続けさせるようにもっていける可能性もあります。
そのため,医療照会が目的の同意書であってもサインはしておいた方がいいと思います。
治療費の支払いを止められても対策はあります。
保険会社が治療費の支払いを止めてきたら
では,医療照会の結果,保険会社が治療費の支払いを止めてきたらどうすればいいのでしょうか?
まずは,治療費の支払いを健康保険での支払いに切り替えるようにしましょう。
先ほども説明したように交通事故の治療費は,医療機関は自由診療で対応しているところが多いのですが,交通事故の治療であっても健康保険を利用することができます。
次に,症状が継続していることをしっかりと医師に伝え,最低6ヶ月以上,定期的に通院するようにしましょう。
通院期間が6ヶ月未満ですと後遺障害が非該当となる可能性が極めて高くなります。
最後に,医師に後遺障害診断書をしっかりと書いてもらうようにしましょう。
後遺障害診断書をしっかりと書いてもらえて後遺障害が認定されれば,保険会社が支払いを中止した後に自己負担した治療費についても,事故と因果関係がある治療費として保険会社に負担させることができる可能性があります。
交通事故で怪我をしたら弁護士に相談しよう!
交通事故で怪我をしたら慰謝料が発生しますし、後遺障害が認定される可能性があります。
慰謝料は最低でも数十万円になりますし、後遺障害が認定された場合には、賠償金は数百万円から1000万円以上になることもありますので、弁護士に相談しましょう!
交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。
死亡事故の逸失利益はどうやって計算するの?
逸失利益とは,将来生きていれば得られたはずの収入を填補するという損害項目です。 死亡事故の逸失利益は,賠償金の大部分を占めますのでどのように計算をするかをしっかりと理解しておく必要があります。死亡事故の逸失利益は以下の計算式で計算をします。 基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 死亡事故一般については,「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。主婦も逸失利益は認められる!
基礎収入は,会社員の場合には交通事故に遭った前年の年収を基準としますが(「死亡事故の逸失利益(会社員の場合)」をご覧ください。),専業主婦の場合,収入がありませんので逸失利益は認められないということになってしまうのでしょうか? それではあまりにも専業主婦の方の家事労働を軽視しすぎですので,収入がないからと言って逸失利益が認められないということは断じてありません! むしろ,専業主婦の方が家事をしっかりとしてくれていることで,旦那さんが仕事に専念できていますので,当然,専業主婦の方の家事労働も対価性が認められます。 では,専業主婦の方の収入はどのように決められるのでしょうか? 専業主婦など収入のない方の場合,毎年,厚生労働省が発表している賃金統計を使います。この賃金統計を「賃金センサス」といいます。省略して「賃セ」といったりします。 専業主婦の方の場合は,、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢」の平均賃金を基礎収入にします。 ちなみに,令和元年の賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢の平均賃金は,388万100円になります。賃金センサスは毎年発表されて基本的には金額も変動していますので,いつの年の賃金センサスを使うのかについては注意する必要があります。 また,最近は,専業主婦の方よりも正社員だったり,パートだったり仕事を持たれている女性も多くなっています。このような兼業主婦(言い方が古くてすみません。もっといい言い方ないですかね?)の方の場合,基礎収入は,仕事から得ている収入と賃金センサスのいずれを利用することになるのでしょうか? 兼業主婦の方の場合,事故前年の年収と賃金センサスの平均賃金を比較して高額な方を基礎収入とします。パートの方ですと,ほとんどのケースで賃金センサスの平均賃金の方が高額になります。そのため,保険会社は,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とせずに事故前年の年収を基礎収入として逸失利益の計算をすることがありますので注意しましょう。 主婦の方の生活費控除率は以下の表のとおり30%になります。| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |
| 年金部分 | 30%~50% |
事故当時40歳で子供2人を持つ専業主婦の逸失利益は5000万円近くになります
基礎収入は,事故の年によって違ってくるのですが,ひとまずここでは先ほど例で挙げた平成27年の賃金センサスの平均賃金372万7100円とします。 生活費控除率は,男性の場合,扶養家族の人数によって生活費控除率が変わってきましたが,専業主婦の方の場合は基本的には被扶養者になりますので,子供がいても生活費控除率が30%から変わることはありません。 労働能力喪失期間は67歳までの27年になります。27年に対応するライプニッツ係数は18.3270になります。 そうすると,この場合の逸失利益は以下の計算式のとおりとなります。 388万100円×(1-30%)×18.3270=4977万7414円事故当時25歳の兼業主婦(大卒)で事故前年の年収が400万円で子供がいない女性の逸失利益は7800万円以上になります
この場合,基礎収入は応用問題になります。先ほど,兼業主婦の場合は,事故前年の年収と賃金センサスの平均賃金を比較してのいずれか高額の方を基礎収入にすると説明をしました。 そうすると,事故前年の収入400万円と令和元年の賃金センサスの平均賃金372万7100円を比較すると事故前年の年収400万円の方が高額なので,基礎収入は400万円になりそうです。 しかし,事案をよく見ていただくとこの方は「25歳」の「大卒」となっています。 30歳未満の若年労働者の方の場合には賃金センサスのうち全年齢の平均賃金を使うのですが,25歳の大卒の場合は,女子大卒全年齢の平均賃金を使うことになります。 令和元年の賃金センサスの女子大卒全年齢の平均賃金は472万400円になります。 そうすると,この場合は事故前年の年収よりも全労働者全年齢の賃金センサスの方が高いということになるので,基礎収入は472万400円になります。 生活費控除率は女性なので30%になます。 労働能力喪失期間は67歳までの42年となり,42年に対応するライプニッツ係数は23.7014になります。 そうすると,この場合の逸失利益は以下の計算式のとおりとなります。 472万400円×(1-30%)×23.7014=7831万6061円民法改正によって中間利息控除をするための年利が変更になったことによって逸失利益が民法改正前(2020年3月31日以前)よりも高額になる!
2020年4月1日に民法が改正されて、法定利率がそれまでの年5%から現状は3%に変更になりました(今後、法定利率は3年ごとに見直しされます。)。 これに合わせて中間利息控除の利率も現状3%に変更になったため、中間利息として控除される金額が民法改正前(2020年3月31日)に比べて少なくなりました。 中間利息として控除される金額が少なくなったということは、その分、逸失利益が高額になるということです。 2020年4月1日以降に発生した交通事故については、改正後の民法が適用されますので、逸失利益の計算をしっかりとしましょう。 亡くなった被害者の大事な賠償金ですので、逸失利益を含めて賠償金が総額でいくらになるのかはしっかりと確認した上で解決するようにしましょう。実際にどれくらいの逸失利益、賠償金になるのかは弁護士に相談しよう!
実際にどれくらいの賠償金になるのかは、それぞれの事情によって違ってきますので、弁護士に相談しましょう! 交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。事前認定って何?被害者請求って何?
交通事故にあった方でも「事前認定」や「被害者請求」という言葉はあまり聞いたことがないと思います。私も弁護士になるまで知りませんでしたし、交通事故の分野を担当していなければ弁護士さんの中にも知らない方がいるかもしれません。
「事前認定」と「被害者請求」はそれくらい一般的に馴染みのない言葉ということです。
「事前認定」と「被害者請求」の説明をする前に、交通事故にあった場合に民事での解決の流れを確認しておきましょう。
①事故発生→②通院・入院→③症状固定→④後遺障害認定→⑤示談、裁判等で解決
という流れになります。詳しくは「交通事故の解決までの流れ」をご覧下さい。
「事前認定」と「被害者請求」は④後遺障害認定に関係する言葉です。後遺障害とは、事故によって怪我をして治療を続けたけど、症状が残ってしまった状態をいいます。
「事前認定」は、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害の認定を受ける手続きです。
「被害者請求」は、被害者の方もしくはその代理人が自賠責保険会社に対して直接後遺障害の請求をして後遺障害認定を受ける手続きです。
事前認定と被害者請求は、いずれも後遺障害の認定を受ける手続きということになります。
事前認定と被害者請求はどっちがいいの?
では、後遺障害の認定を受ける場合、事前認定と被害者請求ではどっちの手続きがいいのでしょうか?
事前認定は、被害者の方に代わって任意保険会社が後遺障害の認定に必要な資料を集めますので、後遺障害の認定に当たっては被害者の方の負担はかなり少ないです。
一方、被害者請求は、被害者や被害者の代理人が後遺障害の認定に必要な資料を集めることになります。
そうすると、事前認定の方が保険会社の担当者が後遺障害の認定に必要な資料を集めてくれるし楽でいいじゃん!って思われるかもしれませんが、これは大きな間違いです。
先日も書きましたが任意保険会社の担当者はできるかぎり被害者に支払う賠償金を低額に抑えようとします(「敵(損保会社)は味方のふりをする」をご覧ください)。後遺障害が認定されると後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が認められますので、賠償金が跳ね上がります。
認定される等級によっては賠償金が数千万円という金額になりますので,保険会社の担当者はできるだけ低い後遺障害等級,もしくは非該当になって欲しいと考えます。
以前,私が担当した事件で保険会社の担当者が症状は軽いから後遺障害はないという内容の資料を事前認定の手続きで提出しているということがありました。
ここが事前認定の一番危険なところなのです。つまり,事前認定だと資料の収集や提出を保険会社の担当者に任せることになってしますので,後遺障害等級が低くなったり,非該当になるような資料を提出されてしまう可能性があるということです。
一方,被害者請求は,被害者の方もしくはその代理人が資料を集めますので,後遺障害が認定されるのに必要十分な資料を自賠責に提出することができます。そのため,想定していた後遺障害等級が認定されなかったり,非該当になったりというリスクが事前認定の場合に比べて格段に低くなります。
症状に見合った後遺障害の認定を受け,適正な賠償金を支払ってもらうためには,後遺障害の認定は,被害者請求で行うべきです。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。