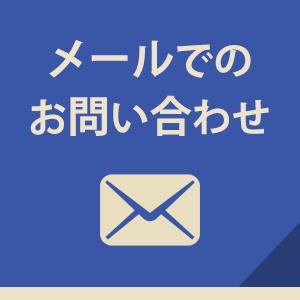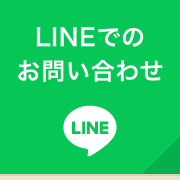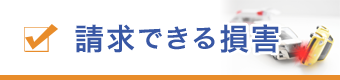横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
弁護士 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
交通事故に遭って損保会社と対等に示談交渉するには弁護士が必要
交通事故に遭って損保会社と示談交渉するには弁護士が必要です。
以前にも「交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)」で解説しましたが、加害者側の損保会社の担当者は、会社の利益になるような賠償案しか提案しませんし、交通賠償の知識もそれなりにありますので、一般の交通事故の被害者が対等な示談交渉をできるはずがないからです。
対等でない当事者が交渉をしても、交通賠償の知識のない一般の交通事故の被害者が交渉では負けてしまうため、適正な賠償を受けることも当然できません。
交通事故の被害者が適正な賠償を受けるために、被害者の立場に立って示談交渉してくれる弁護士に依頼することが必要です。
交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります
当事務所には、交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります。弁護士を変更したいという理由は、それぞれ違うのですが、以下のような理由が多いです。
①弁護士と連絡が取れない
②弁護士ではなく事務員しか対応してくれない
③弁護士が交通事故に詳しくない
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれない
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれない
①弁護士と連絡が取れないと②弁護士ではなく事務員しか対応してくれないという理由は、非常に多い変更理由です。
おそらく弁護士が多くの事件を抱えて依頼者との連絡を怠っているか、事務員任せにしているからだと思います。
③弁護士が交通事故に詳しくないという理由については、弁護士もすべての分野に精通しているわけではないので、運悪く交通事故に詳しくない弁護士に当たってしまったということなんだと思います。
特に交通事故は、保険の知識、医学の知識、工学の知識といった法律以外の知識が必要になりますが、そのような知識は当然司法試験で勉強するはずがありません。
交通事故を専門としている弁護士のほとんどが、弁護士になってから交通事故の事件を多く手掛けて保険、医学、工学などの知識を身に着けているので、交通事故は経験がものをいう分野です。
しかし、交通事故は、弁護士費用特約があるためか交通事故の経験のない弁護士が多く参入してくる分野になってしまいました。
特にもともとサラ金の過払いを多く手掛けていた法律事務所が多く参入してきており、そういった法律事務所は多額の資金をかけて広告で集客をするので、交通事故に詳しくない弁護士が担当になって、被害者の方が弁護士を変更したいと考える事態は多く生じているのではないかと思います。
弁護士を変更したいと考えた被害者の方は、変更を考えてから、交通事故の賠償に関する知識を調べるようで、その過程で当事務所のホームページを見ていただくことが多いようです。
当事務所のホームページには、被害者が契約していた保険を使った解決、医学的な観点が問題となる後遺障害の事案、工学的な観点からの検討が必要な過失相殺が問題となった事案など多くの解決実績やコラムを掲載していますので、それを見て交通事故に詳しくて強い弁護士だと思ってご連絡をいただくことが多いようです。
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれないという理由は、休業損害の交渉をしてくれないという内容がもっとも多いです。
特に自営業者の方が多いです。「個人事業主の休業損害は簡単じゃない~節税もほどほどに~」でも解説しましたが、自営業者の休業損害は、きちんと確定申告をしていない人がいたり、確定申告をしていても必要以上に経費を計上して所得金額がすごく少ない人がいるため、そのような方は、損保会社が休業損害の支払いを拒否することがあります。
また、会社員と違って、第三者が勤怠管理をしているわけではないので、本当に仕事を休んだかを確認できないということで拒否されることもあります。
自営業者の方でも証拠書類をそろえれば損保会社も休業損害を支払うのですが、そもそもそのような証拠書類を揃えることを弁護士が被害者の方にアドバイスをしていないということが多いようです。
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれないという理由は、被害者の方が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談で解決を勧めるということで変更を希望する方が多いです。
示談交渉の時に、過失割合や後遺障害を損保会社が争ってきたときに弁護士の考えと被害者の方の考えが合わないということなんだと思います。
この理由に関しては、難しい問題をはらんでいて、弁護士はできるだけ依頼者の希望通りに解決したいと考えています。
しかし、交通事故紛争処理センターや裁判になった場合に、示談交渉時の提案よりも不利になる可能性がある場合には、依頼者が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談での解決を勧めることがあります。
もちろん、なぜ示談で解決した方がいいのかは説明をしますが、それでも納得してくれない依頼者の方がいらっしゃいます。
その場合には、やむを得ず弁護士の方から辞任する、もしくは依頼者の方から解任されるということもあります。
交通事故の賠償請求のために依頼した弁護士の変更方法
弁護士の変更を考えている被害者の方の中には、弁護士をすると違約金が課されるのではないかなど心配する方が多くいらっしゃいます。
弁護士との委任契約の内容にもよりますが、基本的には違約金を変更設定して委任契約を締結する弁護士はいないと思います(ただし、過去に1件だけ途中解約した場合には違約金を課すという契約内容で委任契約を締結させる法律事務所がありましたので、契約の時は途中解約で違約金が課されるか必ず確認した方がいいです。)。
その代わりに着手金は着手時に支払われるものですので、途中で辞任や解任があっても返還されることはありません。
弁護士がぜんぜん仕事をしていないときには、返還交渉をしてみてはどうですかと勧めることもありますが、基本的には返還されないと思っておいた方がいいと思います。
違約金がなければ、あとは弁護士と依頼者の合意で解約ができますので、弁護士に遠慮せずに解約の申し出をして下さい。
解約したうえで、書類についてはすべて返却してもらってください。
時々、資料を返却してくれない弁護士がいるようですが、基本的には、弁護士が取得した資料は依頼者の委任があって取得できた資料になりますので、依頼者が返却を求めることができます。
ちなみに弁護士費用特約があれば、新しく依頼する弁護士の着手金も保険金がでますので安心して変更することができます。
弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください
当事務所では、すでに弁護士を依頼している交通事故の被害者の方から弁護士を変更したいという相談を多く受けます。
事務所のある横浜や神奈川だけでなく、東京、埼玉、千葉、静岡といった県外からのご相談も多くあります。
電話、メール、LINEでご相談を受け付けておりますので、弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください。
関連記事
交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するために弁護士費用特約の使い方を交通事故に強い弁護士が解説!
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しよう!
交通事故の被害にあったら、加害者が契約している任意保険の担当者と賠償交渉をすることになります。
任意保険の担当者、交通事故を専門としていない弁護士よりも交通事故の賠償に関する知識がありますので、被害者の方が思うような賠償を受けられないこともあります。
任意保険の担当者の中には、被害者の方に交通事故の賠償の知識がないことをいいことに自賠責の範囲で終わらせようとする担当者もいます。
任意保険が被害者に賠償をした場合、任意保険は、自賠責に対し、傷害分120万円、後遺障害分が等級に応じて75万円から4000万円まで求償することができます。
簡単に言ってしまうと、治療費等の支払いについては120万円以内、後遺障害分の損害は等級に応じて支払われる金額以内であれば、任意保険の損保会社は、一切負担をしなくていいということになるのです。
このような知識のない一般の方が任意保険の担当者と交渉しても十分な賠償を受けることはできません。
そうすると、被害者の方は、交通事故の被害に遭った上に、十分な賠償も受けられないとなり、踏んだり蹴ったりの状態です。
交通事故の被害に遭ったのに十分な賠償も受けられないなんてひどい状態を避けるために、交通事故の被害にあったら、損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しましょう!
弁護士費用特約が使えるか確認しよう!
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するといっても弁護士費用は安くありません。
そんなときに使えるのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、自動車やバイクの交通事故の被害者が加害者などの賠償義務者に対して損害賠償請求をするために弁護士に依頼した費用を支払うときに使える保険です。
弁護士費用が使えるかどうかは、加入している自動車保険の保険証券やネット系損保のマイページで確認することができます。
また、保険契約者(記名被保険者)だけでなく、記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居する未婚の子が交通事故の被害者になったときにも利用することができます。
ときどき、保険契約者しか弁護士費用特約を利用できないと勘違いしている方がいるので、交通事故の被害者が保険契約者でない場合も、ぜひ弁護士に相談して下さい。
交通事故に詳しい弁護士であれば、必ず弁護士費用特約が使えるかどうか教えてくれるはずです!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単です。
まず、ご自分が契約している保険会社に事故受付の連絡をして下さい。
事故受付は、弁護士費用特約だけでなく搭乗者傷害保険や人身傷害保険を利用するときにも必要なので、事故に遭ったら必ずしましょう。
ときどき、交通事故の被害者だから自分の契約している保険会社には連絡しなくていいと思っている被害者の方がいますが、交通事故の被害に遭ったら何かしらの保険を使える可能性があるので、必ず事故受付の連絡はしましょう。
次に、ご自分が相談したいと思う弁護士を探しましょう。
弁護士費用特約で相談や依頼ができる弁護士は、保険会社からの紹介などではなくご自分で選ぶことができます。
どんな弁護士を選んだらいいのかは、交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(交通事故に強い弁護士の選び方)をご確認下さい。
最後に、相談、依頼する弁護士を決めたら保険会社に連絡して下さい。
今は、各保険会社が約款で弁護士費用特約の支払基準を設定していますので、保険会社からその弁護士に保険会社の支払基準で対応できるのかという確認があります。
最近は、保険会社の支払いが厳格になっていますので、着手金と報酬の最低金額を定めている法律事務所の場合は、自己負担が発生する場合もあります。
このように、弁護士費用特約の使い方は、①保険会社に事故受付の連絡をする②相談、依頼する弁護士を探して決定する③どの弁護士に相談、依頼するのかを保険会社に連絡するだけなので、すごく簡単です!
弁護士費用特約が使えないこともある
弁護士費用特約が使えない場合は、保険会社の約款に規定されています。
結構、弁護士費用特約が使えない場合は多いので、弁護士費用特約が使えない代表的なケースを紹介します。
①被害者が無免許運転で交通事故の被害に遭った場合
②被害者が飲酒運転で交通事故の被害に遭った場合
③交通事故の被害者と加害者が夫婦や親子の場合
それ以外には、弁護士費用特約が使えないというわけではありませんが、弁護士費用特約には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という限度額があります。
限度額を超える弁護士費用になった場合には、自己負担が発生します。
ただし、自己負担が発生するようなケースは、加害者側の保険会社から支払われる賠償金もかなり高額となっているケースが多いですし、裁判で解決すれば、弁護士費用が被告から支払われますので、実質的な負担はあまりないと思います。
弁護士費用特約がなくてもクロノス総合法律事務所であれば相談も依頼も無料でできます!
弁護士費用特約の使い方を説明してきましたが、弁護士費用特約がなくても弁護士に相談、依頼することを諦めないでください。クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者からの相談は無料で対応していますし、着手金も無料で対応しています。
電話・メール・LINEで無料法律相談、着手金無料、報酬も自己負担0円のクロノス総合法律事務所にご連絡下さい。
クロノス総合法律事務所の解決実績
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得
30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)
関連記事
交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)
後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!
交通事故の被害に遭ったら、加害者側の損保会社の担当者が事故の対応をします。損保会社の担当者は、交通事故の被害者のために動いてくれるでしょうか?
当たり前の話ですが、損保会社の担当者は損保会社の従業員です。そして、損保会社は営利会社ですので、利益を上げることが会社の目標です。
そうすると、損保会社の担当者は、会社の利益のために行動していると考えた方がいいですね。当然、被害者の対応をするときも同じです。
会社の利益にならないと考えれば、治療費の支払いを打ち切りますし、休業損害もいつまでも支払うということはありません。
しかも、損保会社の担当者は、それなりに交通賠償の知識がありますので、被害者が何を言っても丸め込まれてしまうでしょう。
加害者側の損保会社の担当者がどんな立場で動いているかを知ったら、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談した方がいいって思いませんか?相談しようって思いますよね。
後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しましょう!
では、どんな弁護士に相談したらいいのでしょうか。
損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!
先ほどもいいましたが、損保会社の担当者もそれなりに交通賠償の知識がありますので、交通事故の知識が全然ない弁護士を選んでしまうと損保会社の担当者の言っていることを鵜呑みにしてしまうので、まずは損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょう。
でも、交通賠償の知識がある弁護士かどうかってどうやって判断したらいいのかわかりませんよね。それは、あとで説明しますね。
損保会社の担当者に負けない知識のある弁護士を選ぶのは当然のこととして、交渉でも損保会社の担当者に負けない弁護士を選ばなければ、適正な賠償を受けることはできません。
たとえば、損保会社の担当者は、弁護士が交渉相手でも慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した金額の70%から80%程度の金額でしか提示してこないことが多いです。
中には、粘り強く交渉することなく、すんなりと終わらすために弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいるようです。
当事務所は、よほどのことがない限り、弁護士基準の100%を下回る金額で示談することがなく、示談できなければ、裁判か交通事故紛争処理センターに申立てをして解決するようにしています。そのため、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいることに驚きですが、話を聞くと結構多いようです。
解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!
先ほど、損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょうという話をしました。交通賠償の知識のある弁護士かどうかを短い相談時間の中で確認するには、相談した交通事故の解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれるかどうかで判断するといいと思います。
交通賠償の知識のある弁護士であれば、被害者の方からある程度情報を確認すれば、それなりに解決方針や賠償金の見込金額を説明することができます。さらに、交通事故の解決が経験豊富な弁護士であれば、かなり確度の高い説明をすることができるはずです。
当事務所の場合、解決の方針と賠償金の見込金額を必ず説明するようにしています。もちろん事故直後など情報が不確定な時は、ある程度、幅を持たせた説明をしていますが、後遺障害が認定されている事案であれば、かなり確度の高い説明をしていると思います。
特に、賠償金の見込については、弁護士基準で計算するといくらになるのかという説明をしています。
弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのか説明してもらえない場合には、その弁護士は弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士である可能性が高いです。
もちろん、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかを説明すると、解決の目標金額がその金額になってしまうので、弁護士としては仕事のハードルを上げることになります。でも、そうすることで、しっかりとした仕事をしなければ!という戒めにもなるので、当事務所の場合、ほとんどのケースで、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかという説明をしています。
後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!
交通事故の賠償は、後遺障害が認定されるかどうかで金額が大きく変わってきます。一番低い等級の14級が認定されるだけでも、賠償金は150万円以上は変わってきます。そうすると、本当は後遺障害が認定される事案なのに、それが見落とされてしまうと、被害者の方が得られる賠償金は大きく変わってきてしまいます。
そのためには、被害者が負った怪我や症状からどのような後遺障害が認定される可能性があるのかを判断できなければなりません。
ただ、後遺障害の知識については、医学的な知見も必要なので、勉強しただけでは限界があって経験がものをいいます。
そうすると、認定される可能性のある後遺障害の説明までしてくれる弁護士であれば、後遺障害事案の経験が豊富な弁護士である可能性が高いということになります。
裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!
最後に、裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選びましょう。先ほども言ったように、損保会社の担当者は、示談では、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でしか提示してこないことが多いです。
弁護士は、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でも100%の金額でも報酬に大きな違いはないので、正直に言うと、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談して多くの交通事故の案件を回した方が報酬面ではいいということになります。
しかし、それでは被害者の方にとっては最善の解決とは言えません。中には、100%まで金額を上げたとしても30万円くらいしか変わらないという事案もあります。それでも被害者の方にとっては大きな金額です。
裁判や交通事故紛争処理センターにもっていけば、よほどのことがない限り弁護士基準で計算した金額を下回ることがないので、いずれかの方法で解決すれば、弁護士基準の100%で解決することが可能です。
なので、示談交渉で、損保会社の担当者が弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額しか提示しなかった場合には、どうやって解決するかを確認して、裁判や交通事故紛争処理センターで解決するといってくれる弁護士を選びましょう。
まとめ
●後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!
●交通賠償の知識と交渉で損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!
●解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!
●後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!
●裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!
クロノス総合法律事務所の解決実績
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得
30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)
こちらの関連記事もご覧ください
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するために弁護士費用特約の使い方を交通事故に強い弁護士が解説!
80代男性の歩行中の事故で中足骨を骨折し、後遺障害は非該当だったものの10%の過失相殺後をした後で約135万円を獲得しました。詳しくは解決実績をご確認下さい。
圧迫骨折により脊柱変形11級の後遺障害が認定された高齢女性に休業損害,逸失利益が認められて解決することができました。詳しくは解決実績をご確認ください。
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、正式には「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的として、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を行うADR機関です。
法律相談、和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。和解あっせんの進め方は、担当弁護士によっても異なるのですが、ほとんどの担当弁護士は、被害者と加害者側の保険会社もしくは共済組合の担当者からそれぞれの話を聞いて、基本的には弁護士基準で計算した賠償金で和解を勧めることが多いです。
交通事故紛争処理センターは本部のほかに7つの支部と3つの相談室がある
交通事故紛争処理センターは、東京本部のほかに、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡に支部があり、さいたま市、金沢、静岡に3つの相談室があります。
どこでも利用を申し込めるというものではなく、申立人の住所地又は事故地に対応した本部、支部、相談室で利用を申し込むことになります。
一度、本部、支部、相談室のいずれかに利用を申し込んだ場合、そこが気に入らないからといって申し込みを取り下げてほかの本部、支部、相談室に利用を申し込むということはできません。例えば、本人がさいたま相談室で利用を申し込んで、途中から東京の弁護士に依頼した場合でも東京本部に利用の申し込みをすることはできませんので注意が必要です。
交通事故紛争処理センターを利用できない場合
加害者側の保険会社又は共済組合が保険協会又は共済連合会に属していない場合
交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との示談をめぐる紛争を解決することを目的としていますので、加害者側に保険会社又は共済組合がついていない場合には利用することができません。
保険会社及び共済組合は以下の組織に加盟している保険会社又は共済になります。
・日本損害保険協会
・外国損害保険協会
・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
・全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
・全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
紛争の種類によって利用できない場合
また、紛争の種類によっても交通事故紛争処理センターを利用できない場合があります。以下の場合には交通事故紛争処理センターを利用することができません。
①自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
②搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、被害者(側)が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
③自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争
交通事故紛争処理センターで解決するメリット
無料で利用できる!
交通事故紛争処理センターは、最初に説明したように担当弁護士が和解のあっせん等を行いますが、利用するにあたって費用はいりません。無料で利用することができます。そのため、賠償金があまり望めないような交通事故の場合に交通事故紛争処理センターを利用しても費用倒れになることはありません。
迅速に解決することができる!
交通事故紛争処理センターのホームページのQ&Aをみると以下のような説明があります。
「人身損害の場合は、通常3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。物損の多くの場合は、2回程度で取り扱いが終了しています。」
交通事故の裁判の場合ですと、裁判を3回行っただけでは判決はもちろん和解にもならないので、3回で解決できれば迅速な解決といえます。
審査会の判断に保険会社及び共済組合は拘束される
和解のあっせんによって解決ができない場合、審査会の判断で解決することになります。審査会はあっせん担当の弁護士とは違う3人の弁護士で構成され、あっせん担当の弁護士から事案や争点の報告受け、両当事者の主張を確認した上で賠償金の判断を行います。
審査会が下した賠償金の判断は、被害者側は納得がいかなければ、その判断で解決することなく裁判を起こすことができます。
それに対して、保険会社及び共済組合は、どんなに納得がいかない内容の賠償金であっても審査会の判断に拘束され、裁判を起こすことはできません。
実際に交通事故紛争処理センターを利用してみての感想
これまで何件もの交通事故を交通事故紛争処理センターに申立てをして解決をしましたが、事案とあっ旋の担当者によって交通事故紛争処理センターのメリットを享受できるかどうか変わってくると思っています。
後遺障害、過失相殺が争点となっていると早期に解決ができない可能性が高い
後遺障害や過失相殺が争点になっていると保険会社や共済組合はかなり力を入れて争ってきます。後遺障害が争点となる事案では、裁判だと通院した病院のカルテなどを取り付けて意見書を作成したりするのですが、交通事故紛争処理センターでもカルテなどを取り付けて意見書を作成して後遺障害を争う保険会社や共済組合があります。そうすると、3回で終わることはなく、1年以上時間をかけても解決しないということがあります。現に、今も交通事故紛争処理センターでそのような事案を担当しています。
交通事故紛争処理センターの担当弁護士がきちんとあっ旋をしない場合には早期に解決できないことが多い
交通事故紛争処理センターでの解決は、初めに説明した通りセンターの担当弁護士があっせんをしますので、早期に解決できるかどうかは、センターの担当弁護士によるところが非常に大きいです。
中には、保険会社がむち打ちの事案で医療記録を取得して後遺障害14級を争うと言ってきたときに、むち打ち事案で後遺障害14級が認定されている場合には、14級の後遺障害があることを前提に賠償案を出すので、医療記録の取り付けをしても無駄だとはっきり言ってくれて、保険会社側の医療記録の取り付けを認めずに解決をしてくれたような素晴らしい担当弁護士もいます。
しかし、一方で、早期解決に向けてきちんとあっ旋をしない担当弁護士もいるので、そのような場合には解決まで長引くことを覚悟しなければなりません。きちんとあっ旋をしない弁護士は、裁判のように一方が主張をしたらもう一方に反論をさせて、さらにその反論に再反論をさせてということを漫然と繰り返すという特徴があります。やはり、交通事故紛争処理センターは裁判とは異なりますので、そのことを意識して何度も主張と反論を繰り返させるような進め方はやめて欲しいなと思います。
賠償金の金額だけに争いがある事案が向いている
交通事故紛争処理センターでの解決が向いているのは、賠償金の金額だけに争いがあるという事案だと思います。具体的に言うと、例えば、後遺障害は10級が認定されて争いがなく、もちろん過失にも争いがない、争いがあるのは、後遺障害慰謝料が弁護士基準の550万円を下回っているという点だけというような事案です。
極端な話、このような事案であれば、1回で解決することもあります。
それと、先輩弁護士にいちゃもんをつけることになってしまうのであまり大きな声では言えませんが、担当弁護士の方、損害額計算書だけでなく当事者の申立書や証拠ももう少し見て欲しいなって思います。
交通事故紛争処理センターの所在地一覧
東京本部
〒163-0925 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
TEL.03-3346-1756 FAX.03-3346-8714
札幌支部
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241 FAX.011-261-4361
仙台支部
〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング11階
TEL.022-263-7231 FAX.022-268-1504
名古屋支部
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491 FAX.052-581-9493
大阪支部
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277 FAX.06-6227-9882
広島支部
〒730-0032 広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421 FAX.082-245-7981
高松支部
〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階
TEL.087-822-5005 FAX.087-823-1972
福岡支部
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881 FAX.092-716-1889
さいたま相談室
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271 FAX.048-650-5272
金沢相談室
〒920-0853 金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階
TEL.076-234-6650 FAX.076-234-6651
静岡相談室
〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル4階
TEL.054-255-5528 FAX.054-255-5529
個人事業主の休業損害は簡単じゃない
交通事故に遭って仕事を休んだ場合,休業損害を請求することができます。
通常,会社員の方であれば,「休業損害証明書」を会社に作成してもらって,それを保険会社に提出すれば,休業損害を支払ってもらえます。
しかし,個人事業主は会社に休業損害証明書を作ってもらうことはできません。
つまり,個人事業主の場合,休業損害証明書によって収入の日額や休業日数を確認することができないので,休業損害証明書から休業による損害額を把握することができないということになります。
保険会社は,休業損害証明書によって休業による損害額を把握して支払いをするため,これを確認することができない個人事業主の方の場合,休業損害を最低額でしか支払ってこないということが多くあります。
そのため,個人事業主の被害者の方が求める休業損害を保険会社に支払わせることは簡単じゃなく,揉めることが非常に多くあります。
売上を請求することはできないけど固定費を休業損害として請求できる
個人事業主の方から休業損害の相談を受けると,多くの方から売上を休業損害として請求できないのかという質問を受けます。
確かに,個人事業主の方が仕事を休めば,それだけ売上が下がりますので,売上金額そのものを休業損害として請求したいと思う気持ちはよくわかります。
しかし,売上を上げるためには経費が必要となりますが,休業したことによって支払いを免れる経費がありますので,売上そのものを休業損害として認めてしまうと,支払いを免れた経費の分まで休業損害に含めてしまうことなってしまいます。
そのため,売上そのものが休業損害として認められることはありません。
原則として,売上ではなく所得金額が個人事業主の休業損害となります。
もっとも,家賃など毎月固定でかかる経費(固定費)については,休業しても支払わなければならない経費ですので,休業損害として請求することができます。
また,青色申告で確定申告をしている場合には,青色申告特別控除という特典を受けています。
青色申告特別控除とは,所得金額から最高65万円を控除して課税所得を下げることができるというものです。
これは,実際に支出したものではないので経費には当たりませんので,休業損害に含めることが可能です。
そうすると,所得金額に固定費と青色申告特別控除額を足した金額が個人事業主の休業損害ということになります。
確定申告をしていない場合や事業に直接関係ない費用を経費として計上していた場合は?
個人事業主の所得金額や固定費は,基本的には事故前年の確定申告書と添付書類から把握することになります。
では,確定申告をしていなかった場合にはどうなるのでしょうか?
この場合でも何かしら収入がなければ生活ができないので休業損害は認められます。
ただし,確定申告書以外の資料で収入や経費を証明しなければならないので,正確な休業損害の証明はかなり難しいといっていいでしょう。
正確な休業損害の証明ができない場合は,賃金センサスを基準に,平均賃金の50%から60%くらいの金額を収入とみて,日額の計算をすることになってしまいます。
そうすると,日額は1万円を下回るような金額になってしまいます。
また,個人事業主の方だと,事業と直接関係ない費用を経費として計上しているということがあります。
例えば,家族の携帯電話の料金を経費として計上いるような場合です。
このような場合にも,やはり,経費として計上している費用が事業と直接関係ないものであることを被害者側で証明しなければなりません。
先ほど例にあげた携帯電話の料金であれば明細があるので明細と確定申告書の決算書から事業と直接関係のない費用であることを立証できるかもしれませんが,一般的には,事業と直接関係のない費用であることを立証することはかなり難しいです。
保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがある
保険会社から賠償金の提示がある前に依頼を受けると,保険会社が過失割合をどのように考えているかは分からないことが多いです。
保険会社が支払いを拒否しているなどの事情があれば,保険会社が被害者の過失割合を相当大きく考えているということが分かるのですが,ほとんどの場合,被害者に多少の過失があっても,保険会社は治療費等の支払いをして,示談の時に過失相殺をするのが一般的ですので,示談交渉の前に具体的な過失割合の話をすることはあまりありません。
時々,休業損害の支払いなどで,被害者の過失分を控除して支払ってくるような保険会社もありますが,どちらかといえば,このようなケースは少ないように思います。
一方,被害者の代理人としては,被害者がどの程度過失があるのかは重要なことになりますので,事前に刑事記録を入手して,被害者にどの程度の過失が見込まれるかを確認するようにしています。
もちろん,事前に刑事記録を確認するのは,保険会社との交渉のために事前にどの程度の過失割合になるのか知っておくためですが,事前にどの程度の過失割合になるかを確認することで,被害者の方にどの程度の賠償金になるのかという見込みを説明することができるというメリットもあります。
こちらは事前に刑事記録を確認して被害者と加害者の過失割合の想定をしていますが,もちろん,賠償金を請求するときにこちらから過失割合を示して過失相殺をして請求するということはありません。
なぜならば,保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがあるからです。
過失割合の判断には刑事記録が重要
過失割合の判断には刑事記録が重要です。
刑事記録とは,主に交通事故の状況を記録した実況見分調書のことを指します。
事故の状況を記録した実況見分調書以外にも加害車両の状態を記録した実況見分調書や照射実験の結果を記録した実況見分調書などがありますが,事故の状況を記録した実況見分調書が最も重要な刑事記録になります。
刑事記録の中には,このような客観的な事実を記録したもの以外に,事故の当事者や目撃者の供述を調書にした供述調書という記録もあります。
ところが,この供述調書は刑事事件で正式裁判にならず不起訴処分になると開示されないことが多いです。
事故の状況を記録した実況見分調書と当事者の供述調書を照らし合わせて,正確な事故の状況が分かるということもあるので,供述調書も開示して欲しいのですが,刑事記録を保管・管理している検察庁が不起訴の場合はプライバシー侵害のおそれがあるとして供述調書を開示しない方針をとっているのでやむを得ません。
ただし,裁判になれば,供述調書を開示する方法もあるのですが,これはまた別の機会に書きたいと思います。
とにかく,過失割合の判断には刑事記録が重要ということは認識しておきましょう。
保険会社は刑事記録を取得していないこともある
過失割合の判断には刑事記録が重要なので,当然,保険会社も刑事記録を取得していると思うかもしれませんが,実際のところ,保険会社は全ての交通事故で刑事記録を取得しているわけではないようです。
刑事記録は,先ほど検察庁が供述調書を開示しない理由でも書きましたが,プライバシーにかかわる記録です。
そのため,保険会社とはいえ,交通事故の当事者でない者が刑事記録を簡単に入手することはできません。
そうすると,保険会社が刑事記録を入手するためには弁護士に依頼をする必要があります。もちろん,弁護士も無料では依頼を受けませんし,刑事記録の開示を求めるにもそれなりの実費が必要になります。
つまり,1件の交通事故の刑事記録を取得するだけでも保険会社にとってはそれなりのコストが発生するということになります。
保険会社が扱っている交通事故は膨大な件数ですので,そのすべてで刑事記録を取得していたらそのコストだけでかなりの金額になってしまいます。
そのため,保険会社は事故の状況を確認しなければならない事故の時だけ刑事記録を取得しており,すべての事故で刑事記録を取得しているわけではありません。
特に,軽度な事案ではほとんどのケースで刑事記録を取得していないように思います。
刑事記録を取得していないと,当然,こちらは知っているが保険会社は知らないという事実が出てきます。
以前あったのは,自転車が交差点を横断中にトラックに衝突されたという事故で、衝突時の信号は自転車が青でトラックが赤だったのですが,自転車が横断を開始した時の信号の色は赤で横断途中で青に変わり,その後にトラックと衝突したという事故がありました。
トラックの運転手はナビを見て運転をしていたため,当然,自転車が青信号になる前に横断を開始したという事実は知りません。
刑事記録は,自転車の運転手の供述に基づいて記録されていたのです。
保険会社は,トラックの運転手の話しか聞いていませんでしたので,当然,100%トラックの運転手の責任で,自転車の運転手には過失はないと考え,過失相殺をせずに賠償金の提示をしてきたということがありました。
自転車が横断を開始した時の信号が赤で,トラックが交差点に進入した時の信号が青で,その後,信号が変わり衝突したという場合には,多少過失割合が違ってきてもおかしくないという事案です。
しかし,保険会社は,刑事記録を取得していなかったため,被害者の過失を0で解決することができました。
一方で,被害者の過失を下げるような事実が刑事記録を見て初めて分かるというケースもあります。
その場合は,こちらから刑事記録を保険会社に送って,被害者の有利に過失割合を変更することが可能です。
刑事記録は,事故の当事者であれば検察庁で取得することが可能ですが,結構手間がかかりますので弁護士に依頼して取得した方がいいと思います。
解決実績
30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
関連記事
示談書(承諾書,免責証書)は定型文になっている
交通事故の賠償を示談で解決する場合,保険会社と示談書(承諾書,免責証書と言ったりもします)を交わすことになります。
示談書は大抵保険会社が作成した定型書式を利用しますので,示談の内容は定型文になっています。
どこの保険会社も
①示談書に明記された賠償金を受領したらその他の損害賠償請求権を放棄する
②今後,裁判上,裁判外において一切の異議を申し立てない
ということが記載されています。
このような内容にすることで,後から被害者が本当だったらもっと賠償金がもらえたことに気が付いて,あらためて保険会社に請求をしたり裁判を起こしたりしても,被害者の請求が認められないようになっています。
そのため,任意保険会社の基準で計算した慰謝料や賠償金で示談してしまった場合,後から弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金の方がはるかに高額だということが分かったとしても,再度,弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金で保険会社に請求することはできません。
このような事態を避けるためには,保険会社から賠償金の提示をもらったときに,交通事故を専門とする弁護士に相談することが必要です。
「敵(損保会社)は味方のふりをする」でも書きましたが,どんなにいい担当者でも,弁護士が介入していない段階で弁護士基準で計算した賠償金を提示してくる担当者は絶対にいません。
示談書にサインする前に気を付けた方がいいこと
弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がいくらなのか確認すること
しつこいかもしれませんが,示談書にサインをする前に弁護士に相談をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がどれくらいになるのかを確認するように気を付けましょう。
これは絶対に気を付けなければならないことと言っても過言ではありません。
例えば、交通事故で多いむち打ち症で6ヶ月通院した場合には、被害者に過失がなければ、通院に対する慰謝料は弁護士基準で計算する約90万円になります。
しかし、任意保険が計算する通院に対する慰謝料は高くても50万円から60万円程度です。
酷いときには、自賠責基準で計算して20万円から30万円程度しか提示してこないということもあります。
必ず弁護士基準で計算したい慰謝料どれくらいの金額になるのかは確認しましょう!以下のリンク先で交通事故の慰謝料の計算・相場について解説していますので参考にして下さい。
示談書に症状が悪化して後遺障害等級が上がったことを想定した文言を追加すること
また,なんとか自分で交渉をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金になったとしても示談書にサインをする前に気を付けておいた方がいいことがあります。
それは,すべての事案で気を付けた方がいいというわけではないのですが,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合です。
例えば,股関節付近の骨折後に股関節に健側の2分の1以下の可動域制限が残って後遺障害等級10級が認定され,さらに将来的に股関節に人工関節を入れる可能性があるような場合です。
将来,実際に股関節に人工関節を入れて可動域が健側の2分の1以下になった場合には,後遺障害等級が10級から8級に上がります。
このような場合には,被害者としては,人工関節にした際に必要となった手術代(治療費),通院交通費,入院雑費,入通院慰謝料(傷害慰謝料),等級に応じた後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求したいと思うはずです。
このような場合,示談書に何も追加で書かなかったとしても,裁判にすれば後遺障害等級8級になったことによって発生した賠償金を請求することはできます。
しかし,示談では,最初の示談書を盾にとって,保険会社が一切の交渉に応じないという可能性もあります。
そこで,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合には,以下のような文言を示談書に追加して欲しいと保険会社に言った方がいいと思います。
「ただし,症状が悪化して現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,別途協議する。」
このような文言を示談書に入れておけば,現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,保険会社は示談交渉に応じざるを得ない状況になります。
保険会社も,後遺障害等級が上がった時には裁判にされるよりは示談で終わらした方が得策ですので,このような内容の文言を追記することを拒否することはありません。
実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいい?
では,実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいいのでしょうか?
この場合,通常の後遺障害の被害者請求と同じことをすることになります。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい自賠責に対して後遺障害の被害者請求をします。
症状の悪化が交通事故から時間が経っていても,時効の起算日は新たに作成した症状固定日になりますので,時効の心配はありません。
注意が必要なのは自賠責用の診断書(後遺障害診断書ではなく毎月病院が治療費を保険会社に対して請求する際に作成している診断書です)の作成を病院に依頼することです。
一度示談している以上,保険会社が病院に直接治療費を支払うことがないので,手術等の治療費については,一度,被害者の方が健康保険を利用して自己負担することになります。
そうすると,被害者の方から病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しないと,病院は自賠責用の診断書を作成してくれません。
自賠責に後遺障害の被害者請求をするときには自賠責用の診断書が必要になりますので,被害者の方が病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しておく必要があります。
それと,領収書もしっかりと保管しておきましょう。多くの方が示談している以上保険会社にこれ以上賠償金の請求することはできないと考えてしまい,領収書を捨ててしまっていることが多くあります。
示談書にサインをする前に弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談しよう!
示談書にサインするということは、損保会社の提示する慰謝料や賠償金にそれなりに納得したからだと思います。
しかし、その金額は、もしかしたら弁護士基準で計算をすれば、慰謝料も賠償金ももっと高い金額になるかもしれません。
実際に慰謝料や賠償金がいくらになるのかは、後遺障害の有無、被害者の過失の有無、被害者の年収などによって変わってきますので、自分で判断しようと思ってなかなか簡単ではありません。
やはり、示談書にサインする前に交通事故を専門としている弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談した方が納得いく解決ができると思います。
交通事故を専門としている弁護士や交通事故に強い弁護士の探し方は以下の記事を参考にして下さい。
関連記事
交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)
交通事故に強い弁護士が弁護士に依頼するための弁護士費用特約の使い方を解説!
残りの賠償金は慰謝料だけではないですよ!
ヤフーの検索エンジンに「交通事故」と入力すると,最上位の第2検索ワードが「慰謝料」となっています。実際に,交通事故に関係するキーワードで「交通事故 慰謝料」の検索ボリュームはかなり大きいようです。
ここでふと思ったことが,「交通事故」の最上位の第2検索ワードが,なぜ「賠償金」じゃないのだろうかってことです。弁護士の感覚ですと,交通事故の最上位の第2検索ワードは「慰謝料」よりも「賠償金」の方がしっくりきます。
「慰謝料」は,交通事故の賠償実務では,入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料がありますが,あくまでも賠償金を構成する損害項目の1つに過ぎません。交通事故の被害に遭ったら,慰謝料がいくらになるのか,ということ以上に,賠償金が総額でいくらになるのかということの方が気になります。
ここで再びふと思ったのですが,もしかしたら交通事故の被害に遭った人の多くが,治療費や休業損害などは保険会社からすでに支払ってもらったので,残りの賠償金は慰謝料だ!と考えて,「交通事故 慰謝料」と検索しているのかもしれないということです。
確かに,交通事故の相談を受けていると「私の場合,慰謝料はいくらになりますか」と聞かれることが度々あります。この相談者の方が,慰謝料以外に損害項目があることを理解して質問しているとは思えなかったので,「慰謝料以外にも賠償金はもらえますよ」と答えると,大抵,「えっ」という反応をされます。
このような反応をされる方は,治療費や休業損害などはすでに保険会社から支払われているので,残りの賠償金は慰謝料しかないと考えている方ばかりでした。
念のために言っておきますが,治療費や休業損害などが支払われていても,残りの賠償金は慰謝料だけではありません。
慰謝料も重要ですが逸失利益も重要ですよ!
治療費や休業損害などが支払われていた場合,残りの賠償金は,慰謝料と逸失利益です。もちろん,慰謝料も重要ですが,逸失利益はもっと重要です。
慰謝料は入通院期間や後遺障害等級によって決まってきますので,同じ入通院期間や後遺障害等級であれば,慰謝料の金額は同じになります。
一方,逸失利益は,同じ後遺障害等級であっても,収入と年齢によって金額が大きく変わってきます。収入が高く,年齢が若ければ,逸失利益は慰謝料よりも高額になることが多くあります。
例えば,年収1000万円で40歳の男性と年収500万円で50歳の男性で,いずれも後遺障害等級が9級の場合に,逸失利益がどれくらいの金額になるか確認してみましょう。
ちなみに,後遺障害9級の後遺障害慰謝料は弁護士基準で690万円で,40歳の方も50歳の方も違いはありません。
まず,年収1000万円で40歳の方の逸失利益は以下のとおりの金額となります。
1000万円×35%×14.6430=5125万500円
次に,年収500万円で50歳の方の逸失利益は以下のとおりの金額になります。
500万円×35%×11.2741=1972万9675円
いずれのケースでも後遺障害9級の後遺障害慰謝料690万円を大きく上回っています。
また,年収1000万円の40歳男性の逸失利益は,年収500万円の50歳男性に比べると,3000万円以上も高額です。後遺障害等級が同じでも,収入が高く,年齢が若いほど逸失利益が高額になるということをお分かりいただけたと思います。
保険会社は慰謝料もそうだけど逸失利益をもっと低く提示してくる
保険会社は,慰謝料も逸失利益も弁護士基準を大きく下回る金額で提示してきますが,保険会社としては,逸失利益を低い金額で抑えられた方が会社の利益になります。
そうすると,逸失利益は低い金額のまま据え置きで,慰謝料を増額して被害者の方を納得させて示談させるということが多くあります。
被害者の方としては,慰謝料ばかりに目を向けず逸失利益が弁護士基準で計算された金額になっているかということも確認する必要があります。
逸失利益は、基本的には事故前年の年収を基準にして計算しますが、事故当時20代の被害者の場合には、賃金センサスを基準に計算することもあります。被害者の属性によって計算方法に違いがあるので弁護士に相談することをお勧めします。
関連記事
交通事故に強い弁護士が会社員の死亡事故の逸失利益のについて解説!
交通事故に強い弁護士が主婦が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算について解説!
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。