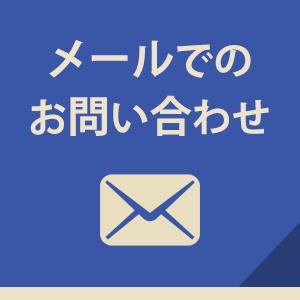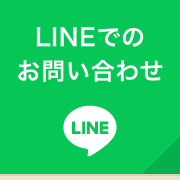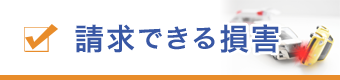横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》 - Part 2
減収が認められない被害者の方でも逸失利益が認められた裁判所和解案で解決することができました。詳しくは解決実績をご覧ください。
年末は酔っぱらって道路に寝ている人が車に轢かれる交通事故が多くなる
年末になると職場の忘年会などでお酒を飲む機会が多くなります。ほどほどに飲むのであればいいですが,飲みすぎてしまうと終電で乗り過ごしてしまって無駄なタクシー代を使ったり,帰れなくてホテルに泊まったりすることもあるので,お酒の飲みすぎには気を付けたいですね。
タクシーを使ったり,ホテルに泊まったりして無駄なお金を使ってしまっただけなら笑い話になりますが,酔っぱらって道路に寝てしまって車に轢かれてお金よりも大事な体や命を失ってしまったら笑えません。
でも,年末になると酔っぱらって道路に寝てしまって,車に轢かれてしまい大怪我をしたり,命を落としてしまう人が多くいらっしゃいます。
先ほど見ていたニュースでも忘年会の帰りに酔っぱらって道路に寝てしまい車に轢かれて亡くなってしまったというニュースが流れていました。
当然,こんなことで亡くなってしまったご本人もやるせないですが,ご家族はもっとやるせない気持ちになるので,酔っぱらって道路に寝てしまうことだけは絶対に止めましょう。
酔っぱらって道路に寝ていた人を轢いてしまった運転手にも民事上の責任は認められます!
酔っぱらって道路に寝ていた人を轢いてしまった運転手の責任はどうなるのでしょうか?
酔っぱらって寝ていた方が悪いのだから運転手が刑罰に問われることはないのでしょうか?
また,民事上も酔っぱらって寝ていた方が悪いのだから運転手が賠償責任を負うことはないのでしょうか?
酔っぱらって寝ている人を見落として轢いてしまった運転手にも過失がありますので,刑事では過失運転致死傷罪の責任が問われる可能性があります(もっとも被害者の過失も大きいので,罰金や不起訴処分で終わる可能性が高いと思いますが)。
一方,民事では,やはり運転手にも過失がありますので,事故の責任が認められ賠償責任を負うことになります。
ちなみに,人身事故の場合,自動車損害賠償保障法(自賠法)3条で,運行供用者(運転手や自動車の所有者など)が自動車の運転によって他人の生命,身体に損害を負わせた場合,原則として,運行供用者が事故の責任を負うとされています。
そのため、よほどのことがない限り,酔っぱらっている人を轢いた運転手の民事上の責任が否定されることはありません。
酔っぱらって道路に寝て事故に遭って死亡しても自賠責3000万円以上の賠償金がみとめられる可能性があります!
酔っぱらって道路に寝ていたところ轢かれて死亡してしまった場合でも賠償金はもらえるのですが,保険会社からは3000万円以下の金額しか提示されないこと多くあります。
3000万円という金額は,死亡事故で自賠責保険から支払われる限度額です。
つまり,保険会社は,自賠責保険の限度額までの提示しかしていないので,自社の負担なく賠償金を支払ったことにできます。
ひどい保険会社や共済だと,自賠責保険の請求書だけ送ってきておしまいにするようなところもあります。
死亡した被害者の家族も「酔っぱらって寝ていたオヤジが悪いんだし」なんて考えて,保険会社の提示する金額で示談してしまうということが多くあるようです。
確かに,酔っぱらって寝ていたお父さん(お父さんとは限りませんが…)に悪いところもあったかもしれませんが,よく考えてみてください。
酔っぱらって寝ていた人はあくまでも歩行者です。
ここで思い出してもらいたいのは,歩行者と自動車の交通事故の場合,基本的には自動車の方が責任は大きいということです。
あまりないかもしれませんが,酔っぱらって日中に道路に寝ていて自動車に轢かれてしまった場合,歩行者の過失は30%で,運転手の過失は70%になります。
夜間の場合であっても,歩行者の過失も運転手の過失も50%です。
仮に夜間に酔っぱらって道路に寝ていたところを轢かれて死亡してしまったとして,被害者の損害額の総額が8000万円であったというケースで見てみましょう。
賠償金は単純計算で8000万円×50%=4000万円になります。
そうすると,死亡事故の自賠責保険の限度額である3000万円よりも1000万円ほど高くなります。
それにもかかわらず,保険会社が提示した3000万円の賠償金で示談してしまった場合,1000万円も損することになってしまいます。
死亡事故の場合,仕事をしていた方であれば,損害額は7000万円から9000万円程度になることが多いので,酔っぱらって道路に寝ていたところを轢かれて死亡してしまったという交通事故の場合でも,過失相殺をされたとしても自賠責保険の限度額である3000万円以上の賠償金を得られるというケースが多くあります。
このような事故でも,「酔っぱらって寝ていたオヤジが悪いんだし」なんて考えずに(お父さんとは限りませんが…),弁護士に相談をしてみてください。
ちなみに,もし,被害者が自動車保険に入っていた場合には,過失相殺によって減額された被害者の過失分も保険金として請求できる場合があるので,交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
クロノス総合法律事務所では被害者の過失が大きい交通事故の相談も受け付けておりますのでお問い合わせください。
まとめ
それでは,酔っぱらって道路に寝ていたところ轢かれてしまったという交通事故についてまとめます。
①運転手は刑事上も民事上も責任を負う可能性がある(民事の場合は自賠法3条があるのでほとんどのケースで賠償責任を負います)
②酔っぱらって道路に寝ていたところ轢かれてしまった被害者でも賠償金はもらえる
③被害者の過失は夜間の道路に寝ていた場合でも50%程度
④賠償金は自賠責保険金の限度額3000万円以上になる可能性が高い
ご参考にしていただければと思います。
解決実績
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
関連記事
交通事故に強い弁護士が保険会社と交渉にも負けない死亡事故で知っていくべき知識を解説!
交通事故に強い弁護士が会社員の死亡事故の逸失利益のについて解説!
横浜で発生した神奈中バスの交通事故
10月28日夜,横浜市西区桜木町で神奈川中央交通の路線バス(神奈中バス)が乗用車に追突し,さらにその乗用車が別の路線バスに追突するという事故が発生しました。男子高校生1名が死亡し,そのほか6人が重軽傷を負ったそうです。
私も横浜市内の高校に通学していたときに神奈川中央交通の路線バスを利用していたので,ひとごととは思えませんでした。突然の交通事故でご子息を失ったご両親の気持ちを考えると非常に痛ましい気持ちになります。ましてや安全運転を第一とすべき公共交通機関である路線バスに乗車中の交通事故で亡くなってしまったとなるとなおさらです。
ニュースでは事故直前に神奈中バスの運転手が意識を失いバスが柱に衝突したと報道されていましたので,運転手に身体的な異常が発生した可能性が高いと思われますが,運転手は過失運転致死傷罪で逮捕されました。被害者が死亡し,けが人も複数となると逮捕は当然といえるでしょう。
刑事裁判になる可能性が高い
運転手の逮捕容疑である過失運転致死傷罪は故意の犯罪ではなく過失の犯罪であるため,一般的には不起訴処分や重くても罰金刑の処分で終わってしまうことが多いのですが,今回の事故は亡くなった高校生を含めて被害者が7名もいますので,法廷で行われる正式裁判となる可能性が高いと思われます。
以前は交通事故の刑事処分というと,被害者にも多少の過失があって発生した死亡事故であったりすると,執行猶予付きの有罪判決であったり,罰金,不起訴処分という結果になることも多くあったかと思いますが,最近では,今回のように被害者が死亡してしまったような交通事故の場合,正式裁判となり,判決も執行猶予のつかない実刑判決になることが多くなっていると思います。
最近,私が被害者側の代理人として参加した死亡交通事故の刑事裁判でも執行猶予のつかない実刑判決になりました。
おそらく,裁判所では,近年飲酒運転やあおり運転などで死亡事故が引き起こされていることに鑑みて,死傷者が出ている交通事故について厳罰にする傾向にあるのだと思います。
被害者遺族も死亡交通事故の刑事裁判に参加することができる
先ほど,私が被害者側の代理人で死亡交通事故の刑事裁判に参加したという話をしましたが,過失運転致死傷罪の場合,被害者や被害者遺族も刑事裁判に参加することができます。これを被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33)といいます。
被害者参加制度は全ての刑事裁判で認められるものではなく,殺人罪などの故意の犯罪行為により人を死傷させた事件や今回の交通事故のように人が死傷したような重大な事件で認められる制度です。
今回の交通事故でも刑事裁判になれば,被害者や被害者のご遺族は被害者参加制度を利用して運転手の裁判に参加することができます。
被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加すると,被害者や被害者のご遺族は以下のことを行うことができます。
①公判期日に出席すること
②検察官の権限行使に意見を述べること
③情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について証人を尋問すること
④意見を述べるために必要と認められる場合に被告人に質問すること
⑤事実又は法律の適用について意見を述べること
⑥心情等に関する意見を述べること
なかなか被害者や被害者のご遺族が自分たちだけで法廷に立って上記のことを行うのは難しいので,代理人となる弁護士を立てて被害者参加することが多いと思います。おそらく,裁判所や検察官も被害者や被害者のご遺族と直接やり取りをするよりは,代理人となった弁護士を通じてやり取りする方がやりやすいのではないかと思います。
弁護士を立てる費用は,弁護士によって異なると思いますが,場合によっては被害者参加人のための国選弁護制度を利用して法テラスの援助を受けることが可能です。なお,当事務所では,交通事故の賠償請求のご依頼をいただいた場合には費用をいただかずに被害者参加人の代理人としての活動を行っています。
死亡交通事故において被害者参加制度を利用する意義
裁判官は,基本的には過去の同じような事故(過失の内容,死傷した被害者の数など)でどのような判決が出されていたかという点を考慮して判決を下すことが多いので,被害者参加制度を利用したからといって,劇的に判決の内容が重くなるということはありません。
しかし,裁判官は被害者や被害者遺族の処罰感情や被害感情を十分に考慮しますので,必ず被害者参加制度を利用し刑事裁判に参加して,被告人に対する処罰感情や家族を失った悲しみが続いているといった被害感情を裁判官に伝えることが重要だと思います。
また,私がこれまでに担当した被害者参加では,刑事裁判で意見を述べることで,被害者や被害者遺族の気持ちが多少でも違ったものになるということもあったように感じます。
やはり,被害者や被害者遺族が外に置かれて刑事裁判が行われるよりも,裁判の当事者として裁判に参加した方が気持ちの面で大きな違いがあるのではないかと思います。
交通事故でフロントガラスが顔面に突き刺さった影響で女優を引退
先日,山の日で休日だったので久々にゴールデンタイムにテレビを見ていたところ,TBSの「爆報!THEフライデー」という番組で,岡寛恵さんという女優さんのことが取り上げられていました。
「爆報!THEフライデー」によると,女優の岡寛恵さんは,14歳の時に大林宣彦監督の「時をかける少女」で主演の原田知世さんの妹役を演じるなど,若いうちから女優として実績を残された方だったようです。
ところが,19歳の時に,対向車線を走っていた自動車が,岡寛恵さんが乗っていた自動車に衝突するという交通事故に遭い,その際に,岡寛恵さんは,フロントガラスに顔面を強打し,割れたフロントガラスが顔面に突き刺さり,顔面に無数の傷跡が残る怪我を負ったそうです。顔面の傷跡は20か所以上で,治療をしても傷跡が残ってしまったために,女優生命を絶たれ,19歳で女優を引退しなければならなくなったそうです。
ただ,現在は,顔面形成外科手術を受けて傷跡はほとんど消えて,女優や声優さんとして復帰されているそうです。
女優の外貌醜状の後遺障害
女優さんにとって顔に傷を負うというのは,職業的には致命傷といっていいと思います。ところが,自賠責では,職業的な違いを考慮することなく,決まった条件によって後遺障害の認定をすることになりますので,女優さんだからといって外貌醜状の後遺障害で1級になるというようなことはありません。
女優さんであっても,醜状の程度によって以下の7級から12級の後遺障害が認定されることになります。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 | 醜状の程度 |
|---|---|---|
| 後遺障害7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの | ①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 ②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 ③頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕 ①から③が人目につく程度以上のもの |
| 後遺障害9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの |
| 後遺障害12級 | 外貌に醜状を残すもの | ①頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 ②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線条痕 ③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕 |
岡寛恵さんの場合,顔面の傷跡が20か所以上ということだったので,この場合には,おそらく7級の後遺障害が認定されることになると思います。
女優の外貌醜状の逸失利益
外貌醜状は,後遺障害による逸失利益が認められるかということが問題となります。
外貌に醜状が残っても,労働能力が低下したわけではないから,後遺障害による逸失利益は認められないのではないかという問題意識です。
しかし,顔面に傷跡が残れば人前に出るような仕事や人と対面するような仕事の場合,労働能力に影響があることは間違いありません。ましてや,岡寛恵さんの場合は女優としての仕事ができなくなってしまったのですから外貌醜状による逸失利益が認められることは間違いありません。
後遺障害による逸失利益は
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という計算式で計算をすることになるので,以下では,岡寛恵さんの交通事故で,労働能力喪失率,基礎収入,労働能力喪失期間がどのように判断されることになるのか考えてみたいと思います。
労働能力喪失率
通常,労働能力喪失率は,後遺障害等級ごとに決まっていて,例えば,7級の後遺障害であれば56%と定められています。
ところが,外貌醜状の後遺障害の場合,先ほど説明したように労働能力が低下したかどうかが問題になるので,逸失利益が認められる場合でも,後遺障害等級ごとに定められている通常の労働能力喪失率よりも下げられることが多くあります。
では,女優さんに外貌醜状が残った場合も同じように労働能力喪失率は下げられてしまうのでしょうか?
岡寛恵さんの場合,実際に女優として活躍し実績があったので,この事実はかなり重視する必要があると思います。
おそらく,実績のない女優さんの場合には,労働能力喪失期間のうち最初の10年くらいを等級どおりの労働能力喪失率として,それ以降を一定程度下げた労働能力喪失率を認定する可能性が高いと思います。
しかし,実績のある女優さんの場合,外貌醜状がなければ長い期間女優として活躍した可能性が高いので,労働能力の喪失の程度は大きいと評価されるように思います。
そうすると,岡寛恵さんの場合は,外貌醜状の後遺障害であったとしても,後遺障害等級どおりの労働能力喪失率が認められる可能性が高いのではないかと思います。
基礎収入
基礎収入は,基本的には事故前年の年収を基準とします。被害者の年齢が30歳未満の場合には,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることもあります。
当時の19歳の女優さんの年収がどの程度の金額なのかは知りませんが,おそらく,高卒で一般的な仕事に就いた女性と比べると高い収入を得ていた可能性が高いと思います。
そうすると,基本的には,賃金センサスを使わずに事故前年の年収を基礎収入とする可能性が高いと思います。
ただし,女優さんのように毎年仕事によって収入が変わる仕事は,保険会社側から,就労可能年齢の67歳まで同じ年収が続く可能性は低いと反論されることがあります。
賃金センサスの平均賃金よりもはるかに高額な年収だった場合には,このような反論が認められる可能性もありますが,賃金センサスの平均賃金よりも100万円から200万円高い程度であれば,おそらく事故前年の年収を基礎収入とすることになるのではないかと思います。
可能性としては低いように思いますが,もし,事故前年の年収が賃金センサスの平均賃金よりも低い場合には,19歳と若年者であることから,賃金センサスの平均賃金が基礎収入となります。
労働能力喪失期間
通常,労働能力喪失期間は,症状固定時の年齢から67歳までの期間とします。仮に,症状固定時の年齢が事故から1年後の20歳であったのであれば,労働能力喪失期間は47年となります。
ところが,外貌醜状の後遺障害の場合,労働能力喪失率を下げ,さらに,労働能力喪失期間まで短くするという判断をされることがあります。
特に,主婦に外貌醜状の後遺障害が残ったようなケースでは,労働能力喪失率,労働能力喪失期間ともに通常のケースを下回るような内容になることが多くあります。
女優さんの場合,ほかの仕事に比べて,外貌醜状による労働能力喪失の程度が大きいことは間違いありませんし,定年のない仕事ですので,実績のある女優さんであれば,長い期間女優として仕事をすることになると思います。このような事情を考慮すれば,外貌醜状であっても,女優さんの場合には労働能力喪失期間は,就労可能年齢の67歳まで認められる可能性が高いのではないかと思います。
まとめ
外貌醜状の場合,後遺障害による逸失利益は必ずといっていいくらい争点になります。仕事が女優さんであれば尚更だと思います。
外貌醜状で後遺障害による逸失利益が認められるためには,外貌醜状により仕事上どのような影響が出る可能性があるのかということを詳しく主張する必要があります。仕事上どのような影響が出るかをしっかりと主張できなければ,外貌醜状の後遺障害による逸失利益は否定されてしまいますので,外貌醜状で保険会社から後遺障害による逸失利益を否定されている場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、正式には「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的として、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を行うADR機関です。
法律相談、和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。和解あっせんの進め方は、担当弁護士によっても異なるのですが、ほとんどの担当弁護士は、被害者と加害者側の保険会社もしくは共済組合の担当者からそれぞれの話を聞いて、基本的には弁護士基準で計算した賠償金で和解を勧めることが多いです。
交通事故紛争処理センターでの解決は以下のようなメリットがあります。詳細については,「交通事故紛争処理センターってどんなところ」をご確認ください。
1 無料で利用できる!
2 迅速に解決することができる!
3 審査会の判断に保険会社及び共済組合は拘束される(保険会社及び共済は裁判にできない)
交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケース
交通事故紛争処理センターには以上のようなメリットがあるため,被害者にとって利用しやすいものではあるのですが,事案によっては交通事故紛争処理センターへの申立てをすることで解決までに時間がかかってしまい,最初から裁判にすればよかったという事案もありました。
ここでは,自分の反省も意味も含めて,交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケースを省みたいと思います。
高齢者の高次脳機能障害のケース
高次脳機能障害は,記憶障害など認知機能に障害が出ることが多いのですが,その症状は,老人性痴呆症の症状と似ています。
そのため,高齢者の場合,軽度の脳外傷しかなかったようなときには,高次脳機能障害による症状なのか老人性痴呆症による症状なのかはっきりと区別がつかないということがあります。
重度の脳外傷を負ってしまったようなケースであれば,もともと痴呆症であったというような事情がない限り,記憶障害などの症状が出現していたら,それは高次脳機能障害による症状と判断されると思います。
しかし、軽度の脳外傷しか負っていない場合,保険会社から高次脳機能障害ではなく単なる痴呆症であると争われることがあります。
私が担当した事案でも,交通事故紛争処理センターで保険会社から高次脳機能障害ではなく,単なる痴呆症だとして高次脳機能障害の存在を争われたということがありました。
ただ,この事案は,脳外傷が重度で,意識障害も長く続いており,しかも,後遺障害等級は5級とわりと重度であったため,保険会社が争ってきても簡単に排斥することができました。
失敗だったのは,交通事故紛争処理センターから高齢であるから被害者に成年後見人を付けて欲しいと言われたことでした。
成年後見人とは,代表的なのは,痴呆症などで意思能力を欠くこととなった高齢者について,その高齢者に代わって財産管理したり,高齢者の身上監護をする人間を裁判所が選任するという制度です。
高齢者だけでなく,若くして遷延性意識障害などになってしまい自分で意思表示ができなくなってしまったような場合にも成年後見人が選任されます。
意思能力がない当事者が行った示談は無効となりますので,意思能力がない当事者が示談をするためには,必ず成年後見人が必要となります。
確かに,高次脳機能障害の被害者の裁判で,裁判を提起する際に成年後見人を付ける必要があるケースというのはありますが,1級から3級くらいの高次脳機能障害の事案で,5級の高次脳機能障害の事案で成年後見人を付けるということはあまり多くないのではないかと思います。
交通事故紛争処理センターでも裁判と同じように,意思能力がないと思われるような1級から3級くらいの重度の高次脳機能障害の事案では成年後見人が必要になることもあると思います。
しかし、まさか5級の高次脳機能障害で成年後見人を付けてくれと言われるとは,申立て段階では全く予想がつきませんでした。
交通事故紛争処理センターの担当弁護士が言うには,以前,高齢者の5級の高次脳機能障害の事案で成年後見人を付けずに示談をしたところ,親族が無効を主張してきたというケースがあったそうです。
そのため,今回も念のために成年後見人を付けて欲しいということでした。
成年後見人は,裁判所に申立てが必要になりますので,実際に,成年後見人が選任されるまで時間がかかります。また,費用も掛かります。
時間や費用をかけたくないと思い,交通事故紛争処理センターに申立てをしたのに,時間も費用も掛かってしまうのであれば,最初から裁判での解決を目指せばよかったというケースでした。
示談交渉段階で争っていなかった事実について争われたケース
交通事故紛争処理センターでの解決に向ている事案というのは,単純に金額だけに争いがあるような事案です。
後遺障害が争われていたり,過失割合が争われているような事案は,交通事故紛争処理センターでも解決までに時間がかかってしまうので,あまり交通事故紛争処理センターでの解決には向きません。
そのため,示談交渉段階で後遺障害や過失割合が争われているような場合には,交通事故紛争処理センターでの解決ではなく,裁判での解決を目指します。
そうすると,交通事故紛争処理センターへ申し立てる事案というのは,当然,示談交渉段階で後遺障害も過失割合も争われていないような事案ということになります。
ところが,示談交渉段階では,保険会社は後遺障害も過失割合も争っていなかったのに,交通事故紛争処理センターへ申立てをしたら争ってきたということがあります。
もちろん,交通事故紛争処理センターで示談交渉段階での主張と違う主張をしてもかまわないので,こちらの読みが甘かったということになるのですが,保険会社が後遺障害や過失割合を争ってきても,自賠責で認定された後遺障害が否定されることはほぼないですし,過失割合にしても,最終的には刑事記録で分かる限りの事実をもとに決定されるので,争ってもあまり意味がないというケースがほとんどです。
保険会社が争ってきたらこちらもそれなりの主張をしなければなりませんので,結局,解決までに時間がかかってしまうということになります。
これについては,失敗というよりも申立てをしてみないと保険会社がどのような主張をしてくるか分からないので,やむを得ない面もあります。
治療費を人身傷害補償保険で支払ってもらっていたケース
これは,完全に私が経験不足で失敗をしたという事案です。
通常,交通事故に遭うと,治療費は加害者側の保険会社が支払います。
ところが,ときどき被害者側の保険会社が人身傷害補償保険で治療費を支払っているというケースがあります。
被害者に,なんで治療費を人身傷害補償保険から支払ってもらっていたのか,と確認をしたところ,加害者側の保険会社の担当者が気に入らなかったからというのです。
当時は,弁護士になって2年目か3年目のときだったので,そんなこともあるのかなと思って,特に気にしませんでした。
ところが,治療費を人身傷害補償保険から支払っているケースというのは,大抵,加害者側の保険会社が何らかの理由で治療費の支払いを拒んでいるというケースです。
そのケースでは,事故が軽度だから大した怪我をしていないという理由で,加害者側の保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切ったという事情がありました。
このような場合,当然,加害者側の保険会社は,治療の必要性,症状固定日,後遺障害などすべて争ってきますので,交通事故紛争処理センターでの解決には向きません。
結局,このケースは,あっ旋では示談できず審査会まで行き,申立てから審査会の裁決がでるまで1年以上かかってしまいました。
埼玉相談室で取下げた事案を新宿本部で再度申立てたケース
一度,被害者が自分で交通事故紛争処理センターの埼玉相談室で申立てをして,あっせん案に納得がいかないために取下げをした後に,こちらに相談に来たという事案でした。
交通事故紛争処理センターは,申立てを取り下げると,同じ事案については,再度,交通事故紛争処理センターへの申立てはできないという規約になっています。
このような規約になっていることは分かっていたのですが,埼玉相談室で申立てをしていたことは新宿本部にはわからないだろうと安易に考え,同じ事案を新宿本部に申し立てることにしました。
そうしたところ,交通事故紛争処理センターから何も言われずに第1回期日を向かえたので,やはり,埼玉相談室のことは新宿本部では分からないんだなとほくそ笑んでいたのですが,第2回期日の前に,交通事故紛争処理センターの担当者から,この事案が埼玉相談室に申し立てられていたことを知ってましたかという連絡があり,結局,規約に従って新宿本部ではこれ以上話し合いは続けられないということになってしまいました。
まあ,埼玉相談室のことは新宿本部では分からないだろうと安易に考えてしまった私が悪いのですが,できれば申し立てたときに確認をしていただいて,第1回期日前に教えて欲しかったなと思います。
もちろん,一番悪いのは私ということは分かってますよ…
交通事故紛争処理センターで解決する場合には弁護士に依頼しよう
時々、被害者が自分で交通事故紛争処理センターに申立てをしたけれども、うまく進められないので途中から交通事故紛争処理センターでの話し合いに入ってもらえないかという相談があります。
相談者の方に聞くと、どうやら保険会社が慰謝料を争っており、交通事故紛争処理センターの斡旋担当弁護士も弁護士基準を下回る慰謝料の提案を慰謝料を提案しているというのです。
まあ、入通院慰謝料だったので、弁護士基準と多少の誤差はあっても通常は弁護士基準から大きく金額がずれることはないのですが、確かに通院期間からすると、弁護士基準の慰謝料をかなり下回っていました。
そんなことあるのかなと思いましたが、途中から交通事故紛争処理センターでの話し合いに参加したのですが、斡旋担当弁護士は、弁護士が入っていない場合は、弁護士基準以下で慰謝料を提案することもあるんだということを言っていました。
本当かどうかは分かりませんが、結局、私が話し合いに参加してすぐに弁護士基準の通院慰謝料の提案がありました。
交通事故紛争処理センターは、被害者本人でも使うことのできるADRですが、このようなこともあるので、交通事故紛争処理センターで解決する場合には弁護士に依頼しましょう。
クロノス総合法律事務所では、電話、メール、LINEで交通事故の無料相談を受けております。交通事故紛争処理センターで解決をお考えの方はクロノス総合法律事務所にご相談ください。
警察や保険会社から物損事故で処理したいと言われても断ろう!
交通事故に遭うと交通事故証明書が発行されます。
この交通事故証明書には,「人身事故」もしくは「物損事故」と事故の種類が記載されるのですが,被害者が事故の怪我で通院をして治療を受けているにもかかわらず,交通事故証明書に「物損事故」と記載されているケースがあります。
通常は,医師が作成した診断書を警察に提出すれば,人身事故として処理されるのですが,警察や保険会社が物損事故で処理したいと言って物損事故扱いになってしまうことがあるようです。
交通事故の被害者から相談を受けると,必ず交通事故証明書で人身事故になっているかを確認するのですが,物損事故になっている場合には,被害者になぜ人身事故扱いにしなかったのか確認をします。
そうすると,相談者は,「警察から物損事故で処理したいと言われた」,もしくは,「保険会社の担当者から治療費は支払うから物損事故として処理してほしいと頼まれた」と回答します。
被害者は,警察や保険会社の担当者から物損事故にして欲しいと頼まれて善意で人身事故にせず物損事故にしているのですが,警察や保険会社の担当者は被害者のことは一切考えず自分たちのことしか考えずに物損事故にして欲しいとと言っているので注意が必要です。
人身事故の場合,警察は,事故現場などの実況見分(いわゆる現場検証)をして,その結果を記録した実況見分調書を作成します。
また,加害者と被害者から事情を聴取して,それぞれの供述調書を作成します。
実況見分調書や供述調書など交通事故の証拠がそろったら,事件を検察官に送致して,交通事故の加害者の刑事処分を検察官に図ることになります。
一方,物損事故の場合,警察は実況見分調書を作る必要も,供述調書を作る必要もなく,物件事故報告書を作成するだけで,検察官に送致もすることなく事件の処理が終了となります。
もうお判りでしょうが,警察官が物損事故で処理をしたいというのは,事件処理を簡単に終わらすためです。被害者のことなど全く考えてません。
また,保険会社の担当者が物損事故として処理して欲しいというのは,当然,物損事故で処理できれば保険会社の支払いを少なくできるからです。
以下では,怪我をしているのに物損事故で処理をしてしまうとどのようなデメリットがあるかについてみていきたいと思います。
クロノス総合法律事務所では物損事故から人身事故への切り替えもアドバイスできますのでご相談ください!
保険会社が早期に治療費の支払いを打ち切る可能性が高くなる
怪我をしているのに物損事故として処理してしまうケースというのは,むちうちのケースが多いと思います。むちうちは,事故直後はほとんど症状がなかったとしても少し時間が経ってから色々な症状が出てくるということがあるので,思いのほか通院が長くなったりします。
ところが,物損事故で処理をしていると,保険会社は,自賠責の120万円の範囲で解決をしようとするので,治療費が120万円を超える前に治療費の支払いの打ち切りを通告してきます。
保険会社は,人身事故の場合でも早期の治療費の打ち切りはあるのですが,物損事故ではほぼ間違いなく早期で治療費の支払いを打ち切り,長期間の通院を認めることはありません。
物損事故で処理してしまうと,保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切る可能性が高くなります。
後遺障害が非該当になる可能が高くなる
交通事故証明書で物損事故となっていた場合,後遺障害の被害者請求をするときには,後遺障害が非該当で返ってくることを覚悟します。
後遺障害の被害者請求をする際には,交通事故証明書を提出するのですが,物損事故の場合,人身事故に比べて明らかに自賠責からの回答が早いので,おそらく調査事務所では,交通事故証明書を確認して物損事故となっていたら,ほとんど調査をせずに非該当と判断して,自賠責に結果を返しているのではないかと思います。
当然,後遺障害が非該当であれば,後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料は認められませんので,保険会社の支払いは少なくなります。
被害者の収入にもよるのですが,後遺障害14級が認められた場合と,非該当の場合とでは,200万円くらいは賠償金の額が違ってきます。
頚椎捻挫と診断されたのに,知らずに善意で物損事故にしてしまうと,200万円の損をする可能性があるということです。
過失割合が不利になる可能性がある
通常,過失割合は交通事故の状況から判断することになります。
基本的には,交通事故の事故態様で当事者の過失割合は決まってくるのですが,当然,その事故特有の事情によって過失割合が変わってくることがあります。
例えば,加害車両が法定速度を超過していたとか,加害車両の運転手が携帯電話を利用していたというような事情です。
実況見分や当事者の事情聴取をしていれば,このような事実がはっきりすることが多いのですが,先ほども説明したように,物損事故として処理してしまった場合,警察は,実況見分や当事者の事情聴取を行いません。
そうすると,その事故特有の事情が分からずに,交通事故の事故態様だけで当事者の過失割合を判断しなければならなくなってしまいます。
もし,加害者の過失を増加する事情があったとしても,それが記録されていなければ,被害者がどんなに主張してもその事情が認められることはありません。
物損事故で処理してしまうと,詳しい事故の状況が判断できないので,被害者の過失割合が不利になってしまう可能性があります。
物損事故でも怪我をして通院していれば慰謝料は請求できる!
物損事故で処理してしまっても怪我をして通院していれば慰謝料を請求できます。
慰謝料は、通院期間や通院回数を基準に算定しますので、物損事故で処理してしまっても通院期間が長くなれば慰謝料もそれなりの金額になることがあります。
もちろん、先ほど説明したように物損事故だと治療費の早期の打ち切りの可能性が高くなるので、それほど長く通院することはできないかもしれませんが、それでも弁護士基準で慰謝料を計算した場合50万円から90万円程度になる可能性があります。
物損事故で処理してしまってもどれくらいの慰謝料が請求できるかは弁護士に相談した方がいいかもしれません。
まとめ
このように,怪我をしているのに物損事故として処理をしてしまうと,被害者に不利になってしまうことが多くあります。
もちろん,怪我をしていないのであれば物損事故で処理することは当然ですが,怪我をしているのに,警察や保険会社の担当者に気を使って,本来,人身事故扱いにすべき事故を物損事故扱いにすることは絶対にしてはいけません。
頚椎捻挫で加療期間1週間という診断であっても,怪我をしていることには間違いありません。医師が作成した診断書を警察に提出すれば,警察は面倒でも人身事故として処理することになりますので,軽くても怪我をした場合には人身事故として処理してもらい,後から失敗したと思うことがないようにしましょう。
また物損事故で処理してしまっても怪我をして通院しているのであれば、慰謝料を請求できる可能性がありますので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。
クロノス総合法律事務所では物損事故から人身事故への切り替えもアドバイスできますのでご相談ください!
交通事故で労災保険から支給される休業補償の内容
交通事故で労災保険を利用できる場合,仕事を休んだら労災保険から休業補償の給付があります。労災保険の休業補償は,給付基礎日額の60%に相当する金額しか給付されません。労災保険の休業補償が給付基礎日額の60%しか給付されないのは,労働基準法の休業補償が給付基礎日額の60%なんですが,これに準じているためです。
この給付基礎日額の60%の休業給付以外に,社会復帰促進事業等の一環として支払われる休業特別支給金というものが給付されます。休業特別支給金は,給付基礎日額の20%が給付されるものですが,福祉給付の性質を有しているので,休業給付そのものとは性質が多少異なります。
とはいえ,休業給付と特別支給金を合計すると,給付基礎日額の80%に相当する金額の給付があるということになります。
休業特別支給金は賠償金から控除されない
労災保険の休業補償は,交通事故の賠償における休業損害と同質性があります。また,労働者災害補償保険法で国が労災保険給付を行った場合,被害者が加害者に対して有している損害賠償請求権のうち労災給付した金額に相当する分については国に移転すると規定されています。
このことから,労災保険の休業補償は,交通事故の賠償における休業損害から控除されることになります(「交通事故で労災保険金を受け取っている場合の控除について」参照)。
ただし,休業特別支給金は,先ほど説明したように休業給付とは異なり福祉給付の性質を有しているものなので,交通事故の賠償における休業損害と同質性がありません。また,労働者災害補償保険法は,国が休業特別支給金を給付したことによる損害賠償請求権の移転を規定していません。
以上のことから,休業特別支給金は交通事故の賠償における休業損害から控除されることはありません。
そうすると,交通事故の賠償における休業損害から労災保険の休業給付の60%だけを控除すればいいので,残りの40%の休業損害は加害者に対して賠償金として請求できることになります。
これまで,保険会社が労災保険の休業特別支給金の分まで賠償金から控除してきたという経験はありませんので,大丈夫だとは思いますが,保険会社から賠償金の提示があったら,念のために,休業特別支給金まで控除した内容になっていないか確認するようにして下さい。
給付基礎日額は歴日数で計算されている
給付基礎日額とは,簡単に行ってしまうと1日当たりの給与額になります。労災保険の場合,給付基礎日額は,事故前3ヶ月の基本賃金+手当の合計金額を歴日数(だいたい90日)で割った金額となっています。
歴日数とは,土日も含めたカレンダーの日数です。
そうすると,歴日数は,通常,休日となる土日も含めた日数なので,実際に稼働した日数(稼働日数)で割った場合よりも,1日当たりの給与額が小さい金額になってしまいます。労災の場合,休業日数に土日も含まれますので,このような計算でも問題はありません。
一方,交通事故の賠償における休業損害は,通常は,土日を除いた実際に休んだ日だけを休業日数としますので,労災保険と同じ歴日数で日額を計算すると,休業日数に土日が含まれない分,損するということになってしまいます。
このような損を避けるために,交通事故の賠償における休業損害の1日当たりの給与額は,実際に稼働した稼働日数で計算する必要があります。
労災保険の休業補償には免責期間がある
労災保険の休業補償は,最初の休業日から3日間は免責期間になります。つまり,最初の休業日を含めて3日は,休業補償は給付されないということです。
そうすると,交通事故の賠償における休業損害を請求する場合には,労災保険の免責期間の3日分も含めて計算する必要があるということに注意が必要です。
過失相殺の方法
交通事故の発生に被害者にも過失があった場合,賠償金は損害額から過失相殺による控除をした金額となります。
被害者の過失が大きくて,過失相殺をした結果,賠償の休業損害よりも労災保険の休業補償の方が高額になってしまうということがあります。
しかし,このような場合でも,労災保険の休業補償はほかの損害項目から控除されることはありません。
例えば,労災保険から60万円の休業補償を受け,交通事故の賠償における休業損害が100万円だったとします。この場合,過失相殺がなければ,100万円-60万円=40万円が休業損害として支払われる金額になります。
この例で,被害者に50%の過失があったとします。
そうすると,100万円×(1-50%)=50万円(休業損害)
50万円(休業損害)-60万円(労災保険の休業補償)=-10万円
このように,被害者に50%の過失があった場合,10万円ほど労災保険の休業補償が払い過ぎということになってしまいます。
ところが,この10万円は,ほかの慰謝料などの損害項目から差し引かれることはありません。
これは,労災保険給付は同質性を有する損害項目からしか控除できないという性質を持っていることによるものです。
つまり,労災保険の休業補償は,賠償における休業損害と同質性がありますが,慰謝料とは同質性がないため,慰謝料から控除することはできないということになります。
関連記事
労働災害(労災)の障害等級に納得がいかない場合どうすればいい?
交通事故で片方の肩の腱板断裂が生じた後の後遺障害
交通事故で片方の肩の腱板断裂が生じた場合、症状としては疼痛や肩関節の可動域制限が残存しますので、肩関節の機能障害の後遺障害が認定される可能性があります。肩関節の機能障害の後遺障害等級と障害の程度は以下の表のとおりです。なお、関節機能障害の後遺障害が認定された場合、疼痛の症状は機能障害と通常派生する関係にあるため、独立して後遺障害として認定されることはありません。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害8級 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
肩関節の主要運動は、屈曲(前方挙上)、外転(側方挙上)及び内転になりますので、これらの可動域が健側の肩関節と比較してどの程度制限されているかによって、上表の後遺障害等級が認定されることになります。
MRIによって腱板断裂が確認できることが必要
肩の腱板断裂が生じた場合、腱板の状態はレントゲンでは明確に確認ができないため、MRI検査を実施する必要があります。MRI画像で腱板断裂が確認されると、肩関節の機能障害の原因が他覚的所見によって確認されたということになります。
余談ですが、頚椎捻挫を負った被害者の後遺障害診断書に、頚椎の運動障害や肩関節の機能障害が残っていると記載されていることがありますが、運動障害や機能障害は、骨折、脱臼、今回のテーマである腱板断裂などの器質的損傷がなければ認定されません。そのため、頚椎捻挫で頚椎の運動障害や肩関節の機能障害が残ったとしても後遺障害として認定されることはありません。
ときどき、交通事故の患者さんだと、医師が頚椎捻挫程度しか負っていないと思い込んでしまって、事故直後にMRI検査をせず、時間が経っても肩関節の痛みが改善しないため、かなり時間が経ってからMRI検査をしたら腱板が断裂していたことが発見されるということもありますので、交通事故に遭って肩関節の痛みが続くようであれば、できるだけ早期にMRI検査を実施してもらった方がいいと思います。
無症候性の肩の腱板断裂に注意
肩関節の腱板断裂で気を付けなければならないのが無症候性の腱板断裂です。もともと、肩の腱板は50歳以上になると断裂しやすくなるため、外傷とは無関係に断裂をすることが多くあるのですが、その中で腱板断裂が生じているのに症状を感じないケースというのがあり、それを無症候性の腱板断裂といいます。
無症候性の腱板断裂の場合、外傷を原因とする腱板断裂と違い、画像上、骨棘や骨硬化が認められるため、通常は、外傷を原因とする腱板断裂か無症候性の腱板断裂かは判別することができるそうなのですが、ときどき、その判別が難しく、自賠責が外傷を原因とする腱板断裂と判断して、機能障害の後遺障害を認定するケースがあります。
このような場合、無症候性の腱板断裂が事故前から存在していたとして、保険会社側から後遺障害そのものを争われることになります。そのような場合、別の医師の画像診断などを依頼して意見をもらうのですが、無症候性の腱板断裂だったという意見になると、全く反論ができなくなってしまい、後遺障害が否定されてしまいます。後遺障害が否定されると逸失利益も後遺障害慰謝料も認めらなくなってしまい、賠償金がかなり低額になってしまいます。
そのため、被害者が高齢者で、事故の状況などから肩を強打していないのに、腱板断裂が生じている場合には、無症候性の腱板断裂が事故前から存在していた可能性が高いので、この場合は注意が必要です。
関連記事
仕事を休んだり、後遺障害が残っても休業損害や逸失利益を争われる仕事とは?
交通事故に遭って仕事を休んで収入が得られなければ休業損害が認められます。また、後遺障害が残れば後遺障害による逸失利益が認められます。
通常、仕事を持っている人が被害者になった場合には、仕事を休めば休業損害が認めれますし、後遺障害が残れば逸失利益が認められます。
ところが、仕事を持っているにもかかわらず休業損害や逸失利益がないと保険会社から争われる場合があります。それは、会社の役員として仕事をしている人が被害者になった場合です。
加害者側に弁護士がついた場合には、会社の役員というだけで休業損害をすべて否定したり、逸失利益を全く認めないということはないのですが、保険会社の担当者と示談交渉をしていると、ときどき、被害者が会社の役員というだけで休業損害も逸失利益も認めないと主張してくる担当者がいます。
驚くことに被害者が会社の役員の事案で被害者側の保険会社に弁護士費用特約で弁護士費用を請求した際に、担当者から休業損害と逸失利益を損害額から外して着手金の請求をして下さいと言われたこともあります。
保険会社の担当者は、裁判例をよく理解していない担当者も多いので、会社の役員というだけで休業損害も逸失利益も認められないといってくることが本当に多いです。
会社の役員の休業損害や逸失利益が問題になる理由
では、なぜ会社の役員の休業損害や逸失利益は問題になることが多いのでしょうか。
通常、会社の役員の場合、会社から給与ではなく役員報酬という名目で報酬の支払いがなされています。一般的に、役員報酬は、決まった金額か、もしくは役員報酬基準に従って計算された金額が支払われるようになっているため、残業をしたから金額が増えるという性質のものではありません。
逆に言うと、働かなかったとしても報酬として会社から支払われるケースもあります。このような役員報酬のことを利益配当的な報酬と言ったりします。
休業損害や逸失利益は、怪我や後遺障害によって働けなくなり収入が得られなくなったことに対して認められる損害ですので、もし、役員報酬が働かなくても支払われるものであれば、休業損害や逸失利益は発生していないということになります。
このように、役員報酬が働かなかったとしても支払われるケースがあるために、役員の休業損害や逸失利益が問題になることがあるのです。
労務対価性がある報酬については休業損害も逸失利益も認められる
確かに、家族経営の会社などでは、税金対策のために家族を名目だけ役員として報酬を支払うというような場合がありますが、このような場合に、名目だけの役員が事故に遭っても、実際に仕事を休んだわけでも、後遺障害によって将来的に役員報酬が得られなくなるわけでもないので、休業損害や逸失利益を否定されてもやむを得ません。
しかし、役員として実際に仕事をしている人まで、役員というだけで休業損害や逸失利益を否定されるいわれはありません。
最高裁判例も、以下のように判断して役員の休業損害や逸失利益を認めています。
「企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきである」と判断しています(最判昭和43年8月2日)。
この最高裁の考え方は、役員報酬のうち労務対価部分については休業損害や逸失利益を認め、利益配当部分については休業損害や逸失利益を認めないという労務対価説という考え方によるものです。
利益配当部分というのは、先ほど説明した税金対策のための役員報酬や役員が株主も兼ねており株式配当分が含まれているような役員報酬を指します。
このように、役員であっても役員報酬が労務の対価として支払われている場合には、役員が交通事故で仕事を休んだり、後遺障害を残した場合には、休業損害も逸失利益も認められるので、役員というだけで休業損害や逸失利益を否定する保険会社の担当者の主張はおかしいということになります。
役員というだけで、保険会社が休業損害や逸失利益を否定してきたときには、必ず弁護士に相談して下さい。
関連記事
解決実績
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
腕や足の骨折後に疼痛の神経症状が残った場合に認定される後遺障害
交通事故で腕や足を骨折をした場合、通常は、固定をすると骨折部が骨癒合して回復に至り症状固定となります。骨折して最終的に症状固定に至っても疼痛が残っている場合には、神経症状の後遺障害が認定される場合があります。腕や足の骨折後に神経症状が残ったときに認定される後遺障害は、むちうちと同じ「局部の神経系統の障害」が認定されます。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害12級 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 後遺障害14級 | 局部に神経症状を残すもの |
12級と14級の違いは,「がん固な神経症状」かどうかにあります。昨日の「むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする際の注意点」でも説明をしましたが、「がん固な神経症状」とは「症状の原因を他覚的に証明できる」場合のことをいい、「症状の原因を他覚的に証明できる」場合とは,基本的には,レントゲン,CT,MRIなどの画像によって症状の原因を確認できることを意味します。
そうすると、骨折は、むちうちと違ってレントゲンで確認ができるのだから、常に、12級の後遺障害が認定されるようにも思えます。
神経症状12級の後遺障害の認定には骨折後の変形癒合や癒合不全などが必要
ここで、あらためて後遺障害が何に対して認定されるのかを考えてみると、後遺障害は怪我に対して認定されるのではなく、怪我をして残った症状に対して認定されるものです。そうすると、骨折はあくまで怪我であって、骨折が完全に治ってしまえば、症状が残らないということもあるので、骨折をしただけでは後遺障害が認定されないということもあります。
そのため、レントゲンで骨折が確認しできたとしても、それだけでは12級の後遺障害は認定されないということになります。
では、どのような他覚的所見が認められれば、骨折後の疼痛の症状に対して12級の後遺障害が認定されるのでしょうか。
通常、骨折部の骨癒合が良好であれば、疼痛などの症状は残らないことの多いのですが、骨癒合が良好でない場合に、骨折後に疼痛の症状が残ります。骨癒合が良好でない場合というのは、骨折部に変形癒合や癒合不全などが生じた状態をいいます。
変形癒合とは骨折部が正常でない位置関係で癒合した状態をいいます。
また、癒合不全とは骨折が通常の癒合に至る期間を経過しても癒合しない状態をいいます。癒合不全の状態があまりにも酷いと神経症状の後遺障害よりも重い偽関節の後遺障害が認定されることもあります。
変形癒合もしくは癒合不全は、骨折部に疼痛を生じさせる原因となりますし、いずれもレントゲンで確認することができますので、症状の原因となる他覚的所見が認められ12級の後遺障害が認定されるということになります。
骨癒合が良好でも神経症状14級の後遺障害が認定されることがある
このように、骨折後の疼痛の症状に12級の後遺障害が認定されるためには、変形癒合や癒合不全などが骨折後の骨癒合が良好でない状態が必要となるのですが、骨癒合が良好であれば後遺障害が認められないかというとそうではありません。
骨癒合が良好でも事故後から疼痛の症状があり、症状固定時まで継続していれば、神経症状14級の後遺障害が認定される可能性があります。神経症状14級の後遺障害が認定されるためには、むちうちの場合と同じように症状が続いていて、継続して治療を受けているかという点が重要となります。
関連記事
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。