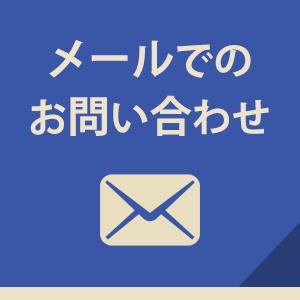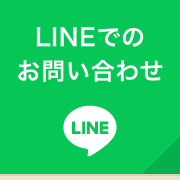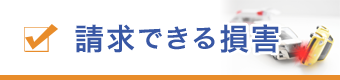横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
後遺障害 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》 - Part 2
脊柱変形の後遺障害
脊柱とは,頚椎,胸椎,腰椎,仙骨,尾椎から構成されるもので,躯幹を支持し,同時に上肢や下肢からの力学的並びに神経学的情報を脳に伝えるための重要な組織のことを言います。
脊柱の機能は,躯幹の支持性,脊椎の可動性,脊髄などの神経組織の保護の3つに集約されます。
ただし,後遺障害の認定においては,脊柱の後遺障害は,頚部及び体幹の支持機能,保持機能,運動機能に着目したものであるため,仙骨と尾椎は脊柱に含まれません。
脊柱変形とは,脊椎骨折,圧迫骨折,脱臼により脊椎に変形を残す後遺障害です。
圧迫骨折は、レントゲンで骨折していることが確認されれば後遺障害が認定されますので、脊柱変形の後遺障害の原因で1番多い骨折になります。
脊椎の変形の程度によって以下の表のとおり6級,8級,11級に区分されています。
| 後遺障害等級 | 障害の程度 | 具体的な基準 |
|---|---|---|
| 後遺障害6級 | 脊柱に著しい変形を残すもの | エックス線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で以下のいずれかに該当する場合 ①脊椎圧迫等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの。 ②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じるとともに,コブ法による側弯度が50度以上となっているもの。 |
| 後遺障害8級 | 脊柱に中等度の変形を残すもの | エックス線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で以下のいずれかに該当する場合 ①脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの ②コブ法による側弯度が50度以上であるもの ③環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの。 ⅰ60度以上の回旋位になっているもの ⅱ50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの ⅲ側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの |
| 後遺障害11級 | 脊柱に変形を残すもの | ①脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの ②脊椎固定術が行われたもの ③3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの |
脊柱変形の労働能力の喪失が問題になった経緯
以前,脊柱変形は6級と11級しかなく,後遺障害を認定する具体的基準も現在とは異なるものでした。
例えば,6級は,「レントゲン写真上明らかな脊柱圧迫骨折または脱臼等に基づく強度の亀背・側弯等が認められ,衣服を着用していても,その変形が外部から明らかに分かるもの」という内容でした。
現在の具体的基準は客観的な基準になっていますが,以前は,「衣服を着用していても,その変形が外部から明らかに分かるもの」というやや主観的な条件も含まれていました。
このような基準であったため,著名な整形外科の医師が「着衣の上から分かる程度の変形であれば6級(喪失率67%)とすることは,それがもたらす労働能力の低下となると過大評価である」と指摘したということがありました。
また,11級については,「脊椎圧迫後の変形では,労働能力の実質的喪失は,ほとんど無いに等しい」という指摘もありました。
このように,著名な整形外科医が脊柱変形の労働能力の喪失に疑問を呈したことから,脊柱変形によって労働能力は喪失しないという主張が保険会社側からされるようになったのです。
基本的に脊柱変形でも労働能力の喪失は認められるべき!
脊柱変形は,これにより頚部及び体幹の支持機能,保持機能,運動機能が低下するという点を評価して後遺障害とされているものです。
頚部や体幹の支持機能,保持機能,運動機能が低下すれば,当然,労働能力に影響をありますので,基本的には,脊柱変形による労働能力の喪失は認められるべきだと思います。
裁判官が中心となって編集された「交通関係訴訟の実務」にも以下のような説明があります。
「脊柱変形は,脊椎骨折に由来する器質的障害であるが,脊柱の支持性及び運動性を減少させるとともに,骨折した脊椎の局所に疼痛や易疲労性を生じさせ得るものといわれている。そして,障害等級認定基準の見直しの経緯及び内容を踏まえると,高度の脊柱変形については,基本的には現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられる。」(森冨義明,村主隆行編著「交通関係訴訟の実務」207頁)
このように,裁判所も少なくとも高度の脊柱変形である6級については,等級通りの67%の喪失率があると考えています。
では,11級の脊柱変形についての労働能力喪失についてはどのように考えられているのでしょうか。
同じく「交通関係訴訟の実務」では以下のように説明されています。
「脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には,このような取り扱いが相当ではないこともあり得る。このような場合には,被害者の職業,神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断することになろう」(森冨義明,村主隆行編著「交通関係訴訟の実務」207頁)
このように,実務では,軽微な脊柱変形であったとしても,直ちに労働能力の喪失が否定されるわけではなく,被害者の職業,神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断するという取り扱になっています。
私が担当した交通事故で11級の脊柱変形が認定された事案では,脊椎の運動機能は低下しているので,周辺の筋肉がこわばることで痛みの症状が現れるということが多く,また,疲れやすくなったり疲れが取れにくくなったりで仕事に影響のあるケースばかりでした。
そのため,11級の脊柱変形の事案でも,労働能力の喪失を否定されたという件は1件もなく,すべてのケースで11級の喪失率20%がそのまま認められました。
11級の脊柱変形ですと,労働能力の喪失が争われやすいですが,脊柱変形により出現している症状とその症状による仕事の支障の程度をしっかりと主張することが労働能力の喪失を認めさせる上で大事なのではないかと思います。
脊柱変形の後遺障害慰謝料は最低でも420万円、賠償金は1000万円を超えることもあります。
脊柱変形の後遺障害が認定された場合、等級は最低でも11級になります。
後遺障害11級の後遺障害慰謝料は弁護士基準で420万円になります。
逸失利益の労働能力喪失率は11級で20%、もし労働能力喪失率が下げられても12級の14%は維持されることが多いです。
そのため、脊柱変形の後遺障害が認定された場合、被害者に大きな過失がない限り賠償金は1000万円以上になることが多いです。
保険会社は脊柱変形の後遺障害の場合、必ず労働能力喪失率を下げてきますし、後遺障害慰謝料も弁護基準では提示しませんの420万円を下回ります。
保険会社から100万円を超えるような賠償金の提示があっても、圧迫骨折をしている場合や圧迫骨折で脊柱変形の後遺障害が認定された場合には、示談する前に弁護士に相談しましょう。
解決実績
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得(一人暮らしの無職の高齢女性で逸失利益を獲得!)
70代女性 圧迫骨折(脊柱変形)11級 約1100万円獲得 500万円増額
関連記事
自賠責の後遺障害と労災の障害の認定基準は同じ
自賠責の後遺障害は1級から14級までありますが,これは労災の障害補償の障害等級表に準じた内容になっていますので,自賠責の後遺障害の認定基準と労災の障害認定基準は同じということになります。
例えば,交通事故でよくあるむち打ち症による神経症状14級の場合,正式には,自賠法施行令別表第2に規定されている第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という基準に該当した時に認定されます。
労災の障害認定基準を規定した労働者災害補償保険法施行規則別表第1の第14級9号も「局部に神経症状を残すもの」という基準になっています。
自賠責と労災で認定された後遺障害が一致しないことがある
このように,自賠責は労災の障害認定基準を準用しているので,通勤災害のように自賠責も労災も使えるような場合,認定される後遺障害は必ず同じ等級になるように思えます。
ところが,自賠責で認定された後遺障害と労災で認定された障害等級が一致しない,もしくは一方で後遺障害認定されたのにもう一方では非該当だったということが時々あります。
認定された後遺障害の等級が一致しなかったり,一方で後遺障害認定されたのにもう一方で非該当だったということが生じる大きな原因として以下の2つが考えられます。
①後遺障害診断書等の資料に症状固定時に残っている症状がしっかりと書かれていない
②後遺障害の有無や程度を判断するために必要な検査結果が労災と自賠責で異なっている
症状がしっかりと書かれていない
症状はあくまでも自覚症状であったり,家族など被害者の周囲の人の申告に基づいて後遺障害診断書等の資料に記載される主観的なものですので,症状の捉え方が医師によって違うということが生じてきてしまいます。
特に,高次脳機能障害のように認知機能障害や人格障害の程度よって後遺障害等級が変わってくる障害になると,後遺障害診断書以外に障害の程度を確認するための資料があるのですが,同じ被害者のことでも障害の程度が違って記載されているということが時々あります。
このような場合に,自賠責の認定と労災の認定が異なってくるということがあります。
検査結果が自賠責と労災で異なっている
後遺障害診断書等の資料には,通常は,残っている症状が後遺障害に該当するかを確認するのに必要な検査結果が記載されています。
例えば,機能障害であれば,関節可動域の検査結果が記載されています。
この検査結果が自賠責と労災で異なっているということがあります。
後遺障害認定の際に提出する資料は,自賠責と労災で異なっているのですが,その資料を自賠責と労災でそれぞれ違う医師が作成するということがあります。
また,資料の作成時期も異なっているということがあります。
このように,資料を作成する医師や作成時期が違うと,検査結果も違ってくるということがあります。
先ほどの機能障害は,測定する時期によって関節の可動域の制限の程度が異なるということがよくあります。
そうすると,例えば,労災では2分の1以下の制限が認められ10級が認定されたのに,自賠責では4分の3以下の制限しか認められず12級しか認定されないという事態が生じます。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合にはどうすればいいか
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合にはどうすればいいのでしょうか?
認定された後遺障害の結果に不服があるときのために,自賠責では異議申立て,労災では審査請求という制度が用意されています。
後遺障害の認定に納得がいかない場合には,この制度を利用することになります。
いずれの制度も,なぜ後遺障害が認定されなかったのか,なぜ上位の後遺障害等級が認定されなかったのかを分析した上で,認定されなかった理由を覆すだけの資料を準備する必要があります。
では,異議申立てないし審査請求の資料に,一方の有利な認定結果を用いることはできるでしょうか?
先ほどの機能障害の例で説明すると,労災で10級が認定されて,自賠責で12級しか認定されなかったときに,労災の10級の認定結果自体を自賠責の異議申立ての資料として用いるのことができるのかという問題です。
自賠責又は労災は,後遺障害の認定をする際にそれぞれ必要な調査をしていますが,これは異議申立てや審査請求でも同じです。
そうすると,異議申立てや審査請求でも後遺障害の認定基準に該当するかを症状や検査結果を記載した新たに提出した資料に基づいて判断をします。
一方の有利な認定結果は症状や検査結果を記載した資料ではありませんので,提出しても参考程度にしか用いられません。
つまり,一方の有利な認定結果は,異議申立てないし審査請求で最初の認定を覆すだけの決定的な証拠にはならないということです。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合には、後遺障害に強い弁護士に相談しよう!
最初に説明したように、自賠責と労災の後遺障害の認定基準は同じです。
そうすると、本来であれば、自賠責と労災の後遺障害の認定は同じ結果になるはずです。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違うということは、必ず原因があるはずです。
後遺障害の認定結果が違う理由は、後遺障害診断書等に認定基準を満たす内容が記載されていないということが多いと思います。
後遺障害診断書等に認定基準を満たす内容が記載されてない場合には、認定基準を満たすような内容を記載してもらうようにしなければなりません。
そのためには、後遺障害の認定基準をしっかりと理解している必要があります。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合には、後遺障害の認定基準をしっかりと理解している後遺障害に強い弁護士に相談しましょう!
クロノス総合法律事務所は、後遺障害の異議申立て、審査請求をして後遺障害の認定結果を変更した実績が多くあります。
後遺障害の認定結果を変えたいという被害者の方は、クロノス総合法律事務所にご相談下さい。
クロノス総合法律事務所は、電話・メール・LINE・オンライン面談のいずれの方法でも無料相談をしております。
解決実績
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)
関連記事
機能障害とは?
機能障害とは,上肢,下肢,指の関節の動きが制限された場合に認められる後遺障害です。交通事故では比較的によく見られる後遺障害になります。
上肢及び下肢であれば3大関節の動きが制限された場合に後遺障害が認定されます。上肢とは腕のことで下肢とは脚のことをです。3大関節とは,腕であれば肩関節,肘関節,手関節(手首の関節)をいい,脚であれば股関節,膝関節,足関節(足首の関節)をいいます。
上肢及び下肢の機能障害は,「関節の用を廃した」場合,「関節の機能に著しい障害を残す」場合,「関節の機能に障害を残す」場合で認定される等級が異なってきます。
上肢の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害1級 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害5級 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害6級 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害1級 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害5級 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害6級 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害12級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
指の場合は,手指と足指で後遺障害が認定される条件が異なります。
手指の場合は,「手指の用を廃した」場合と「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」場合に後遺障害が認定されます。
足指の場合は,「足指の用を廃した」場合だけ後遺障害が認定されます。
手指の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害7級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害9級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 後遺障害12級 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
| 後遺障害13級 | 1手の小指の用を廃したもの |
| 後遺障害14級 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
足指の機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害9級 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害11級 | 1足の第1の足指を含み2の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害12級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害13級 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害14級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
同一上肢の機能障害と手指の機能障害,または,同一下肢の機能障害と手指の機能障害は,本来的にはそれぞれ同一系列ではないのですが,みなし系列として同一系列の扱いを受けてしまいます。
具体的に説明すると,例えば,右肘関節で10級の機能障害が認定され,右指関節で10級の機能障害が認定された場合,併合されて1等級繰上り9級になるように思えますが,同一系列の扱いになりますので,後遺障害等級は10級となってしまいます。
機能障害はよく争われる後遺障害
機能障害は関節付近の骨を骨折したような場合に残りやすい障害なので,よく発生する後遺障害です。ただ,これまでの経験からすると,機能障害は,裁判でよく争われる後遺障害という印象が強いです。
機能障害は,最初に説明したように関節の動きが制限される後遺障害ですので,症状固定時に関節がどの程度動くかを測定して,その数値を後遺障害診断書に記載し,その数値からどの程度関節の動きが制限されているかを判断して,後遺障害の認定をします。
当然ですが,症状固定とはこれ以上治療しても改善しない状態ですので,事故直後が最も関節が動かず,徐々に改善して症状固定時が最も改善した状態ということになります。
ところが,ケースによっては症状固定時の関節の動きの数値よりも,それ以前に測定した関節の数値の方が改善した数値になっているということがあります。そうすると,本当は,関節の動きはもっといいはずであるのに,後遺障害診断書には本当の動きよりも悪い数値が記載されたとして,保険会社側の弁護士から,機能障害が本当に残っているのか,または,もっと軽い程度の機能障害しか残っていないのではないか,と争われてしまうのです。
後遺障害診断書に記載された関節の動きの数値よりも,それ以前のカルテに記載された関節の動きの数値の方が改善した数値になっていたということは,実際によくあることですので,関節機能障害は,障害の存在や程度がよく争われる後遺障害といえます。
機能障害には注意が必要
このように,関節機能障害はよく争われる後遺障害ですので注意が必要です。
関節の動きの測定方法が医師によってばらつきがあるということを知っておく必要があります。
本来であれば,日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が制定する測定法によって関節の動きを測定する必要があります。
ところが,医師によってはその測定法に従わずに測定をしたり,測定器を使わずに目測で測定することが多々あります。
そのために,先ほど説明したような症状固定時の関節の動きの数値よりも,その前に測定した関節の動きの数値の方がよい数値であったというような事態が生じてしまうのだと思われます。
そのため,もし,機能障害の後遺障害で裁判をする場合には,裁判をする前にカルテを取得して後遺障害診断書に記載された関節の動きの数値よりも良い数値がカルテに記載されていないか確認した方が良いでしょう。
疼痛以外の感覚障害とは?
今回はかなりマイナーな後遺障害の話になります。私が以前担当した交通事故で「疼痛以外の感覚障害」という後遺障害が認定されたという事案がありました。
疼痛以外の感覚障害とは,疼痛はないけど蟻走感や感覚脱失等の感覚異常が残ってしまった障害をいいます。ちなみに,私が担当した被害者の方は,多少違和感があるくらいで,常時気になるようなことはないと言っていました。
疼痛以外の感覚障害は,単に感覚異常が残っただけでは認められずその範囲が広い場合に後遺障害として認定されます。ただし,労災や自賠責の基準では,どの程度の範囲に感覚異常が残れば,「範囲が広い」に該当するのかは明確にされていません。
疼痛以外の感覚障害の後遺障害等級は14級しかなく,そのほかの神経症状の後遺障害のように他覚的所見があったとしても12級は認定されません。というか,おそらく,疼痛以外の感覚障害の後遺障害は,他覚的所見がある場合にしか認められないと思います。
私が担当した事件でも,こめかみ辺りから3つに分かれている三叉神経のうち第三枝の損傷が画像によって確認することができるという事案でした。
疼痛以外の感覚障害による労働能力の喪失はあるか?
疼痛以外の感覚障害は,先ほど説明したように後遺障害等級は14級しかなく,認定の基準も労働能力とは無関係な感覚異常の範囲が広いかどうかというものだったので,この事案を担当することになった時には,感覚障害による労働能力の喪失が認められるのかという疑問を持ちました。
このような疑問がありましたが,むちうちによる14級の後遺障害でも労働能力の喪失が認められるのだから,疼痛以外の感覚障害にも労働能力の喪失は認められるだろうとそれほど大きな問題とは考えていませんでした。それどころか,三叉神経損傷が画像によって確認でき他覚的所見があるのだから,14級でも労働能力喪失期間は10年にはなると考えていたくらいです。
また,示談交渉の段階では労働能力喪失期間に争いはありましたが,保険会社は逸失利益が認められないという争い方はしなかったので,それほど労働能力の喪失の有無については気にしていませんでした。
裁判になったら労働能力喪失の有無を争ってきた!
この事案は,結局,示談では解決できず,交通事故紛争処理センターへの申立てをしました。過失がある事案だったのですが,当方は,最低でも自賠責保険金75万円を除いて350万円以上の賠償金を主張し,相手方は,200万円程度の賠償金までしか応じられないという回答でした。そのため,交通事故紛争処理センターでも示談することができず,裁判に移行することになりました。
交通事故紛争処理センターの時点で,加害者側には弁護士がついていたのですが,交通事故紛争処理センターでは労働能力の喪失の有無を争わなかったにもかかわらず,裁判になったら労働能力の喪失の有無を争ってきました。
しかも,相手方弁護士が労働能力の喪失が認められないと主張する理由の1つに,感覚障害が残った部位が唇からアゴにかけてであったため,歯牙障害と同じようなものだという理由があったのです。
歯牙障害とは,事故によって歯が喪失や欠損して歯科補綴をした場合に認められる後遺障害なのですが,一般的に労働能力の喪失は認められません。
労働能力の喪失が認められた!
相手方弁護士は,三叉神経損傷による感覚異常はこの歯牙障害と同じだという主張を裁判になって初めてしてきたのです。この主張は盲点だったので多少ドキッとしました。確かに,残っている症状は多少違和感があるくらいで,普通に仕事をしていたので,歯牙障害と同じようなものと裁判所に思われてしまうのではないかと思ったからです。
しかし,歯牙障害と同じ口の障害には,「言語機能の障害」というものがあります。「言語機能の障害」とは,発音不能の語音がある場合に認定される後遺障害なのですが,これは,コミュニケーションに支障が生じるために問題なく労働能力の喪失が認められる後遺障害です。
そこで,歯牙障害ではなく言語機能の障害に近いと裁判所に思わせれば,裁判所は労働能力の喪失を認めるのではないかと考え,そのような主張をしました。つまり,唇からアゴにかけての感覚障害によって事故前に比べて会話がしづらくなっておりコミュニケーションに支障が生じているという主張をしたのです。
この作戦がうまくいったのかは分かりませんが,裁判所が出した和解案では,感覚異常の後遺障害による労働能力の喪失が認められました。しかも,労働能力喪失期間は5年ではなく10年となりました(ちなみにトータルの賠償金は自賠責を除いて450万円となりました)。
どの部位に疼痛以外の感覚障害が残っても労働能力の喪失が認められるか?
今回は,唇からアゴにかけての感覚障害だったので,コミュニケーションに支障があるという主張ができましたが,ほかの部位に感覚障害が残った場合にも労働能力の喪失は認められるでしょうか?
おそらく上腕部や前腕部,大腿部や下腿部,胸部や臀部など体の動きとあまり関係のない部位に感覚障害が残ったとしても,労働に支障が生じるケースは少ないと思うので,労働能力の喪失は認められないような気がします。
行政書士が被害者請求するのって弁護士法違反にならないの?
後遺障害の認定の手続きは被害者請求で行った方がいいという話をしました(「事前認定と被害者請求ってどっちがいいの?」をご覧ください。)。ただ,被害者請求は後遺障害の認定に必要な資料を自分で集めなければならないので少し面倒です。しかし,事前認定にすると,保険会社の担当者が被害者にとって不利な資料を提出してしまうかもしれません。そうすると,誰かに代わりに被害者請求の手続きを手伝ってもらいところです。
では,被害者請求は誰に手伝ってもらったらいいのでしょうか?
被害者請求は自賠法16条に基づく請求ですので,本来,被害者請求を代理することができるのは弁護士だけです。ところが,現在では,多くの行政書士が被害者請求の代理業務を行っています。弁護士法72条は,弁護士以外の法律事務の取り扱いを禁止していますが,行政書士が自賠法16条に基づく被害者請求を行うことは,弁護士法72条違反とならないのでしょうか?
大阪高裁平成26年6月12日は,行政書士が交通事故の被害者と締結した自賠責保険の申請手続き・書類作成等の準委任契約は,弁護士法72条に反するものであり,公序良俗に反するため無効であるという判断をしました。
通常は,被害者請求の手続きにおいては,被害者の方の症状を確認して,どのような後遺障害等級が認定されるかを予測し,その予測のもと,被害者の方にアドバイスをすることが必要となります。また,予測した後遺障害等級が認定されない場合には,自賠責保険に対して異議申立てをする必要があります。
そうすると,自賠法16条に基づく被害者請求は,将来法的紛争が発生することが十分に予測される手続ですので,弁護士法72条の法律事件に関する法律事務に該当します。
そうだとすれば,行政書士が自賠法16条に基づく被害者請求の代理をすることは,弁護士以外が法律事務を取り扱うことを禁止している弁護士法72条に違反すると考えるのが妥当です。おそらく,代理だけでなく,被害者請求に関するアドバイスをすることも弁護士法72条違反になるでしょう。
被害者請求の報酬は弁護士と行政書士どっちが高い?
このように,行政書士が被害者請求を代理したり,アドバイスしたりすることは弁護士法72条に違反すると考えられますが,現状,多くの行政書士がホームページ等で被害者請求に関して集客をしている以上,行政書士に被害者請求の手続きを依頼することを考えている方もいらっしゃると思います。
そこで,弁護士と行政書士の被害者請求の報酬を比較してみたいとおもいます。
弁護士が被害者請求の手続きを代理して行う場合,日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)の基準に基づいて契約することが多いと思います。
LACでは,被害者請求を含む事案簡明な自賠責保険の請求は,着手金・報酬方式ではなく,手数料方式で行うように規定されています。手数料は,自賠責保険金が150万円以下の場合は3万円,150万円を超える場合は2%と規定されています。
一方,行政書士の報酬をみると,着手金が3万円から5万円,報酬が自賠責保険金の15%から20%とするところが多いようです。
以下の表は,被害者請求の手続きの弁護士の手数料と行政書士の報酬を比較した表です(※自賠責保険金が150万円以下の場合3万円)。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険金 | 弁護士手数料(2%)※ | 行政書士報酬(20%) |
|---|---|---|---|
| 1級(別表Ⅰ) | ¥40,000,000 | ¥800,000 | ¥8,000,000 |
| 2級(別表Ⅰ) | ¥30,000,000 | ¥600,000 | ¥6,000,000 |
| 1級(別表Ⅱ) | ¥30,000,000 | ¥600,000 | ¥6,000,000 |
| 2級(別表Ⅱ) | ¥25,900,000 | ¥518,000 | ¥5,180,000 |
| 3級 | ¥22,190,000 | ¥443,800 | ¥4,438,000 |
| 4級 | ¥18,890,000 | ¥377,800 | ¥3,778,000 |
| 5級 | ¥15,740,000 | ¥314,800 | ¥3,148,000 |
| 6級 | ¥12,960,000 | ¥259,200 | ¥2,592,000 |
| 7級 | ¥10,510,000 | ¥210,200 | ¥2,102,000 |
| 8級 | ¥8,190,000 | ¥163,800 | ¥1,638,000 |
| 9級 | ¥6,160,000 | ¥123,200 | ¥1,232,000 |
| 10級 | ¥4,610,000 | ¥92,200 | ¥922,000 |
| 11級 | ¥3,310,000 | ¥66,200 | ¥662,000 |
| 12級 | ¥2,240,000 | ¥44,800 | ¥448,000 |
| 13級 | ¥1,390,000 | ¥30,000 | ¥278,000 |
| 14級 | ¥750,000 | ¥30,000 | ¥150,000 |
このように弁護士の手数料に比べて,行政書士の報酬の方が非常に高額であることが分かります。
弁護士費用特約があるの使えなかった!
このように,被害者請求の手続きに関する行政書士の報酬が非常に高額であるため,保険会社は,弁護士費用特約が付いていても行政書士の報酬を支払わないという方針をとるようになりました。
そうすると,弁護士費用特約があるにもかかわらず,行政書士の報酬の支払いに弁護士費用特約が使えず被害者の方が自己負担しなければならないというケースが非常に増えています。
さらに,東京海上日動火災は,平成27年10月1日以降の約款から,弁護士費用特約で報酬を支払う対象から行政書士を除外しています。この約款の規定は,行政書士の被害者請求の報酬について支払いを拒否することを明確にしたものと思われます。
被害者請求から弁護士に依頼しましょう
行政書士は,後遺障害認定があった後に,保険会社と示談交渉をすることができませんので,結局は,示談交渉を弁護士に依頼することになります。
行政書士の報酬がこれだけ高額で弁護士特約も使えないのであれば,被害者請求の手続きから弁護士に依頼した方が賢明ということになります。
むち打ち症で12級の後遺障害は認定されるか?
前回は,交通事故に遭ってむち打ち症などの神経症状しかない場合でも14級の後遺障害が認定されるので整形外科への通院を定期的にしましょうという話をしました。
今回は,神経症状で12級の後遺障害が認定されるケースについて話をしたいと思います。
逸失利益の労働能力喪失期間ので,むち打ち症の場合,12級で10年,14級で5年という話をよく聞きます。
そうすると,むち打ち症だけでも12級の後遺障害が認定されるケースがあるように思います。
12級の後遺障害が認定されるには症状の原因を裏付ける他覚的所見が必要です。
しかし,通常,医師がむち打ち症と言われるような頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断するのは他覚的所見がない場合です(ちなみに,他覚的所見とは画像や検査で異常が確認できることをいいます)。
そうすると,他覚的所見がない場合に診断される頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などのむち打ち症で,他覚的所見が必要な12級の後遺障害が認定されることはないのではないかという疑問が生じます。
これまで何件もの後遺障害の請求をしてきましたが,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群としか診断されていないケースで,12級の後遺障害が認定されることはないというのが実感です。
神経症状しかないときに12級の後遺障害が認定されるケース
では,痛みやしびれなどの神経症状しかないときに12級の後遺障害が認定されるのはどのような場合なのでしょうか。
代表的なのは骨折後に癒合不全が生じ神経症状が残ってしまったというケースです。
この場合,画像で骨折後の癒合が良好でないことを確認できるため,症状の原因を客観的に確認することができます。つまり,他覚的所見があるということになります。
次に神経症状12級が認定されるケースが多いと感じるのが、観血的整復固定術により骨折部をプレート等の固定材で固定して痛みやしびれの症状が残っているケースです。
このケースで難しいのが固定材を除去する場合です。
固定材を除去するのは、骨折部の癒合が良好な場合なので、固定材を除去すると後遺障害が認定されない可能性が高くなってしまいます。
まあ、後遺障害が認定されないということは後遺症が残っていないということなので悪いことではないのですが、賠償金は数百万単位で違ってきてしまうので、賠償という面では非常に悩ましいということになります。
以前に固定材を除去する前に症状固定にして後遺障害の認定を受けて、賠償を受けてから自費で固定材を除去する手術を受けたという事案を担当したことがあります。
結果的に後遺障害を認定されたからよかったものの、後遺障害が認定されなければ、賠償金は少ない、固定材除去の手術は自費になってしまうというリスクがあるので、お勧めできる解決方針ではありません。
そのため、基本的には医師と話をして固定材を除去するかを決めてくださいとアドバイスをしています。
また,外傷性の椎間板ヘルニアによって神経症状が生じたというケースでも12級の後遺障害が認定されることがあります。
ただし,椎間板ヘルニアと診断されていれば必ず12級の後遺障害が認定されるというわけではありません。
椎間板ヘルニアは加齢によって生じる経年性の椎間板ヘルニアもあり,経年性の椎間板ヘルニアでは後遺障害の認定はされないからです。
後遺障害は,交通事故に遭って外傷を負い,それによって症状が残った場合に認定されるものですので,これはやむを得ません。
後遺障害診断書に椎間板ヘルニアと記載されることは多いのですが,自賠責で外傷性の椎間板ヘルニアと判断されて12級の後遺障害が認定されるケースはあまり多くないように思います。
神経症状12級の後遺障害の認定のためには後遺障害診断書をしっかりと作成してもらおう
神経症状12級の後遺障害が認定されるためには、痛みやしびれの原因を確認できる他覚的所見が必要ですが、自覚症状を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらうことも重要です。
これは、どの後遺障害にも共通して言えることですが、自覚症状がしっかりと記載されていなかったために後遺障害が認定されなかったということがよくあります。
特に神経症状の場合は、痛みやしびれが出現する場面を限定して記載してしまい、後遺障害が認定されないということがあります。
後遺障害は、交通事故による怪我の症状が残存している状態ですので、普段は痛みはないけど、例えば、寒いときだけ痛みが出現すると後遺障害診断書に記載してしまうと、神経症状の後遺障害が認定されず非該当になってしまう可能性が高くなります。
神経症状の後遺障害が認定されるためには、神経症状が出現する場面を限定せずに、「骨折部に痛み、しびれ」と自覚症状の欄に記載した方がいいということになります。
神経症状12級の後遺障害の賠償金(示談金)の相場
神経症状12級の後遺障害は、後遺障害の慰謝料だけで290万円(弁護士基準)になります。
逸失利益は、労働能力喪失期間を10年間に制限されてしまうため、ほかの後遺障害に比べてそれほど高額にはなりませんが、それでも一般的には400万円から1000万円程度の金額になります(収入によって金額が変わってきます。)
これに、入通院の慰謝料が90万円から120万円になりますので、慰謝料と逸失利益だけで500万円から1200万円の賠償金(示談金)になります。
被害者の過失があるかなどの事案にもよりますが、保険会社から提示された賠償金(示談金)がここで説明した金額を下回るようであれば、示談せずに弁護士にご相談することをお勧めします(クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで賠償金(示談金)の適正金額について無料でアドバイスしています)。
解決実績
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
関連記事
むちうち(むち打ち症)でも後遺障害は認定される!
交通事故の中で最も多く発生する事故は追突事故です。
もっとも、追突事故で重度な後遺障害(後遺症)が残るような大怪我をすることはあまりありません。
追突事故で負う怪我は,一般的にむちうち(むち打ち症)といわれる頚椎捻挫や外傷性頚部症候群がほとんどです(むちうち(むち打ち症)の賠償については「むち打ち症」をご確認下さい。)。
むちうち(むち打ち症)は,頚部痛,頭痛,めまい,しびれなど様々な症状が出現します。
このような症状を神経症状といいます。
多くのケースでは,症状は軽く,時間が経てばいずれなくなります。
そのため,追突事故に遭って病院を受診すると,多くの医師はレントゲン検査だけをして,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断して,あまりしっかりとした検査や治療をしてくれないということが多くあります。
症状はあるけど,あまり効果のある治療を受けられないし,診察を受けるまでに待ち時間がかかるため,だんだんと病院に通院することが面倒になってきます。
しかし,頚部痛などの神経症状は,はっきりと目で見て確認することができませんのでほとんどのケースが自覚症状しかありません。
そのため、定期的に通院をしているという客観的事実が,後遺障害の認定において重要な意味を持ちます。
多くの方がむちうち(むち打ち症)のように神経症状しかない場合には,後遺症は残っていない、後遺障害は認定されないと考えてしまいます。
しかし、そのようなことはなく神経症状しかない場合でも14級の後遺障害が認定されるケースというのは多くあります。
神経症状14級の後遺障害の認定に必要なことやってはいけないこと
神経症状14級の後遺障害が認定されるためには,先ほど説明したように定期的に通院をしているという事実が重要になります。
具体的には,1ヶ月以上の間隔をあけずに6ヶ月以上、合計の通院日数が100日前後で整形外科に通院をしていれば14級の後遺障害が認定される可能性があります。
反対に神経症状で14級の後遺障害が認定されないケースというのは,①通院の間隔が1ヶ月以上空いている場合,②通院期間が6ヶ月未満の場合,③整形外科に通院していない場合です。
特に,③の整形外科に通院をしていない場合というのは,接骨院や整骨院に通院していたけど整形外科に通院していなかったという場合も含まれます。
自賠責では,接骨院や整骨院への通院は,後遺障害の認定との関係では通院していたという扱いにしないので注意が必要です。
損保会社は後遺障害が認定されないように治療費の支払いを6ヶ月未満で打ち切ってくる!
神経症状14級の後遺障害は、むちうち(むち打ち症)などの場合は、自覚症状しかないため、後遺障害の認定の条件として通院の実績が重要な意味を持ちます。
当然、損保会社も通勤の実績が多くなれば、神経症状14級の後遺障害が認定されやすくなるということを知っています。
以前は、損保会社の担当者の中にも、交通事故の被害に遭ったのっだから後遺障害が認定されないと被害者がかわいそうという気持ちがあったのか、6ヶ月以上の通院を認めて治療費の支払いに応じることもありました。
しかし、自動車の利用が減少し、それに伴い自動車保険の契約も減少しているという現状では、損保会社の担当者は、できる限り支払う賠償金を少なくしようとします。
そのため、今では損保会社の担当者は、追突事故などのそれほど重い事故でない場合、治療費の支払いは6ヶ月以内に打ち切ってくることが多いです。
最近では、さらに打ち切りまでの期間が短くなっており、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告してくる損保会社も多くなってきました。
このような場合、損保会社の治療費の打ち切りに合わせて通院を止めるのか、それとも健康保険に切り替えて治療費の3割分を自己負担して通院するのかは、非常に難しい判断です。
せっかく神経症状14級の後遺障害が認定される可能性があるのに、損保会社が治療費の打ち切りを言ってきて治療費を自己負担したくないといって通院を止めてしまうと、200万円近くを損してしまう可能性があります。
もちろん、症状がないのに賠償金のためだけに通院するのはよくありませんが、症状があって後遺障害が認定されるべき状態にあるのに通院を止めてしまうと適正な賠償を受けられないということになってしまいます。
症状が残っているのに損保会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、その後の通院について交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
神経症状14級の後遺障害の賠償金(示談金)は弁護士に交渉を依頼して増額できる!
神経症状14級の後遺障害は、後遺障害の慰謝料だけで110万円(弁護士基準)になります。
逸失利益は、労働能力喪失期間を5年間に制限されてしまうため、ほかの後遺障害に比べてそれほど高額にはなりません。
それでも一般的には70万円から150万円程度の金額になります(収入によって金額が変わってきます。)。
これに、入通院の慰謝料が90万円から100万円になりますので、慰謝料と逸失利益だけで250万円から350万円の賠償金(示談金)になります。
しかし、損保会社は、神経症状14級の後遺障害が認定されていても、慰謝料は弁護士基準の60%程度の金額でしか被害者に提示してきません。
それでも自賠責よりも高い金額になっていますといって被害者を納得させようとします。
また、逸失利益についても、むちうち(むち打ち症)で神経症状14級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失期間は5年に制限されてしまうことが多いのですが、損保会社は5年よりも短い2年から3年の労働能力喪失期間で逸失利益を計算していることがあります。
そうすると、神経症状14級の後遺障害が認定されていても、逸失利益は30万円から40万円くらいにしかならないことが多いです。
逸失利益は、収入によって金額が変わってきます。
しかし、神経症状14級の後遺障害が認定されている場合には、専業主婦でも年収380万円程度を前提として、逸失利益は85万円以上になります。
収入が多い方が神経症状14級の後遺障害が認定された場合には、逸失利益だけで150万円程度になることもあります。
神経症状14級が認定された場合には、損保会社から賠償金(示談金)の提示があってもすぐに示談してはいけません。
神経症状14級の後遺障害がい認定された場合の賠償金(示談金)は、弁護士に交渉を依頼することで増額できます!
被害者の過失があるかなどの事案にもよりますが、損保会社から提示された賠償金(示談金)がここで説明した金額を下回るようであれば、示談せずに弁護士にご相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所は神経症状14級の後遺障害が認定された被害者の方の賠償金(示談金)がどのくらいの金額になるのか無料で査定しております。
ぜひご相談ください。(クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで無料でご相談できます。)。
解決実績
50代男性 追突事故 後遺障害14級(むち打ち) 300万円で解決(2ヶ月で135万円増額)
事故直後からご依頼を受けて後遺障害14級(むち打ち)認定 320万円で解決
専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決
30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得
40代男性 左足首骨折 14級9号 585万円獲得(示談の提示金額よりも460万円も増額して解決!)
30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)
関連記事
後遺障害の異議申立てによって後遺障害等級が上がれば慰謝料が増額する!
後遺障害の異議申立てとは,認定された後遺障害等級に不服がある場合や後遺障害が非該当であった場合に,自賠責保険に対して不服を申し立てる制度です。
後遺障害は,1等級違うだけでも後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってきます。
以下の表は,弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額の一覧表です。
後遺障害等級が上がれば後遺障害慰謝料だけで数十万円から数百万円単位で金額が上がることがお分かりいただけると思います。
特に非該当の場合は、後遺障害慰謝料は0円になってしまうため、後遺障害の異議申立てによって後遺障害の認定を受けることが重要であることがお分かりいただけると思います。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
| 後遺障害1級 | 2800万円 |
| 後遺障害2級 | 2370万円 |
| 後遺障害3級 | 1990万円 |
| 後遺障害4級 | 1670万円 |
| 後遺障害5級 | 1400万円 |
| 後遺障害6級 | 1180万円 |
| 後遺障害7級 | 1000万円 |
| 後遺障害8級 | 830万円 |
| 後遺障害9級 | 690万円 |
| 後遺障害10級 | 550万円 |
| 後遺障害11級 | 420万円 |
| 後遺障害12級 | 290万円 |
| 後遺障害13級 | 180万円 |
| 後遺障害14級 | 110万円 |
| 非該当 | 0円 |
後遺障害の異議申立てによって後遺障害等級が上がれば逸失利益が増額する!
後遺障害の異議申立てによって非該当から等級が認定されたり、等級が上がった場合には逸失利益も増額します。
逸失利益は、年収に労働能力喪失率と中間利息を控除する係数であるライプニッツ係数をかけて計算します。
つまり、労働能力喪失率が高ければ逸失利益も高い金額になるということです。
当然、後遺障害が非該当の場合は、逸失利益は0円ですので、後遺障害の異議申立てによって後遺障害認定を受けることが非常に重要です。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
| 後遺障害1級 | 100% |
| 後遺障害2級 | 100% |
| 後遺障害3級 | 100% |
| 後遺障害4級 | 92% |
| 後遺障害5級 | 79% |
| 後遺障害6級 | 67% |
| 後遺障害7級 | 56% |
| 後遺障害8級 | 45% |
| 後遺障害9級 | 35% |
| 後遺障害10級 | 27% |
| 後遺障害11級 | 20% |
| 後遺障害12級 | 14% |
| 後遺障害13級 | 9% |
| 後遺障害14級 | 5% |
後遺障害の異議申立ては交通事故に強い弁護士に任せましょう!
ただし,後遺障害の異議申立てで非該当から認定を受けたり、等級を上げるのは簡単なことではありません。
後遺障害の認定基準を理解して、その認定基準を満たすような異議申し立てをする必要があります。
後遺障害の内容によっては、後遺障害が認定されるために医学的な検査や画像所見などが必要となります。
そのため,後遺障害の異議申立てにはそれぞれの後遺障害に関する知識と医学的な知識が必要となります。
また、異議申立ての根拠となる資料の収集には非常に手間も時間もかかりますので、被害者の方がご自身で後遺障害の異議申立てをするのはハードルが高いと思います。
交通事故に強くない弁護士は異議申立ては時間と手間がかかる、そもそも分からないからという理由で断ることもあります。
しかし,被害者の方が適切な賠償を受けるためには,適切な後遺障害の認定を受ける必要があります。
自分の症状に照らして認定された後遺障害では納得がいかないという場合には,後遺障害の異議申立ての手続をとることをお勧めします。
ただし、後遺障害の異議申立てを被害者自身が行うのはハードルが高いので、後遺障害の異議申立ては交通事故に強い弁護士に任せましょう!
当事務所は、むちうちで非該当から14級が認定された事案、高次脳機能障害で非該当から7級が認定された事案など後遺障害の異議申立てをして後遺障害が認定された事案が多くあります。
ぜひ、後遺障害の異議申立てはクロノス総合法律事務所にご相談ください!
解決実績
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)
30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得
関連記事
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。