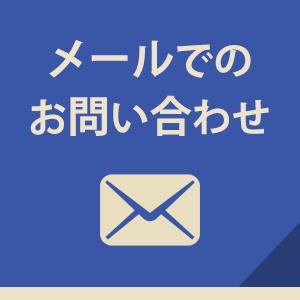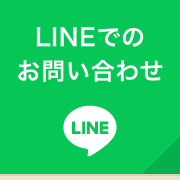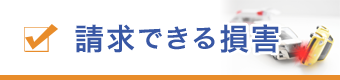横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》 - Part 6
敵(損保会社)は味方のふりをする
「敵は味方のふりをする」は,先日までTBS系列で放送されていたドラマ「小さな巨人」に出てくるセリフです(このドラマ面白くて毎週見てました。平井堅さんの主題歌もよかったですよね)。
このセリフを聞いたときに,交通事故の加害者側の損保会社にもまさに「敵は味方のふりをする」というタイプの担当者がいるなと思ってしまいました。
加害者側の損保会社の担当者の多くは,できるだけ被害者への支払額を少なくしようとしますので,通常は,被害者の方に冷たく,治療費を途中で打ち切ったり,休業損害を支払わなかったりということをしてきます。
このような担当者は,被害者も「敵」だと感じるようで,相談に来られた被害者の方の中には,お金はどうでもいいので,損保会社の担当者をぎゃふんと言わせたいとおっしゃる方がいます(ちなみに,このような担当者をぎゃふんと言わせるのは,最大限に賠償金を獲得することですのでお金は重要です)。
被害者の方が損保会社の担当者を「敵」だと感じている場合には,徹底的に交渉することができますし,被害者の方も裁判にして最大限有利な解決をして欲しいと言ってくれますので,弁護士としては非常にやりやすいです。
一方,損保会社の担当者の中には,あたかも被害者の方の味方ですという顔をして,示談交渉にあたる担当者がいます。実際は,できる限り被害者に支払う賠償金を低額にしようとして味方のふりをしているだけですので決して被害者の味方ということはないのですが,このような担当者は,お金以外の部分では被害者の方に寄り添った言動をしますので,被害者の方は,すっかり味方と勘違いしてしまいます。
被害者の方が担当者を味方と勘違いしてる場合は,弁護士の所に相談に来られても,●●さん(担当者)はすごくいい人だったので裁判までは考えてません,と言ったりすることがあるので,弁護士としては困ってしまいます。
でも,損保会社の担当者が真に被害者の方の味方をすることはないと断言できます。味方のように思えても,それは被害者の方の賠償金を低額に抑えるために味方のふりをしているだけで実際は「敵」なのです。
まさに「敵(損保会社)は味方のふりをする」です!
簡単に示談書にサインしないようにしましょう
あたかも敵という感じの担当者であれば,被害者の方も簡単に示談書にサインすることはないのですが,味方のふりをしている担当者の場合,きっと多くの被害者が低額な賠償金で示談書にサインをさせられているのではないかと思います。
損保会社の担当者は,損保会社の従業員ですので会社の利益のために行動します。支払う賠償金をできるだけ低額にしようとすることは会社の利益になることですので,損保会社の従業員として正しい行為です。
逆に言えば,真に被害者の味方になって高額な賠償金を支払う担当者は損保会社の従業員としては失格です。
なので,どんなに被害者の方に親身になっていたとしても,損保会社の社員が真に被害者の味方になることはないのです。
損保会社の担当者が被害者の方に提示した示談書は,すべてにおいて弁護士が介入する場合よりも低額な賠償金額になっているはずです。ですので,簡単に示談書にサインしないようにしましょう。
過失とは?
通常、交通事故は、事故の当事者の過失を原因として発生するのが一般的です。
過失が何かというと、法的な用語を使えば、客観的注意義務に違反することをいうのですが、非常にわかりにくいですね。
例えば、自動車の運転手が前方を見ないで運転した場合、前方の車両に追突してしまったり、交差点で別の車に衝突してしまったりします。また、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断すれば、青信号で走行してきた自動車に轢かれてしまいます。
事故の発生を防止するために、自動車の運転手には前方に注意して運転する義務が課されていますし、歩行者には赤信号のときに横断歩道を横断してはならないという義務が課されています。
このように、事故の発生を防止するために、運転手や歩行者等に一般的にまたは法的に課されている義務に、不注意によって反することを過失といいます。
過失割合とは?
例えば、信号機のない交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の場合、両方の自動車の運転手に過失があります。このような事故の場合、どちらが優先道路を走行していたか、どちらが一時停止規制のある道路を走行していたかといった事情によって、それぞれの過失の大きさが違ってきます。
過失が大きい小さいだけでは、交通事故の賠償の解決ができませんので、便宜上、過失の大きさを数字で示すことになります。事故の当事者の過失の大きさを数字で示したものを過失割合といいます。
先ほどの交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の例で、一方の道路に一時停止規制がある場合で説明してみます。
この場合、一時停止規制のある道路を走行していた自動車の運転手の方の過失が大きくなるのですが、一時停止規制のない道路を走行していた自動車の運転中にも前方左右の不注意を理由として一定程度の過失があります。
この場合、それぞれの過失割合は、一時停止規制のある運転手が85、一時停止規制のない運転手が15という数字になります。
この数字は、裁判所が多くの交通事の故事例を分析して事故の態様ごとに過失割合を分類した書籍を参考にしています。実務では、この書籍を参考にして過失割合について、事故の当事者が主張をすることになります。
過失割合はどのように決まるか?
過失割合は、先ほど説明したように事故の態様ごとに過失割合を類型化した書籍を参考に決めています。しかし、すべての事故が事故の態様だけで過失割合で決まってしまうかというとそうではありません。
先ほどの例でいうと、一時停止規制のある運転手の過失割合は85、そうでない運転手の過失割合は15になりますが、一時停止規制のある運転手が制限速度40kmの道路を時速60kmで走行して事故を起こした場合、一時停止規制のある運転手の過失割合は85+10となり95になります。
このようにそれぞれの事故の具体的事情によって過失割合は増減することになります。もちろん、スピード違反だけでなく、飲酒運転や携帯電話を使いながら運転していたなどの事情も過失割合を増加させる事情になります。
結局、過失割合は事故の態様を基本に、具体的な事情を加味して決定するということになります。
過失相殺をして賠償額を決定する
過失割合が決定した後、被害者に過失があれば、損害額から被害者の過失割合に相当する金額を控除して賠償額を決定します。これを過失相殺といいます。
損害額が1000万円で被害者の過失割合が15%の場合、過失相殺後の賠償金は以下の計算になります。
1000万円×15%=150万円
1000万円-150万円=850万円
保険会社が過失相殺をしない場合もあるけど…
このように被害者に過失があれば、過失割合に従って過失相殺をしますので、当然、過失がない場合に比べて、被害者が受け取る賠償金は低額になります。
そうすると、できるだけ賠償金を低額に抑えようとする保険会社は、過失相殺をした上で賠償金を提示するのが一般的です。
ところが、その保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示してくることがあります。このような保険会社はいい保険会社ですね!っていうことではありません。
被害者に過失があるのに保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示するケースは、必ず、慰謝料や逸失利益などの損害額を非常に低く見積もって提示しています。
つまり、過失相殺をした後の賠償金を下回る賠償金を提示すれば、保険会社が損をすることはありませんので、過失相殺をしなくても何も問題がないということになります。
被害者の方は、交通事故の被害にあっているのに、自分に過失があるといわれると心情的に納得がいきません。保険会社は、被害者のこのような心情を利用しているわけです。被害者の方の過失は0にして被害者の方を納得させて、保険会社の提示する低額な賠償額で示談させようとしているのです。
ほとんどの交通事故では、交通事故の当事者に過失があります。そのため、多くのケースでは過失相殺をして賠償の解決をすることになります。
ですので、保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示している場合は、慰謝料や逸失利益などの損害額を低く提示されていると疑った方が賢明です。
弁護士に依頼したら慰謝料が増額する
交通事故に遭って怪我をしたら慰謝料を請求できるということは多くの方がご存知だと思います。
交通事故の慰謝料には、交通事故の被害に遭って病院に入院したり通院したことに対して支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)と自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
慰謝料の詳しい内容については、「交通事故の慰謝料」をご覧ください。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)も後遺障害慰謝料も自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
金額は、自賠責基準≧任意保険基準>弁護士基準の順番で高くなります。
加害者側の保険会社は、慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で計算して提示してきます。
保険会社が慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で提示してきたときに、被害者の方がご自分で慰謝料の増額の交渉をすることも可能ですが、おそらく、弁護士基準まで増額することは難しいと思います。
慰謝料を弁護士基準まで増額するには、やはり弁護士が交渉の窓口にならなければ保険会社も応じることはありません(まあ「弁護士基準」というくらいなので当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが)。
ちなみに、任意保険基準というのは保険会社の内部的な基準なので、一般的に公開されているものではありませんが、自賠責基準の後遺障害慰謝料と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較すると金額に大きな差があることが分かります。
慰謝料を増額したい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
| 事案 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 死亡※ | 400~1350万円(350~1350万円) | 2000~2800万円 |
| 後遺障害1級(要介護) | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 後遺障害2級(要介護) | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 後遺障害1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 後遺障害2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 後遺障害3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 後遺障害4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 後遺障害5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 後遺障害6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 後遺障害7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 後遺障害8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 後遺障害9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 後遺障害10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 後遺障害11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 後遺障害12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 後遺障害13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
| 後遺障害14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※死亡慰謝料は、家族内での本人の立場や扶養家族の有無によって変わってきます。
※2020年3月31日以前に発生した事故はかっこ内の金額になります。
弁護士に依頼したら賠償金(特に慰謝料と逸失利益)が増額する
弁護士に依頼したら増額するのは、慰謝料だけではありません、慰謝料以外の賠償金も増額します。
特に、賠償金の中で大きな割合を占める逸失利益が増額します。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったり、死亡したことによって将来られなくなった収入を填補する損害項目をいいます。
実は、慰謝料よりも逸失利益の方が金額が高くなることが多いので、弁護士に依頼したメリットは、慰謝料よりも逸失利益の方が大きいと思います。
逸失利益の詳しい内容については、「後遺障害逸失利益」と「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。
後遺障害逸失利益と死亡による逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
【後遺障害逸失利益の計算方法】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率期間に対応するライプニッツ係数
【死亡による逸失利益の計算方法】
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
保険会社は、上記の計算方法のいずれかの項目もしくはすべての項目を低く見積もって、弁護士基準よりも低額な逸失利益を提示してきます。
逸失利益については、あまり一般的でないということもあり、被害者の方がご自分で保険会社相手に交渉するのは難しいといえるでしょう。
逆に言うと、逸失利益については、弁護士に依頼すれば増額できるといえるでしょう。
弁護士費用はどうすればいいの?
弁護士に依頼する際の最大の懸念事項といえば弁護士費用だと思います。
弁護士費用は、通常、着手金と報酬という費用体系になっています。確かに、弁護士費用は決して安い金額ではありません。
しかし、もし、ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円までの弁護士費用は、弁護士費用特約で支払ってもらうことができます。
もちろん、弁護士費用特約を利用しても保険の等級は上がりませんので、翌年の保険料が上がってしまうという心配もいりません。
ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険会社と契約した後に保険会社から送られてきた保障内容の案内などに載っていますので、確認をしてみて下さい。
また、自動車保険に入っていなくても、弁護士費用保険に入っていれば一定額は弁護士費用保険から支払ってもらうことが可能です。
保険に全く入っていなかったとしても、現在は、交通事故については、多くの弁護士が相談料も着手金も0円としていますし、報酬については、保険会社から支払われる賠償金から支払うことができますので、被害者の方の持ち出しがなく弁護士に依頼することができると思います。
当事務所でも、相談料も着手金も無料にした弁護士費用としていますので、「弁護士費用」をご覧下さい。
どのような弁護士を選ぶべきか?
では、どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。
実は、保険会社の提示する慰謝料や賠償金を増額することは、どの弁護士でも可能です。
しかし、交通事故では、例えば、後遺障害の存在が争われていたり、過失割合が争われたりする場合に、裁判で解決するしかないというケースが多くあります。
裁判になれば、加害者側は保険会社の顧問弁護士が裁判を担当することになりますが、保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に大変精通しています。
そのため、裁判になっても保険会社の顧問弁護士と同じくらい、もしくはそれ以上に交通事故の裁判に精通した弁護士でないと裁判になったときに負けてしまいます。
また、裁判になれば弁護士費用や遅延損害金がつきますので、示談に比べると賠償金の総額が大きくなりますので、場合によっては、示談で解決するのではなく、積極的に裁判を起こして解決した方が被害者の方にとってメリットが大きいというケースも多くあります。
そうすると、交通事故の被害者の方が依頼すべき弁護士というのは、交通事故の裁判に精通した弁護士ということになります。
死亡事故の逸失利益は生活費を控除して計算する
死亡事故の逸失利益は,賠償金の大部分を占めますのでどのように計算をするかをしっかりと理解しておく必要があります。死亡事故の逸失利益は以下の計算式で計算をします。
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
生活費控除率とは、死亡したことによって支出を免れた生活費を控除するための数値になります。
後遺障害の逸失利益との違いは、死亡事故の逸失利益は生活費を控除して計算するという点です。
生活費は、多くの方が仕事をして得た収入から支出しています。
重度の後遺障害が残っても、当然ですが食事や住居費などの生活費はかかります。
一方、交通事故によって亡くなってしまった場合には、その後の生活費の支出は免れることになります。
そのため、死亡事故の逸失利益は生活費を控除して計算することになるのです。
死亡事故一般については,「死亡で知っておくべき知識」をご覧ください。
会社員の逸失利益を計算してみよう
基礎収入は,会社員の場合は事故前年の年収になります。
例外的に,年俸制の契約で年収が決まっていたのに,交通事故によって事故に遭った年の年収が下がった場合には,事故に遭った年の年俸を基礎収入とすることができます。
具体的に説明すると,事故前年の年収が850万円で,事故に遭った年の年収が年俸制の契約で1000万円決まっている場合,基礎収入は850万円ではなく1000万円とすることが可能です。
生活費控除率は被害者の家庭内での立場などによって異なります。生活費控除率の具体的な数値は以下のとおりです。
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
| 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |
| 年金部分 | 30%~50% |
労働能力喪失期間は事故当時の年齢から67歳までの期間になります。
ただし,高齢で67歳までの期間が平均余命の2分の1よりも短い場合には,平均余命の2分の1が労働能力喪失期間になります。
ライプニッツ係数は労働能力喪失期間によって変わりますので具体的な事例の中で見ていきましょう。
また,ライプニッツ係数は,以前は,民法の法定利率と同じく年5%で中間利息を控除する数値でしたが,現在は,年3%で中間利息を控除する数値になっています。
以下の例では年3%で中間利息控除をする前提のライプニッツ係数の数値で計算しています。
事故当時40歳で妻と子供2人を持つ男性で事故前年の年収が800万円の場合の逸失利益は1億円以上
事故当時40歳で妻と子供2人を持つ男性で事故前年の年収が800万円だった場合を例に会社員の逸失利益の具体的な計算についてみてみましょう。
基礎収入800万円
生活費控除率 30%(被扶養者が2人以上)
労働能力喪失期間 27年(40歳から67歳までの27年) ライプニッツ係数 18.3270
800万円×(1-30%)×18.3270=1億236万1200円
中間利息控除の年利が3%になったことで逸失利益が非常に高額になるようになりました。
事故当時25歳の独身男性(大卒)で年収400万円の場合の逸失利益は約8000万円
今度は、事故当時25歳、大卒、年収400万円の独身男性を例に会社員の逸失利益の具体的な計算についてみてみましょう。
基礎収入は,400万円と思ってしまいますが,この場合400万円ではありません。
30歳未満の若年労働者の場合,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とします。
男性の大卒の場合671万4600円(令和元年)になります。そうすると,この場合,基礎収入は671万4600円になります。
基礎収入 671万4600円
生活費控除率 50%(独身男性)
労働能力喪失期間 42年(25歳から67歳までの42年) ライプニッツ係数 23.7014
671万4600円×(1-50%)×23.7014=7957万2710円
民法改正によって中間利息控除をするための年利が変更になったことによって逸失利益が民法改正前(2020年3月31日以前)よりも高額になる!
2020年4月1日に民法が改正されて、法定利率がそれまでの年5%から現状は3%に変更になりました(今後、法定利率は3年ごとに見直しされます。)。
これに合わせて中間利息控除の利率も現状3%に変更になったため、中間利息として控除される金額が民法改正前(2020年3月31日)に比べて少なくなりました。
中間利息として控除される金額が少なくなったということは、その分、逸失利益が高額になるということです。
2020年4月1日以降に発生した交通事故については、改正後の民法が適用されますので、逸失利益の計算をしっかりとしましょう。
亡くなった被害者の大事な賠償金ですので、逸失利益を含めて賠償金が総額でいくらになるのかはしっかりと確認した上で解決するようにしましょう。
実際にどれくらいの逸失利益、賠償金になるのかは弁護士に相談しよう!
会社員の死亡事故は、中間利息控除の数値が小さくなったことで逸失利益が非常に高額になりました。
それに伴って賠償金も非常に高額になり、収入が高く、扶養家族がいる被害者の場合、賠償金の総額は1億円を超える可能性もあります。
実際にどれくらいの賠償金になるのかは、それぞれの事情によって違ってきますので、保険会社から提示された賠償金が高額であったとしても必ず弁護士に相談しましょう!
交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのか無料でお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。
解決実績
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
関連記事
交通事故には2種類の慰謝料があることを知っておこう!
交通事故に遭ったら慰謝料がもらえるかもしれないということは多くの方が知っていると思います。
そのため、インターネットでも交通事故の被害者向けの広告で慰謝料を増額します!といった内容のものが多くあります。
でも、交通事故にあったら支払ってもらえる慰謝料って何でしょうか?
実は、交通事故の慰謝料には,入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類があります。
この2種類の慰謝料は、どれくらい通院したのか、後遺障害が残ったのかどうかによって、もらえるのか、もらえるとしてもどのくらいの金額になるのか違ってきます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故の被害に遭って病院に入院したり通院したことに対して支払われる慰謝料です。
多くの方が交通事故に遭ったときにもらえる慰謝料は、おそらく入通院慰謝料(傷害慰謝料)のことをイメージしていると思います。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故に遭って怪我をして通院をすれば、基本的には発生します。
入通院慰謝料の名称のとおり、入院日数、通院日数、通院期間を基準に金額を算定します。
注意が必要なのは、保険会社と弁護士では入通院慰謝料の計算基準が異なるという点です。
特に入院はしてなくて通院しかしていない場合に注意が必要です。
保険会社は、通院に対する慰謝料を算定するときに実際の通院日数を基準とします。
これは自賠責が通院日数を基準に通院慰謝料を算定するためです。
一方、弁護士は、通院日数ではなくて通院期間を基準に通院慰謝料を算定します。
通院日数を基準とする場合、実際に通院した日だけしか慰謝料の対象になりません。
通院期間を基準とする場合、通院していない日も慰謝料の対象になります。
当然、通院していない日も慰謝料の対象に含める通院期間を基準とした方が通院慰謝料は高額になります。
保険会社は、被害者に賠償金の提示をするときには必ず通院日数を基準に慰謝料の算定をしています。
そのため、弁護士基準で算定しなおせば、保険会社が提示した入通院慰謝料(傷害慰謝料)よりも必ず高い金額になります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、通院日数ではなく通院期間を基準に算定すると覚えておきましょう。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と違って交通事故に遭って怪我をしてももらえないこともあります。
後遺障害慰謝料は、自賠責で後遺障害が認定されなければ支払ってもらえない慰謝料です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級によって違ってきます。
以下の表は、自賠責の後遺障害慰謝料になります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 (2020年4月1日以降) | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 (2020年3月31日以前) |
| 後遺障害1級(常時介護) | 1,650万円(1,850万円) | 1,600万円(1,800万円) |
| 後遺障害1級(随時介護) | 1,203万円(1,373万円) | 1,163万円(1,333万円) |
| 後遺障害1級 | 1,150万円 (1,350万円) | 1100万円 (1,300万円) |
| 後遺障害2級 | 998万円 (1,168万円) | 958万円 (1,128万円) |
| 後遺障害3級 | 861万円 ( 1,005万円 ) | 829万円 (973万円) |
| 後遺障害4級 | 737万円 | 712万円 |
| 後遺障害5級 | 618万円 | 599万円 |
| 後遺障害6級 | 512万円 | 498万円 |
| 後遺障害7級 | 419万円 | 409万円 |
| 後遺障害8級 | 331万円 | 324万円 |
| 後遺障害9級 | 249万円 | 245万円 |
| 後遺障害10級 | 190万円 | 187万円 |
| 後遺障害11級 | 136万円 | 135万円 |
| 後遺障害12級 | 94万円 | 93万円 |
| 後遺障害13級 | 57万円 | 57万円 |
| 後遺障害14級 | 32万円 | 32万円 |
※かっこは被扶養者がいる場合
以下の表は、弁護士基準の後遺障害慰謝料になります。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
| 後遺障害1級 | 2800万円 |
| 後遺障害2級 | 2370万円 |
| 後遺障害3級 | 1990万円 |
| 後遺障害4級 | 1670万円 |
| 後遺障害5級 | 1400万円 |
| 後遺障害6級 | 1180万円 |
| 後遺障害7級 | 1000万円 |
| 後遺障害8級 | 830万円 |
| 後遺障害9級 | 690万円 |
| 後遺障害10級 | 550万円 |
| 後遺障害11級 | 420万円 |
| 後遺障害12級 | 290万円 |
| 後遺障害13級 | 180万円 |
| 後遺障害14級 | 110万円 |
| 非該当 | 0円 |
このように自賠責と弁護士基準では後遺障害慰謝料の金額は大きく異なります。
保険会社は後遺障害慰謝料については、自賠責と同じ金額か自賠責を少し上回る金額しか提示してきません。
そのため、後遺障害が認定されている事案では弁護士に交渉を依頼すれば後遺障害慰謝料は増額する可能性が高いです。
詳細については「交通事故の慰謝料」をご覧下さい。
慰謝料の増額とは?(慰謝料の増額には2つの意味がある!)
交通事故の賠償に関するホームページを見ていると「慰謝料を増額します!」という広告文が見られます。
実は,慰謝料の増額には2つの意味があるということを知っておく必要があります。
1つ目の意味は,保険会社の提示する慰謝料を増額するという意味です。
通常,保険会社は,弁護士基準を大幅に下回る慰謝料しか提示しません。
例えば,後遺障害14級の弁護士基準の慰謝料は110万円です。ところが,保険会社は50万円くらいの金額しか提示してきません。
保険会社との交渉に弁護士が入ると,保険会社は50万円で提示していた慰謝料を80万円から90万円まで増額します。
これをみると,弁護士が入ったことにより慰謝料が増額しているので,「慰謝料を増額します!」という広告文に嘘はありません。
しかし,弁護士の仕事としては不十分です。
弁護士の仕事としては慰謝料を弁護士基準まで上げて,初めて保険会社の提示する慰謝料を増額したことになります。
もちろん,被害者に有利な過失割合が提示されているなどの事情がある場合には、弁護士基準を下回る慰謝料で解決することもあると思いますが,それはあくまでも例外的なケースです。
2つ目の意味は,弁護士基準の慰謝料よりも増額するという意味です。
例えば,一家の支柱が死亡した場合の慰謝料は2800万円ですが,加害者に飲酒運転をしてたというような事情がある場合,これを慰謝料増額事由として,通常2800万円の慰謝料を3000万円に増額するようなケースです。
飲酒運転以外には,慰謝料増額事由として過度な速度違反やひき逃げなどが上げられます。
ほかにもいろいろなケースがありますので,慰謝料増額事由があるとお考えの場合は,交通事故を専門にしている弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士基準の慰謝料よりも増額するというのは弁護士が入ってもそう簡単なことではありません。
少なくとも,示談では保険会社は具体的な事情は考慮せず、定型的な解決でしか応じませんので,弁護士が入っても弁護士基準の慰謝料よりも増額して解決することはかなりレアケースです。
そうすると,弁護士基準の慰謝料よりも増額するような事情がある場合には,裁判で解決する必要あります。
慰謝料の増額は交通事故専門の弁護士に相談しましょう!
交通事故に遭ったら慰謝料がもらえる可能性があります。
しかし、慰謝料の種類や慰謝料増額の意味を知らないと、適正な金額の慰謝料をもらえないおそれがあります。
保険会社は、被害者に対して、基本的には慰謝料は自賠責と同じくらい、もしくは自賠責を少し上回るくらいの金額しか提示してきません。
弁護士が入れば、基本的には保険会社は被害者に提示していた慰謝料よりも高い金額を提示してきます。
ただし、保険会社は弁護士基準の70%から80%くらいしか提示してきませんので、弁護士が入って提示された金額が弁護士基準で計算した慰謝料の100%であるのかは確認が必要です。
弁護士基準で計算した100%の慰謝料を獲得するためには、保険会社が示談で応じない場合には、裁判や裁判以外の解決機関(ADR)を利用する必要があります。
いずれにしろ、慰謝料の増額については、交通事故専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所では保険会社から提示された慰謝料が適正な金額なのか無料で査定しておりますのでご相談ください。
死亡交通事故の解決方法
大切なご家族を死亡交通事故で亡くしてしまったら、ご家族はどうすればいいのか分からないはずです。
何が行われているのか分からないまま刑事裁判が終わってしまい、そのあとは保険会社から賠償金の提示があってどうしたらわからないという理由でご相談いただくことも多くあります。
ここでは、交通事故の死亡事故の民事の解決方法について解説します。
死亡交通事故の民事の解決方法は,以下の4つの解決方法が考えられます。
・示談(裁判外の解決機関を含む)で解決 ・裁判で解決 ・被害者側の自動車保険の人身傷害保険を取得して解決 ・自賠責保険だけ取得して解決
死亡交通事故は示談で解決することは少ない
示談での解決のメリットは,交通事故の解決方法で説明をした通り早期に解決できるという点です。
死亡交通事故で早期に解決をしないといけないケースというのは,家族の生活を支えていた一家の主が被害者になり,早期に解決をしなければ残された家族の生活が立ち行かなくなってしまうというような場合です。
しかし,通常,一家の主の場合には生命保険がかけられていることが多いので,家族の生活が立ち行かなくなるケースというのはそれほど多くありません(もちろん,賠償金は生命保険とは別で請求することができます)。
そもそも、一家の主の場合は、自賠責保険から3000万円がおりますので、自賠責保険を取得してから裁判で解決するという方法をとることもできます。
ほかに死亡交通事故で示談で解決をした方がいいケースは,保険会社が通常よりは有利な過失割合を提示していたり,有利な逸失利益を提示しているような場合になります。
あまりあるケースではありませんが,まれにこのようなこともあります。
そうすると,実は,死亡交通事故については示談で解決した方がいいケースというのはほとんどなく示談で解決することは少ないと思います。
死亡交通事故は裁判で解決することで最大限の賠償金を獲得できる
このように死亡交通事故の場合,示談で解決した方がいいケースというのはあまりないので,基本的には裁判で解決をした方がいいでしょう。
裁判で解決をする場合,弁護士費用が損害額の10%で認められ,遅延損害金が事故日から賠償金の支払いまで年3%もしくは5%※で認められるので,トータルの賠償金が示談で解決する場合と比較して高額になります。※交通事故の発生時期によって異なります。
ただし,死亡事故の場合,過失割合と逸失利益という賠償金の計算に大きくかかわってくる事項が争点となりやすいです。
特に過失割合はほとんどの死亡事故で争点になると思いますので、死亡事故を裁判で解決する場合には、交通事故を専門としている弁護士に依頼した方がご遺族にとってよりよい解決ができます。
弁護士に依頼する場合でも,弁護士特約があれば家族の負担になる事もないですし,弁護士特約がなかったとしても,着手金を不要としている弁護士もいるので,費用面での心配はそれほどないと思います(クロノス総合法律事務所の弁護士費用)。
また交通事故で亡くなった被害者の無念を裁判で解決することによって晴らすことができる、ご遺族も裁判で解決することによって被害者にできる限りのことをやってあげたというお気持ちを感じることができるという面もあります。
交通事故で亡くなった被害者のためにも、死亡事故は最大限の賠償金を獲得できる裁判で解決した方がいいでしょう。
被害者側の自動車保険の人身傷害保険を取得して解決
被害者側が自動車保険に入っている場合、交通事故の被害者となった場合でも使うことができる保険があります。
被害者の損害を補償する保険としては人身傷害保険が代表的な保険になります。
死亡交通事故の場合、人身傷害保険だけを取得して解決するのではなく、裁判を起こして加害者から賠償金を取得するとともに人身傷害保険を取得して解決することになります。
人身傷害保険は、通常、自損事故(加害者がいない自分に責任のある事故)を起こした場合でも、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料を支払ってくれるという保険になります。
自分に責任のある場合でも保険金を支払ってくれるという保険ですので、加害者がいる交通事故であっても被害者に過失がある場合に被害者の過失分に相当する損害について保険金を支払ってくれます。
人身傷害保険を活用することで、裁判で認められた被害者の損害額の全額を取得することができるようになりますので、実質的には過失がない場合と同じ解決を実現できることになります。
人身傷害保険の活用は、交通事故の専門的な知識が必要ですので交通事故を専門としている弁護士に相談しましょう。
自賠責保険だけ取得して解決
自賠責保険だけ取得して解決をするケースというのは,賠償金の総額が自賠責の死亡事故の限度額である3000万円を超えないことが明らかな場合です。
もちろん、人身傷害保険がある場合は自賠責保険だけを取得して解決ということはありません。
しかも、自賠責保険と人身傷害保険の請求の順番を間違えてしまうと、数千万単位で最終的に取得できる金額が違ってくるケースもあるので注意が必要です。
よくある自賠責保険だけ取得して解決するケースとしては,トータルの賠償金が6000万円以下で,過失が少なくとも50%以上あるようなケースです。
このようなケースでは,裁判を起こしたとしても賠償金の総額が自賠責の限度額である3000万円を下回る可能性がありますので,自賠責で3000万円を取得して解決する方が取得できる金額が高くなります。
ただし、裁判で解決する場合には、弁護士費用と遅延損害金が加算されますので、裁判で解決した方がいいのか、それとも自賠責保険だけ取得して解決した方がいいのかは、被害者の損害額や過失割合をしっかりと検討する必要があります。
亡くなった被害者の過失が大きい事故になりますと、保険会社は自賠責の限度額でしか賠償金の提示をしてこないことがあります。
これで示談してしまうと、実質的には自賠責保険だけを取得して解決したのと違いはありません。
保険会社の中には、ご遺族に自賠責保険の請求書類だけを送ってきてそれ以降の対応を一切しないという保険会社もあります。
本当に自賠責保険だけを取得して解決すべき事案なのかは、交通事故を専門としている弁護士に相談してから判断した方がいいです。
死亡交通事故の相談は交通事故を専門にしている弁護士に相談しましょう
死亡交通事故は、交通事故の内容、被害者の属性、被害者側の保険の有無などの事情によって最終的に取得できる金額が大きく違ってきます。
大切な家族がなくなってしまったのに最大限の賠償金や保険金を獲得できないのでは、交通事故の二次被害に遭ったといっても過言ではありません。
交通事故の死亡事故は、弁護士を入れて裁判で解決した方がいいケースが多いので,交通事故を専門にしている弁護士に相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所では死亡交通事故の解決実績が豊富です。
死亡交通事故は、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けています。
また着手金も無料で報酬も獲得した賠償金からいただいていますので自己負担は実質的に0円です。
解決実績
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
関連記事
交通事故の裁判とは?
交通事故の裁判には刑事裁判と民事裁判があります。
刑事裁判は、加害者となった運転手に刑事罰を与える必要があるか、また、与える必要がある場合にはどのような刑事罰を与えるのが妥当であるのかを判断する裁判になります。
刑事裁判の場合、当事者は被告人である加害者と検察官でであり、被害者は当事者となりません。
ただし、交通事故によって被害者が死亡や重大な障害を負った場合には、被害者参加制度によって被害者のご家族が加害者の刑事裁判に参加して量刑に関する意見等を述べる機会が設けられています。
一方、民事裁判は、通常は、被害者が原告となって被告である運転手や自動車の保有者に対して損害賠償を求める裁判になります。
刑事裁判と違い、被害者や被害者の家族が裁判の当事者となります。
また、交通事故の被害者と加害者以外に自動車の所有者が裁判になります。
例えば、夫が所有者となっている自動車で妻が事故を起こして加害者になってしまったような場合に、夫も妻とともに被告になります。
これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で、自動車の所有者などを「運行供用者」として、運行供用者にも事故の責任を認めているからです。これを運行供用者責任といいます。
交通事故の刑事裁判
交通事故の刑事裁判は、先ほど説明したように、被害者や被害者の家族は、裁判の当事者となりません。
被害者参加という制度を利用して加害者の刑事裁判に参加するしかありません。
被害者参加については、通常、捜査や裁判を担当する検察官からご家族に参加の意思確認があります(基本的に被害者本人は死亡もしくは重大な障害を負っているので被害者として参加することはほとんどありません。)。
検察官の中には、被害者参加があると手続きが増え面倒なためか嫌がる検察官もいます。
その際、検察官は、被害者参加をしても量刑に影響はないという話をするそうです。
被害者の家族としては、検察官から被害者参加に参加しても量刑に影響がないと言われてしまうと、被害者参加しなくてもいいという思いになってしまいます。
しかし、被害者参加では、刑事裁判で提出された証拠のすべてを閲覧することができるのでできる限り参加した方がいいと思います。
非常に不思議なことではあるのですが、刑事裁判が終わってから刑事裁判に提出された証拠の閲覧請求をすると、被害者や加害者のプライバシーに関することなどが黒塗りにされてしまうのです。
時には、当事者の過失を決めるような重大な記載部分が黒塗りにされているということもあります。
死亡事故や重大な障害を負うような事故の場合、過失が問題となり刑事裁判に提出された証拠の記載内容が非常に重要となります。
そのため、刑事裁判のときに被害者参加をして黒塗りにされていない状態の証拠を確認しておくということが極めて重要になります。
もちろん、裁判所に対して加害者に対する処罰感情をきちんと伝えるということも重要ですので、やはり被害者参加できるのであればしておいた方がいいことは間違いありません。
被害者の家族の方が参加の意思を強く示せば検察官も必ず応じてくれます。
交通事故の民事裁判
交通事故の民事裁判は、被害者が加害者や自動車の所有者に対して賠償金を請求する裁判ですので、主に、交通事故によってどのような損害が発生したのか、損害額はいくらなのか、当事者に過失はあるのかというような点を裁判所が判断して、加害者や自動車の所有者に対して賠償金の支払いを命じる判決を下します。
ただし、多くの場合、加害者も自動車の所有者も任意保険に入っていますので、交通事故の民事裁判では、被告側の弁護士は保険会社の顧問弁護士が担当することになります。
保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に精通していますので、被害者の方も裁判をする場合には(裁判をしない場合でも)交通事故の裁判に精通した弁護士に依頼する必要があります。
そうしなければ、後遺障害や過失などが争点になった場合に、保険会社の顧問弁護士に太刀打ちできずに、適正な賠償金を獲得できなくなってしまうというおそれがあります。
また、交通事故の民事裁判は、示談や裁判外の解決機関での解決と違って、弁護士費用や遅延損害金が認められるというメリットがあります。
弁護士費用は損害額の10%、遅延損害金は事故日から支払い日まで年3%もしくは5%※で認められます。※交通事故の発生時期によって異なります。
そのため、裁判で解決した場合には、損害額以外にもかなりの額の金額を獲得できるということになります。
例えば、損害額が1000万円だった場合で、支払いが事故日から4年後だったとします。弁護士費用は損害額の10%ですので100万円になります。遅延損害金は事故日から4年が経過すると12%もしくは20%になります。
遅延損害金は、損害額と弁護士費用を加算した合計額に対して発生するので以下の金額になります。
1000万円+100万円=1100万円
遅延損害金5%の場合 1100万円×20%=220万円
遅延損害金3%の場合 1100万円×12%=132万円
その結果、賠償金総額は以下のとおりとなります。
遅延損害金5%の場合 1000万円+100万円+220万円=1320万円
遅延損害金3%の場合 1000万円+100万円+132万円=1232万円
示談や裁判外の解決機関ですと、弁護士費用や遅延損害金はつきませんので、賠償金は1000万円だけとなってしまいます。
差額は320万円もの金額になります。
最大限の賠償金を獲得したい場合には裁判を起こした方がいいということをお分かりいただけたと思います。
刑事裁判の対応も民事裁判の対応も弁護士に依頼しよう
被害者が死亡してしまったような交通事故(死亡事故)の場合、ご遺族は、刑事裁判の場合には被害者参加人として、民事裁判では加害者に対する損害賠償請求の当事者として裁判に参加する可能性があります。
刑事裁判の被害者参加制度では、裁判で意見陳述をしたり、被告人の量刑について意見を述べたり、被告人に質問することができます。
これらの被害者参加人ができることは、検察官が案内してくれることもありますが、弁護士を付けた方が被害者のご遺族も負担なく刑事裁判に参加することができます。
そのため、被害者参加人として刑事裁判に参加する場合には、刑事裁判の対応を弁護士に依頼することをおすすめします。
民事裁判の場合は、被害者や被害者のご遺族が損害賠償請求の当事者になりますので、請求の根拠となる主張や証明を被害者や被害者のご遺族がしなければなりません。
多くの方が裁判での主張や証拠に基づいて証明をするということをやったことがありません。
交通事故の民事裁判は、被告側は交通事故の民事裁判に慣れた保険会社の顧問弁護士が付きますし、賠償金の金額も徹底的に減額しようとしてきます。
保険会社の顧問弁護士と民事裁判で対等に戦うためには、被害者側も交通事故に強い弁護士に依頼する必要があります。
交通事故の民事裁判の対応は交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
クロノス総合法律事務所では無料で刑事裁判の被害者参加人の対応をしていますし、民事裁判も自己負担なしでご依頼いただけますので一度ご相談ください。
関連記事
交通事故の解決方法には示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)がある
交通事故の解決方法には、示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)があります。
示談は、加害者もしくは加害者側の保険会社と交渉をして賠償金について合意をして示談書を交わして解決をするという解決方法になります。
裁判は、加害者を被告として裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、判決もしくは和解という形で解決するという解決方法になります。
加害者が被告となりますが、加害者が任意保険に加入していれば、通常は保険会社の顧問弁護士が被告の代理人となります。
裁判以外の解決機関(ADR)とは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのことをいいます。
センターから嘱託を受けた弁護士が被害者と保険会社の主張を確認した上で、示談をあっせんして解決するという解決方法です。示談と裁判の中間的な解決方法です。
解決方法ごとのメリットとデメリット
示談のメリットとデメリット
示談のメリットは、早期に解決をできるという点にあります。
示談のデメリットは、裁判やADRに比べると獲得できる賠償金(示談金)の総額が低くなってしまうことが多いということです。
示談には、裁判のときに認められる弁護士費用や遅延損害金の支払いはありません。
また、示談では、保険会社が提示する賠償金(示談金)が裁判やADRよりも低額であることが多いです。
なぜかというと、保険会社は、示談の場合には被害者側に弁護士がついても慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した70%から80%で提示すればいいと考えているためです。
また、示談の場合、弁護士基準以上の慰謝料の増額が認められないなど形式的な解決しかできないというデメリットもあります。
裁判のメリットとデメリット
裁判のメリットは、慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算された賠償金とそれを前提とした弁護士費用(賠償金の10%)と遅延損害金(事故日から年3%もしくは5%※)が認められるため、賠償金の総額が最も高くなるという点にあります。※交通事故の発生時期によって異なります。
裁判の場合、示談やADRでは認められない弁護士費用という損害項目と遅延損害金が認められるため、基本的には獲得できる賠償金が最も高額になります。
裁判のデメリットは、解決までに時間がかかるという点です。
裁判は、通常で和解成立までに6ヶ月~10ヶ月、判決までに1年から2年の時間がかかります。
責任の有無、後遺障害の有無、過失割合などが争われると、事案によっては裁判を起こしてから解決までに3年以上もかかる裁判もあります。
実際に当事務所でも裁判を起こしてから解決までに3年以上かかった事案があります。
解決までに時間がかかる以外のデメリットは、時間がかかるというデメリットにもつながるのですが、示談の時には争われていなかった事項が裁判になると争われて、証明できなければ賠償金が減額される可能性があるという点です。
特に後遺障害の有無については、自賠責で後遺障害が認定されたても裁判所は自賠責の判断に拘束されませんので、後遺障害があることをきちんと説明できないと後遺障害の存在が否定されてしまうこともあります。
後遺障害の存在が否定された場合、逸失利益と後遺障害慰謝料が0円になってしまうので、結果的に示談の時よりも低額の賠償金しか獲得できなかったり、賠償金を全く獲得できないという事態が生じます。
そのため、なんでもかんでも裁判にすれば示談よりも高額の賠償金を獲得できるというわけではなく、裁判になった時に保険会社側から争われる争点を見極めてそれがきちんと証明できるという確信がなければ裁判での解決は選択しない方がいいです。
交通事故で示談で解決するのではなく裁判で解決した方がいい事案は、加害者の責任が明らかな被害者が死亡した事故(死亡事故)です。
死亡事故は、当然ですが後遺障害はありませんので、争点になる可能性があるのは、加害者の責任と過失割合です。
加害者の責任が否定される可能性のある事案は、示談での解決も検討した方がいいです(ただし加害者の責任が否定される事案では当然保険会社側も示談で0円の回答しかしてこないこともあるのでいずれにしろ裁判にしなければならないということもあります)。
加害者の責任が明らかな死亡事故の場合、最も大きな争点は過失割合になることが多いです。
過失割合は、事故態様によってある程度決まっていますので、仮に裁判で被害者に不利な判断となったとしても、弁護士費用と遅延損害金でカバーできてしまうことが多いです。
そのため、加害者の責任が明らかな死亡事故の場合は、示談で保険会社から提示された賠償金を下回る可能性が低いので裁判で解決した方がいいということになります。
裁判以外の紛争解決機関(ADR)のメリットとデメリット
裁判以外の解決機関(ADR)での解決のメリットは、裁判よりは時間がかからず基本的には弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提とした賠償金で解決することができるという点です。
日弁連交通事故相談センターは、まれに弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料にならないこともあったのですが、交通事故紛争処理センターは、弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提として解決します。
そのため、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合などが争われておらず、単に慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算した金額よりも下回っているという事案の解決ではベストな解決方法になります。
デメリットは、弁護士費用や遅延損害金が認められないので、賠償金の総額が裁判よりも低くなってしまうという点です。
また、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合など刑事記録や医療記録に基づいて主張立証が必要になる事案には向いていないというデメリットもあります。
示談、裁判、ADRどの解決方法にするべきか?
上記3つの解決方法のうちどの解決方法が一番いい解決方法かというのは、事案によって異なってきます。
例えば、死亡事故で、ご遺族の生活が当面の間成り立っているような場合には、早期に解決をする必要はありませんので、ご遺族のお気持ちや将来のご遺族の生活のために賠償金の総額が高くなる裁判を選択するのが最も理にかなっています。
弁護士費用も、弁護士費用特約があれば、ご遺族にご負担いただくことはありませんし、弁護士費用特約がなくても賠償金を取得した時に報酬を支払えばいいという弁護士が増えていますので、負担も少なくすみます。
交通事故のベストな解決は、事案によって異なってきます。
保険会社から示談書にサインを求められていても安易にサインせずに、一度、どのような解決がベストなのか弁護士にご相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで交通事故の解決について無料で相談できます。
解決実績
70代女性 高次脳機能障害9級 関節機能障害12級 併合8級 約2100万円獲得(高齢女性の休業損害と逸失利益を獲得!)
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
関連記事
交通事故の賠償請求のために依頼した弁護士の交代はどうしたらいい?
むち打ち症で12級の後遺障害は認定されるか?
前回は,交通事故に遭ってむち打ち症などの神経症状しかない場合でも14級の後遺障害が認定されるので整形外科への通院を定期的にしましょうという話をしました。
今回は,神経症状で12級の後遺障害が認定されるケースについて話をしたいと思います。
逸失利益の労働能力喪失期間ので,むち打ち症の場合,12級で10年,14級で5年という話をよく聞きます。
そうすると,むち打ち症だけでも12級の後遺障害が認定されるケースがあるように思います。
12級の後遺障害が認定されるには症状の原因を裏付ける他覚的所見が必要です。
しかし,通常,医師がむち打ち症と言われるような頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断するのは他覚的所見がない場合です(ちなみに,他覚的所見とは画像や検査で異常が確認できることをいいます)。
そうすると,他覚的所見がない場合に診断される頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などのむち打ち症で,他覚的所見が必要な12級の後遺障害が認定されることはないのではないかという疑問が生じます。
これまで何件もの後遺障害の請求をしてきましたが,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群としか診断されていないケースで,12級の後遺障害が認定されることはないというのが実感です。
神経症状しかないときに12級の後遺障害が認定されるケース
では,痛みやしびれなどの神経症状しかないときに12級の後遺障害が認定されるのはどのような場合なのでしょうか。
代表的なのは骨折後に癒合不全が生じ神経症状が残ってしまったというケースです。
この場合,画像で骨折後の癒合が良好でないことを確認できるため,症状の原因を客観的に確認することができます。つまり,他覚的所見があるということになります。
次に神経症状12級が認定されるケースが多いと感じるのが、観血的整復固定術により骨折部をプレート等の固定材で固定して痛みやしびれの症状が残っているケースです。
このケースで難しいのが固定材を除去する場合です。
固定材を除去するのは、骨折部の癒合が良好な場合なので、固定材を除去すると後遺障害が認定されない可能性が高くなってしまいます。
まあ、後遺障害が認定されないということは後遺症が残っていないということなので悪いことではないのですが、賠償金は数百万単位で違ってきてしまうので、賠償という面では非常に悩ましいということになります。
以前に固定材を除去する前に症状固定にして後遺障害の認定を受けて、賠償を受けてから自費で固定材を除去する手術を受けたという事案を担当したことがあります。
結果的に後遺障害を認定されたからよかったものの、後遺障害が認定されなければ、賠償金は少ない、固定材除去の手術は自費になってしまうというリスクがあるので、お勧めできる解決方針ではありません。
そのため、基本的には医師と話をして固定材を除去するかを決めてくださいとアドバイスをしています。
また,外傷性の椎間板ヘルニアによって神経症状が生じたというケースでも12級の後遺障害が認定されることがあります。
ただし,椎間板ヘルニアと診断されていれば必ず12級の後遺障害が認定されるというわけではありません。
椎間板ヘルニアは加齢によって生じる経年性の椎間板ヘルニアもあり,経年性の椎間板ヘルニアでは後遺障害の認定はされないからです。
後遺障害は,交通事故に遭って外傷を負い,それによって症状が残った場合に認定されるものですので,これはやむを得ません。
後遺障害診断書に椎間板ヘルニアと記載されることは多いのですが,自賠責で外傷性の椎間板ヘルニアと判断されて12級の後遺障害が認定されるケースはあまり多くないように思います。
神経症状12級の後遺障害の認定のためには後遺障害診断書をしっかりと作成してもらおう
神経症状12級の後遺障害が認定されるためには、痛みやしびれの原因を確認できる他覚的所見が必要ですが、自覚症状を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらうことも重要です。
これは、どの後遺障害にも共通して言えることですが、自覚症状がしっかりと記載されていなかったために後遺障害が認定されなかったということがよくあります。
特に神経症状の場合は、痛みやしびれが出現する場面を限定して記載してしまい、後遺障害が認定されないということがあります。
後遺障害は、交通事故による怪我の症状が残存している状態ですので、普段は痛みはないけど、例えば、寒いときだけ痛みが出現すると後遺障害診断書に記載してしまうと、神経症状の後遺障害が認定されず非該当になってしまう可能性が高くなります。
神経症状の後遺障害が認定されるためには、神経症状が出現する場面を限定せずに、「骨折部に痛み、しびれ」と自覚症状の欄に記載した方がいいということになります。
神経症状12級の後遺障害の賠償金(示談金)の相場
神経症状12級の後遺障害は、後遺障害の慰謝料だけで290万円(弁護士基準)になります。
逸失利益は、労働能力喪失期間を10年間に制限されてしまうため、ほかの後遺障害に比べてそれほど高額にはなりませんが、それでも一般的には400万円から1000万円程度の金額になります(収入によって金額が変わってきます。)
これに、入通院の慰謝料が90万円から120万円になりますので、慰謝料と逸失利益だけで500万円から1200万円の賠償金(示談金)になります。
被害者の過失があるかなどの事案にもよりますが、保険会社から提示された賠償金(示談金)がここで説明した金額を下回るようであれば、示談せずに弁護士にご相談することをお勧めします(クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで賠償金(示談金)の適正金額について無料でアドバイスしています)。
解決実績
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
関連記事
むちうち(むち打ち症)でも後遺障害は認定される!
交通事故の中で最も多く発生する事故は追突事故です。
もっとも、追突事故で重度な後遺障害(後遺症)が残るような大怪我をすることはあまりありません。
追突事故で負う怪我は,一般的にむちうち(むち打ち症)といわれる頚椎捻挫や外傷性頚部症候群がほとんどです(むちうち(むち打ち症)の賠償については「むち打ち症」をご確認下さい。)。
むちうち(むち打ち症)は,頚部痛,頭痛,めまい,しびれなど様々な症状が出現します。
このような症状を神経症状といいます。
多くのケースでは,症状は軽く,時間が経てばいずれなくなります。
そのため,追突事故に遭って病院を受診すると,多くの医師はレントゲン検査だけをして,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断して,あまりしっかりとした検査や治療をしてくれないということが多くあります。
症状はあるけど,あまり効果のある治療を受けられないし,診察を受けるまでに待ち時間がかかるため,だんだんと病院に通院することが面倒になってきます。
しかし,頚部痛などの神経症状は,はっきりと目で見て確認することができませんのでほとんどのケースが自覚症状しかありません。
そのため、定期的に通院をしているという客観的事実が,後遺障害の認定において重要な意味を持ちます。
多くの方がむちうち(むち打ち症)のように神経症状しかない場合には,後遺症は残っていない、後遺障害は認定されないと考えてしまいます。
しかし、そのようなことはなく神経症状しかない場合でも14級の後遺障害が認定されるケースというのは多くあります。
神経症状14級の後遺障害の認定に必要なことやってはいけないこと
神経症状14級の後遺障害が認定されるためには,先ほど説明したように定期的に通院をしているという事実が重要になります。
具体的には,1ヶ月以上の間隔をあけずに6ヶ月以上、合計の通院日数が100日前後で整形外科に通院をしていれば14級の後遺障害が認定される可能性があります。
反対に神経症状で14級の後遺障害が認定されないケースというのは,①通院の間隔が1ヶ月以上空いている場合,②通院期間が6ヶ月未満の場合,③整形外科に通院していない場合です。
特に,③の整形外科に通院をしていない場合というのは,接骨院や整骨院に通院していたけど整形外科に通院していなかったという場合も含まれます。
自賠責では,接骨院や整骨院への通院は,後遺障害の認定との関係では通院していたという扱いにしないので注意が必要です。
損保会社は後遺障害が認定されないように治療費の支払いを6ヶ月未満で打ち切ってくる!
神経症状14級の後遺障害は、むちうち(むち打ち症)などの場合は、自覚症状しかないため、後遺障害の認定の条件として通院の実績が重要な意味を持ちます。
当然、損保会社も通勤の実績が多くなれば、神経症状14級の後遺障害が認定されやすくなるということを知っています。
以前は、損保会社の担当者の中にも、交通事故の被害に遭ったのっだから後遺障害が認定されないと被害者がかわいそうという気持ちがあったのか、6ヶ月以上の通院を認めて治療費の支払いに応じることもありました。
しかし、自動車の利用が減少し、それに伴い自動車保険の契約も減少しているという現状では、損保会社の担当者は、できる限り支払う賠償金を少なくしようとします。
そのため、今では損保会社の担当者は、追突事故などのそれほど重い事故でない場合、治療費の支払いは6ヶ月以内に打ち切ってくることが多いです。
最近では、さらに打ち切りまでの期間が短くなっており、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告してくる損保会社も多くなってきました。
このような場合、損保会社の治療費の打ち切りに合わせて通院を止めるのか、それとも健康保険に切り替えて治療費の3割分を自己負担して通院するのかは、非常に難しい判断です。
せっかく神経症状14級の後遺障害が認定される可能性があるのに、損保会社が治療費の打ち切りを言ってきて治療費を自己負担したくないといって通院を止めてしまうと、200万円近くを損してしまう可能性があります。
もちろん、症状がないのに賠償金のためだけに通院するのはよくありませんが、症状があって後遺障害が認定されるべき状態にあるのに通院を止めてしまうと適正な賠償を受けられないということになってしまいます。
症状が残っているのに損保会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、その後の通院について交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
神経症状14級の後遺障害の賠償金(示談金)は弁護士に交渉を依頼して増額できる!
神経症状14級の後遺障害は、後遺障害の慰謝料だけで110万円(弁護士基準)になります。
逸失利益は、労働能力喪失期間を5年間に制限されてしまうため、ほかの後遺障害に比べてそれほど高額にはなりません。
それでも一般的には70万円から150万円程度の金額になります(収入によって金額が変わってきます。)。
これに、入通院の慰謝料が90万円から100万円になりますので、慰謝料と逸失利益だけで250万円から350万円の賠償金(示談金)になります。
しかし、損保会社は、神経症状14級の後遺障害が認定されていても、慰謝料は弁護士基準の60%程度の金額でしか被害者に提示してきません。
それでも自賠責よりも高い金額になっていますといって被害者を納得させようとします。
また、逸失利益についても、むちうち(むち打ち症)で神経症状14級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失期間は5年に制限されてしまうことが多いのですが、損保会社は5年よりも短い2年から3年の労働能力喪失期間で逸失利益を計算していることがあります。
そうすると、神経症状14級の後遺障害が認定されていても、逸失利益は30万円から40万円くらいにしかならないことが多いです。
逸失利益は、収入によって金額が変わってきます。
しかし、神経症状14級の後遺障害が認定されている場合には、専業主婦でも年収380万円程度を前提として、逸失利益は85万円以上になります。
収入が多い方が神経症状14級の後遺障害が認定された場合には、逸失利益だけで150万円程度になることもあります。
神経症状14級が認定された場合には、損保会社から賠償金(示談金)の提示があってもすぐに示談してはいけません。
神経症状14級の後遺障害がい認定された場合の賠償金(示談金)は、弁護士に交渉を依頼することで増額できます!
被害者の過失があるかなどの事案にもよりますが、損保会社から提示された賠償金(示談金)がここで説明した金額を下回るようであれば、示談せずに弁護士にご相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所は神経症状14級の後遺障害が認定された被害者の方の賠償金(示談金)がどのくらいの金額になるのか無料で査定しております。
ぜひご相談ください。(クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで無料でご相談できます。)。
解決実績
50代男性 追突事故 後遺障害14級(むち打ち) 300万円で解決(2ヶ月で135万円増額)
事故直後からご依頼を受けて後遺障害14級(むち打ち)認定 320万円で解決
専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決
30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得
40代男性 左足首骨折 14級9号 585万円獲得(示談の提示金額よりも460万円も増額して解決!)
30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)
関連記事
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。